保険業界ではAI革命が押し寄せていますが、以下のような悩みによって導入に踏み切れない方も少なくありません。
「保険業界にAI導入を検討しているが、事業価値を生み出す活用法を見極めたい」
「人材の代替というネガティブな印象ではなく、業務効率化というポジティブな文脈でAIを捉えたい」
そこで今回は、保険業界における生成AIの現状や具体的な活用事例、メリットを解説します。
【記事を読んで得られること】
- 生成AIが保険業界でどのように活用されているか
- 業務効率化やコスト削減に繋がるAI導入のメリット
- AI導入における課題とその対策
AIを「共に働くスキル」として捉え、自社のビジネスを効率化させるヒントも掲載しているので、ぜひ参考にしてみてください。
保険業界における生成AI活用の現状
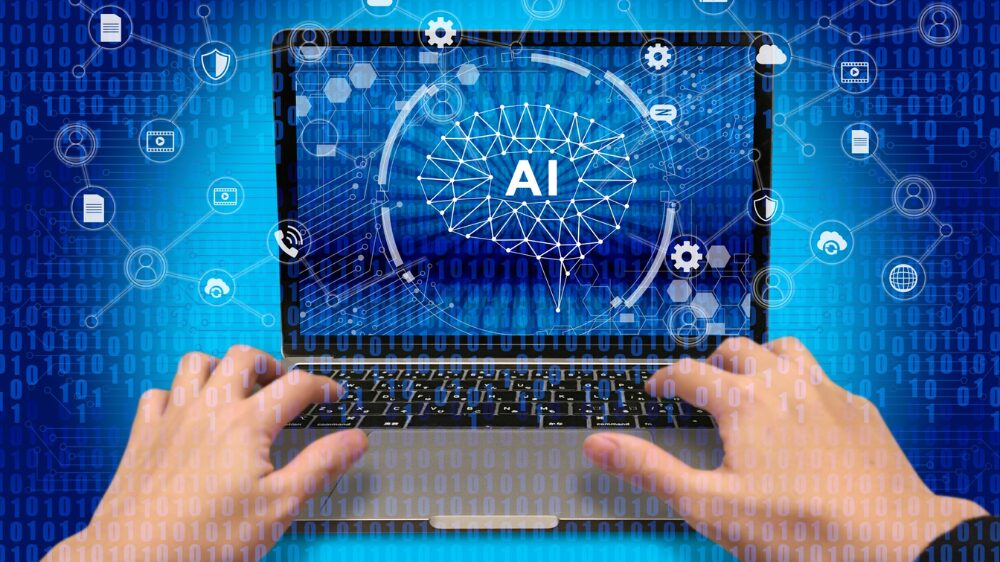
保険業界では、生成AIの活用が加速しているのはご存じでしょうか。この技術は、パターンやデータを学習して自動でコンテンツを生成できる点が特長です。
ChatGPTの登場以降、国内の生命保険会社を中心に導入が進み、2025年7月時点では業務効率化や生産性向上を目的とした導入が多く見られます。
一方、顧客体験の強化を目指す商品・サービス開発にも活用が広がり、新たなビジネスモデル創出の可能性も高まっています。
AIやIoTを組み合わせた保険テクノロジー(インシュアテック)の取り組みも進展し、現場業務と商品設計の両面で変革が起きつつあるといえるでしょう。
保険業界で生成AIを活用する5つのメリット

ここでは、保険業界で生成AIを活用するメリットを5つ紹介します。
- 査定や審査の精度とスピードが向上する
- 最適な保険プランを提案できる
- 顧客対応が効率化できる
- 事務作業が省力化できる
- 不正請求や解約リスクを検知できる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
査定や審査の精度とスピードが向上する
生成AIは社内業務を効率化し、処理のスピードと精度を高めます。
SBI日本少短は、家財保険事故に関する過去の支払事例をAIに学習させ、社内FAQ検索エンジンとして運用。担当者が資料を探す手間を削減し、判断の迅速化にもつながりました。
楽天生命では、加入希望者の健康情報をAIで分析し、入院リスクの予測によって査定を自動化しています。
東京海上日動では、自動車修理の見積点検にAIを活用し、損傷内容から妥当な修理方法を導き出しています。
最適な保険プランを提案できる
AIは契約者のデータを分析し、最適な保障内容の提案を可能にします。
第一生命は1,700万件の保障設計データをもとに、顧客の意向に合ったプランをレコメンドするAIシステムを開発。
アクサダイレクトでは、過去の契約と顧客情報を活用した補償提案機能を導入し、成約率が1カ月で5%向上しました。
こうしたAI活用により、保険募集人は効率よく一人ひとりに合った提案ができるでしょう。
顧客対応が効率化できる
AIチャットボットや音声応答の導入により、問い合わせ対応を自動化できます。
三井住友海上は、業界初のチャットボットで控除証明書の再発行などに対応。SBI生命は、生命保険料控除証明書の再発行をAIで受け付け、処理まで自動化しました。
太陽生命は、生成AIによるアバターを使った保険募集の実証実験を実施し、実業務への活用を模索しています。
AIの活用により、人件費の抑制だけでなく、記録保存や感情分析による対応品質の向上にもつながるでしょう。
事務作業が省力化できる
生成AIは申込書や見積書の作成業務を自動化し、事務負担を軽減します。
アフラックの「Aflac Assist」は、マニュアル検索の時間を3割削減し、業務効率も15%向上。
日本生命はAI-OCRで契約申込書の処理を効率化し、新契約処理コストを最大5割削減しました。
住友生命では、本人確認書類をAIで判定し、ペーパーレス化とセキュリティ確保の両立を実現しています。
こうしたAIの導入により、正確な処理と時間短縮が可能になるでしょう。
不正請求や解約リスクを検知できる
AIは過去データを分析し、不正請求や解約の兆候を早期に検知できます。
東京海上日動は、不正請求の特徴をAIで抽出し、リスクの低い請求は迅速に対応できる体制を構築しました。メットライフ生命の「Force」は、給付金の不正検知精度を向上させています。
AI活用により、顧客満足度を維持しつつ、収益機会の損失を防げるでしょう。
日本の保険業界における生成AIの活用事例16選

ここでは、日本の保険業界における生成AIの活用事例を16社紹介します。
- 日本生命
- 第一生命
- 明治安田生命
- 住友生命
- アフラック
- SBI生命
- 楽天生命
- 太陽生命
- オリックス生命
- ライフネット生命
- 東京海上日動
- 損保ジャパン
- 三井住友海上
- あいおいニッセイ同和
- アクサダイレクト
- SBI損保
それぞれ詳しく見ていきましょう。
日本生命
日本生命は、生成AIを活用した業務支援ツール「コパイロット」の実証を進めています。
2024年度中に10件の実証を予定し、すでに300人を対象に試験導入を実施。1日あたり平均18分の業務時間削減が確認され、94%の社員が継続利用を希望しています。
内勤職の業務負担を最大3割削減する目標も掲げており、全社導入に向けた取り組みが加速しています。
第一生命
第一生命は、生成AIを使ったチャットサービス「ICHI-to-Chat」の実証を実施しました。LINE公式アカウントを活用し、保険に不慣れな層にも気軽に備えを考える機会を提供。
2024年5月16日〜6月6日に実施された実証では、約1万人の方が利用し、チャット途中でのアンケートに回答いただけた約2,000名のうち73%が会話に「満足」または「やや満足」と回答しました。
今後も最適な情報提供を目指し、本格的にAI導入を検討していると発表しています。
明治安田生命
明治安田生命は、引受査定にAIを活用した「健活未来予測モデル」を導入しました。
匿名医療ビッグデータとAIによるリスク予測を組み合わせることで、精度の高い査定と未加入層への対応を可能にしています。
約130万件の匿名医療ビッグデータを活用し、健康診断書をご提出いただいた契約年齢50歳以上のご契約者に適用。2025年1月6日発売の「循環器病対策Pro」を対象に本格導入されました。
新たな顧客層の獲得にもつながっています。
住友生命
住友生命は、営業職員の支援を目的に、AI搭載の顧客情報管理システムを導入しました。
営業活動で得た顧客の意向や状況をAIが分析し、リマインドや提案タイミングを自動で通知。アイスブレイクのヒントや上司への共有補助など、育成や顧客対応の質向上に役立っています。
全国3万人の営業職員のスキル底上げにもつながる取り組みです。
アフラック
アフラックは、代理店業務を支援する生成AIシステムを本格運用しています。
メール作成や資料検索などを自動化し、事務負担を軽減しながら顧客対応に集中できる環境を整備しました。
資料検索では社内ポータル内の情報を参照し、回答文と関連リンクを生成する機能が注目されています。
SBI生命
SBI生命は、社内サービスデスク業務の一部にAIオペレーター対応を導入し、業務効率化を進めています。
アカウントロック解除では、声紋認証から処理・通知・監査記録作成までを一括で対応。複雑化・増加する社内問い合わせに対し、よりスピーディなサービス提供が可能となっています。
今後は対応範囲を広げ、コールセンター業務にもAIを展開する予定です。
楽天生命
楽天生命は、日立製作所と共同で、保険引受業務の自動化に生成AIを活用しています。
「Risk Simulator for Insurance」を使い、健康状態から将来の入院リスクをAIが予測。
申込時に告知する健康状態や過去の病歴情報から予測したリスクに基づき、保険引受の諾否判定処理の自動化を実現し、手続きの迅速化と満足度向上を実現しました。
査定業務の平準化にもつながり、事業拡大への対応力も強化しています。
太陽生命
太陽生命は、ネオス株式会社および株式会社NSDと共同で、生成AIを活用した生命保険募集プロセスの実証実験を実施しました。
生成AIによる顧客との会話を通じた情報収集と外部システムとのデータ連携、要望に応じた保険プランの自動修正などを検証。
商用化に向けた可能性が示された一方、反応速度や誤情報への対策など、今後の検討課題も明確になりました。
オリックス生命
オリックス生命は、従来引受が難しかった傷病者層への対応強化を目的に、AIによる新査定ルールを構築中と発表しています。
この取り組みでは、フランスの再保険会社SCOR SEのAIモデル「バーチャルアンダーライティング(VUW)」を活用し、保険会社が持つビッグデータに基づいて傷病ごとの給付発生率をシミュレーションします。
これまで特別条件付きでしか引き受けられなかった傷病について、約90%のケースで無条件引受が可能になる見通しです。
ライフネット生命
ライフネット生命は、自社開発の大規模言語モデル(LLM)を社内で導入し、業務効率化と文化浸透を図っています。
2025年1月時点で、正社員の87%が一度以上利用し、アクティブ率は54%を記録。「AI歌人チャレンジ」など、業務外でもAIに触れる機会を設けたことが社内定着を後押ししました。
導入は段階的に進められ、全社での活用が拡大中です。
東京海上日動
東京海上日動は、PKSHA Technology、株式会社AlgoNautと共同で、複雑性の高い保険業務に特化した照会応答システム「AI Search Pro」を2024年11月に本格導入を開始しました。
検索AIと生成AIを組み合わせて回答案を自動生成し、照会対応にかかる時間を約4割削減。
火災・傷害など複数の保険種別に対応しており、社員の業務負担軽減と対応品質の向上につながっています。
損保ジャパン
損保ジャパンは、生成AIを活用した照会回答支援システム「おしそん LLM」を2025年6月より全国営業店で運用。約4割の業務時間削減効果を実現しました。
損保ジャパンが保有する膨大なマニュアルやQ&Aを学習したAIが、営業店や代理店からの問い合わせに対する回答案を生成。
業務時間を約4割削減した実績があり、担当者による確認を前提に誤情報の抑制にも配慮しています。
三井住友海上
三井住友海上は、NECと共同で事故対応業務の通話内容を自動要約するシステムを開発しました。
音声認識技術で通話をテキスト化し、「Azure OpenAI Service」で内容を即時に要約。記録作成にかかる手間を大幅に削減し、顧客対応の質向上と時間創出につなげています。2024年内に全国の保険金支払いセンターへ導入予定と発表しています。
あいおいニッセイ同和
あいおいニッセイ同和損害保険は、株式会社Archaicと共同で、国内初となる「生成AI専用保険」の提供を開始しました。
知的財産権侵害や情報漏えい、ハルシネーションなどのリスクに対応し、調査・相談・再発防止費用も補償対象に含まれています。
また、保険だけでなく、Archaicが提供するガバナンス体制構築支援や事故後のコンサルティングサービスもパッケージで提供され、事故の未然防止と早期回復を支援している点が特徴です。
アクサダイレクト
アクサダイレクトは2020年にダイレクト型自動車保険業界で初めて、AIを活用した「補償おすすめ機能」を導入しました。
100万件以上の契約内容を含む匿名化したビッグデータと、顧客が入力した情報をもとに、AIがリアルタイムで補償内容を提案。
導入からわずか1カ月で成約率5%向上という成果を上げており、顧客が自身の潜在ニーズに合った補償を納得して選択できるようサポートしています。
同社のデジタル化推進の中核となる施策です。
SBI損保
SBI損保はアルティウスリンク株式会社と共同で、2025年4月から自動車事故受付センターでの顧客体験(CX)向上を目的としたAI活用実証実験を開始しました。
コンタクトセンターにおいて、「Altius ONE for Support」というAI活用システムを導入し、お客様との通話内容の要約やVoC(Voice of Customer)分析にAIを利用しています。
オペレーターが通話後に要する後処理時間の35%削減を目標に、商品改善や満足度向上につなげるデータ活用が進められています。
保険業界における生成AI導入の5つの課題

最後に、保険業界における生成AI導入の5つの課題を解説します。
- AI人材や開発予算が不足している
- AIの判断根拠が不透明になりやすい
- 個人情報の漏洩リスクが高まる
- 既存システムとの連携が難しい
- 法規制や業界ガイドラインに違反しないよう注意する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
AI人材や開発予算が不足している
AIの導入にはデータ分析やシステム構築に対応できる専門人材が必要です。しかし、AIに関する知見を持つ人材はまだ少なく、社内での育成も進んでいません。
AIの開発・運用には高額なコストがかかります。自社開発・外部委託を問わず、予算確保が障壁となるケースが多いといえるでしょう。
生成AI活用を浸透させるための研修やリテラシー向上も課題となっています。
AIの判断根拠が不透明になりやすい
生成AIは複雑な仕組みで動作するため、出力内容の理由を説明しにくい傾向があります。
特にディープラーニングを使ったシステムでは「なぜその結果になったのか」が不明確になりやすく、ブラックボックス化が問題視されています。
保険料の算出や査定業務などでは、根拠が説明できなければ顧客対応に支障が出るおそれがあるでしょう。そのため、出力の透明性を確保する体制の整備が欠かせません。
個人情報の漏洩リスクが高まる
保険業界では契約者の健康状態や収入情報など、機密性の高い個人データを扱います。
無防備なままAIツールを活用すると、情報漏洩のリスクが一気に高まる可能性があるでしょう。特に、社員が公的ガイドラインに沿わず外部の無料ツールを使用するケースには注意しなければなりません。
セキュリティ対策を講じた専用環境を構築し、社内ルールも整備するのがおすすめです。
既存システムとの連携が難しい
保険会社の多くでは、業務プロセスが属人化しており、レガシーシステムが長年使われています。
新たにAIを導入しても既存システムとの連携が進まず、データ活用や業務自動化に時間と費用がかかる場合が少なくありません。
システムの更新や業務フロー全体の見直しをして、AIが活用しやすい基盤を整えましょう。
法規制や業界ガイドラインに違反しないよう注意する
生成AIの進化に対し、法整備や業界ルールの対応が追いついていない現状があります。保険業界では、顧客保護や公平性の観点から法的なチェックが欠かせません。
たとえば、損保ジャパンではリスク評価とガバナンス体制を構築し、生成AIの運用を全社で管理しています。
導入前に法律・ガイドラインへの適合性を慎重に確認し、運用ルールや管理体制を整えましょう。
保険業界における生成AIの活用事例を参考にビジネスを効率化させよう
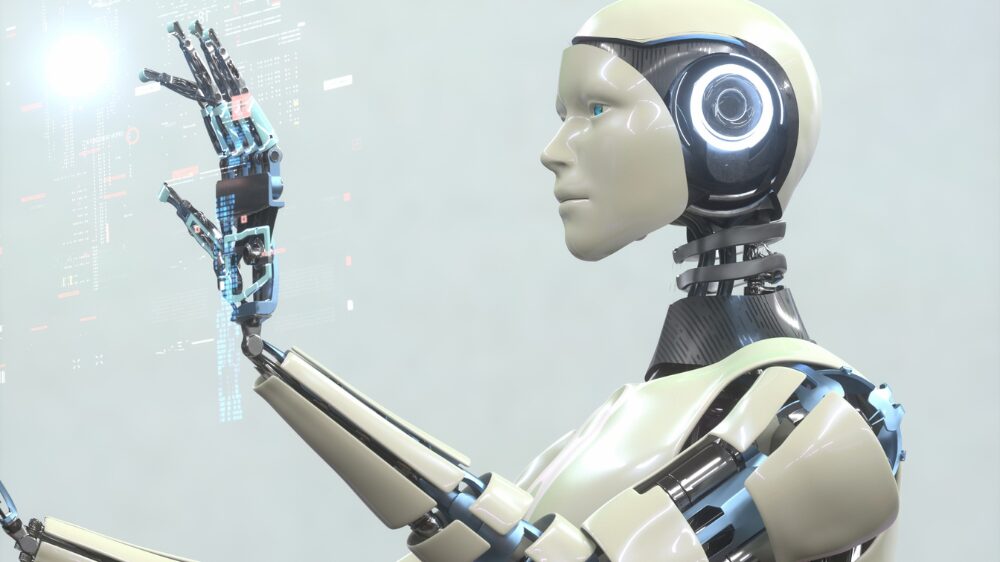
本記事では、保険業界の生成AI活用現状、多様なメリット、そして導入課題を解説しました。効率化や新価値創造に貢献する一方、人材・予算不足、リスク管理、システム連携などの課題も伴います。
【生成AI導入成功への対策】
- 中長期戦略を策定し高ROI目的を選定
- システムとルールでリスクを管理する
- 社員のAI活用スキルを向上させる
AIは「共に働くスキル」として、人の能力を拡張し、事業に役立つはずです。
保険業界におけるAI活用事例を参考に、導入の目的を定めたうえで自社に合うAI活用方法を見極めましょう。












