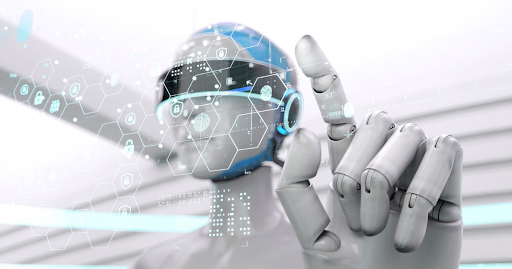生成AIは中小企業の業務効率化を支える強力なツールですが、以下のような悩みから導入に踏み切れない方も少なくありません。
「中小企業でも生成AIを導入して業務効率化している事例が知りたい」
「自社に合った生成AI活用法がわからない」
そこで今回は、中小企業における生成AIの活用事例や導入のメリット・課題を詳しく解説します。
【記事を読んで得られること】
- 導入が進む中小企業のAI活用状況
- 競争力強化につながる5つのメリット
- 導入時の課題と使える補助金情報
自社での活用を見極めるヒントも紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
中小企業で生成AI導入している活用状況とは
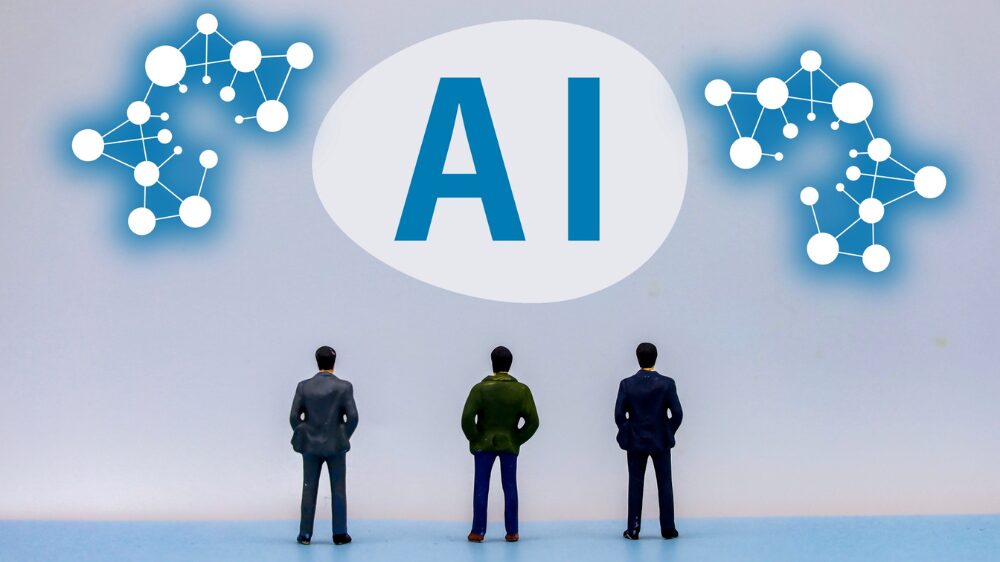
中小企業における生成AIの導入は年々増加しています。東京商工会議所の2024年調査では、導入済みが11.7%、検討中が33.5%となり、前年比でいずれも拡大しました。
導入が遅れることで競争から取り残される可能性が高まっており、先行企業では、業務効率化・サービスの差別化・人手不足対策など複数の成果が報告されています。
特に従業員数の少ない企業では、生成AIを業務改善や売上強化に直結する手段として期待する声が少なくありません。
参考:中小企業のための「生成AI」活用入門ガイド|東京商工会議所
中小企業で生成AIを導入するべき5つの理由
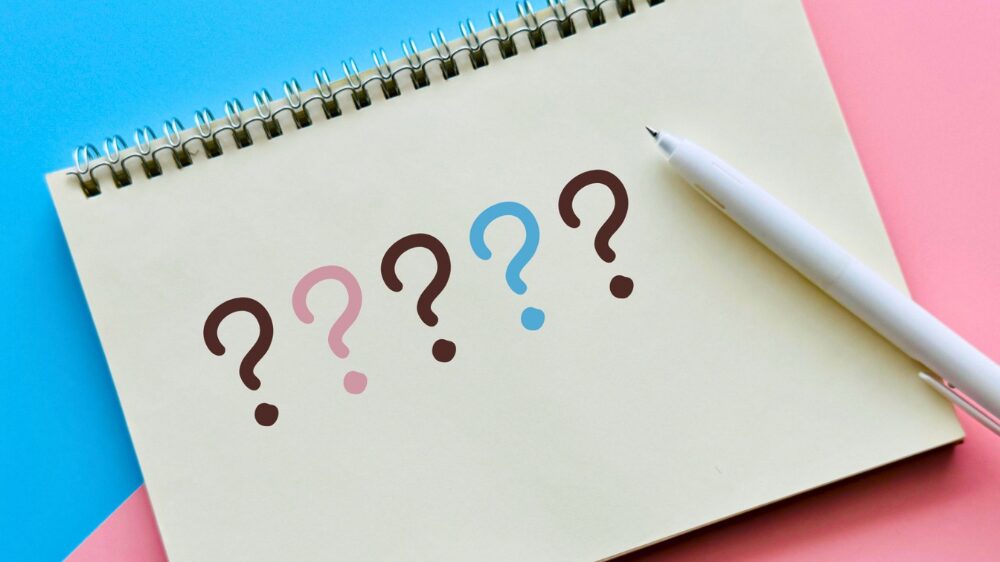
ここでは、中小企業で生成AIを導入するべき理由を5つ紹介します。
- 市場変化に柔軟に対応し競争力を高められる
- 業務の無駄を省き生産性を向上できる
- 人手不足を補い労働負担を軽減できる
- 経営資源を最適に配分してコストを抑えられる
- 新たな商品やサービスの創出につなげられる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
市場変化に柔軟に対応し競争力を高められる
生成AIは、売上推移や需要傾向などのデータを高速で分析し、精度の高い予測を実現します。
中小企業でも市場動向や顧客ニーズの変化に素早く対応でき、大手と同等のスピードで意思決定ができる点が強みです。過剰在庫や欠品のリスクを事前に察知し、仕入れや生産計画を調整できるため、運用効率の向上にもつながるでしょう。
生成AIを積極的に活用する企業は、業務改善とコスト削減の両立を実現する一方、導入の遅れは競争力低下に直結するため、早期の対応が求められるでしょう。
業務の無駄を省き生産性を向上できる
生成AIを活用すれば、人が対応していた反復的な定型業務を自動化できます。
データ入力・レポート作成・帳票処理などの作業を効率化し、AI OCRによる書類のデジタル化も実現可能です。従業員の負担が軽減され、人の手でしかできない業務へリソースを集中しやすくなるでしょう。
その結果、業務のスピードや精度が向上し、ヒューマンエラーの抑制にもつながります。全体として、生成AIの活用は業務品質の安定と生産性の底上げに効果を発揮するでしょう。
人手不足を補い労働負担を軽減できる
少子高齢化による人材不足は、多くの中小企業で深刻化しています。
生成AIによる業務の自動化は、人的リソースに依存する作業を減らし、担当者への業務集中や長時間労働の回避に役立ちます。生成AIの導入により、残業や休日出勤の削減が可能となり、従業員のワークライフバランスが整いやすくなるでしょう。
結果として、モチベーションの維持や定着率の向上にもつながり、採用コストの抑制にも有効です。従業員はより高度な判断やコミュニケーションが求められる業務に時間を使えるようになります。
経営資源を最適に配分してコストを抑えられる
生成AIの導入によって業務の無駄を削減し、コスト構造の見直しが進みます。
単なる人件費削減にとどまらず、処理時間の短縮やエラー防止により損失を抑える効果も得られます。紙書類の削減により印刷・保管コストの負担も軽くなり、全体の業務効率が改善されるでしょう。
中小企業にとっては、限られた予算の中で収益性を高める手段として、生成AIの活用が現実的な選択肢になりつつあります。
新たな商品やサービスの創出につなげられる
生成AIは、既存データの活用によって顧客ニーズの発見や新たな価値提案を支援します。
マーケティングや商品企画においても、発想の幅を広げるツールとして活用が進んでおり、少人数でも効率的なアイデア出しが可能です。顧客ごとの行動傾向を分析し、パーソナライズしたサービスの構築にも役立ちます。
こうした取り組みにより、企業は市場を広げ、収益源の多様化を図れるでしょう。成長戦略を実行するうえで、生成AIは中小企業にとって実用的なパートナーといえます。
中小企業における生成AI導入後の活用事例13選
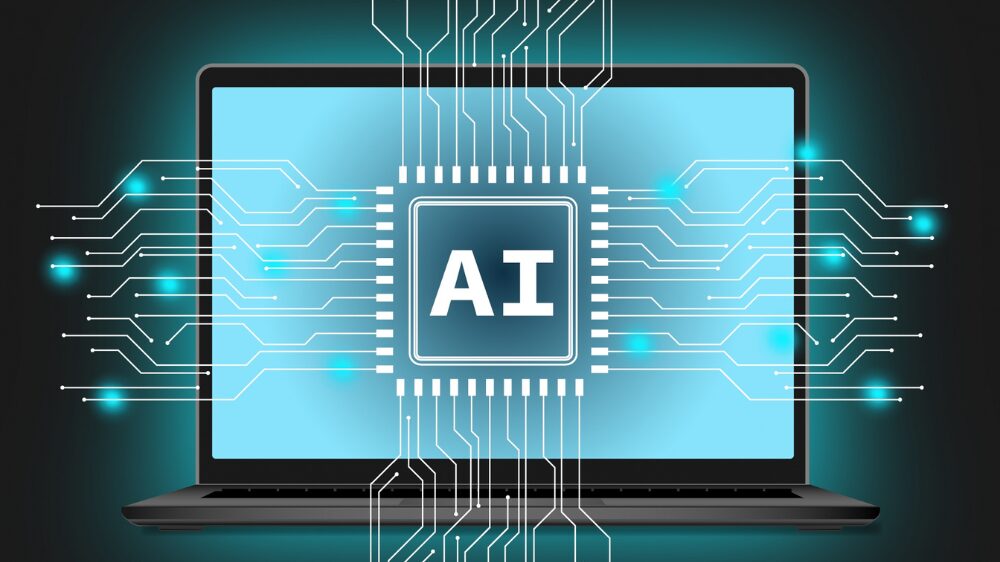
ここでは、中小企業における生成AI導入後の活用事例を13個紹介します。
- 図面データから見積書を自動で作成
- 受注数量を予測して在庫を最適化
- 来客数を予測して売上を改善
- SNS投稿文を自動で作成
- 会議の文字起こしと議事録を作成
- メールや社外文書を自動で作成
- プレゼン資料のたたき台を作成
- パッケージや広告の画像を作成
- チャットボットで顧客対応を自動化
- Excel関数を自動で作成
- 商品アイデアやコンセプトを提案
- 社内マニュアルやノウハウを要約して共有
- ショート動画を自動で作成
それぞれ詳しく見ていきましょう。
図面データから見積書を自動で作成
図面をもとに見積書を作成する業務は、特定の担当者に依存しやすく、時間もかかりがちです。
生成AIを活用すると、図面から加工の難易度を判定し、見積り金額を自動で算出する仕組みを構築できます。この仕組みを導入すれば、営業担当者に限らず他の社員でも対応できるようになり、見積書作成にかかる時間を短縮できるでしょう。
属人化が解消され、対応スピードが安定しやすくなります。
受注数量を予測して在庫を最適化
発注内示と実際の受注数に差があると、余剰在庫や欠品が発生しやすくなります。
生成AIに製品ごとの発注情報や納品実績を学習させることで、受注数量の予測精度を高められるでしょう。予測に基づいて仕入れや在庫管理を見直せば、無駄な在庫や欠品を防げます。
物流のムダも抑えられ、在庫や配送の調整がしやすくなるでしょう。
来客数を予測して売上を改善
気象条件や周辺施設の状況によって来客数が変動しやすい業態では、天候・宿泊数・売上履歴などのデータをAIで分析し、来客数や注文傾向を予測できます。
予測結果をもとに仕入れ量や人員を調整すれば、廃棄ロスや品切れを防ぎやすくなるでしょう。ムダなコストを抑えつつ、接客対応もしやすくなります。
SNS投稿文を自動で作成
毎日SNSに投稿する文章を考えるのは、運用担当者にとって大きな負担になります。
生成AIを使えば、ターゲット層に響く投稿文を自動で作成でき、コンテンツ制作がぐっと楽になるでしょう。さらに、投稿のタイミングや内容の最適化も可能なため、フォロワーの反応を見ながら効果的な発信を続けやすくなります。
会議の文字起こしと議事録を作成
議事録作成は大切な業務ですが、参加者の手間がかかり、負担に感じる場合もあります。
生成AIを活用すれば、会議中の発言をリアルタイムで文字起こしし、要点をまとめた議事録も自動で作成可能。事後の整理に時間を取られずに済むため、参加者全員が議論に集中しやすくなるでしょう。
リモート会議でも内容の共有がしやすくなり、業務のすれ違いも防げます。
メールや社外文書を自動で作成
商品説明や報告書、問い合わせ対応メールなど、文章作成は日々の業務で頻繁に発生します。
生成AIを使えば、指示に沿った内容を自動で文章化でき、最適な表現やテンプレートを提案してくれます。
文章の作成にかかる時間を減らせれば、少ない人手でも対応しやすくなり、事務作業がスムーズに進むでしょう。
プレゼン資料のたたき台を作成
プレゼン資料の構成を考え、スライドをまとめる作業には多くの時間がかかります。
生成AIは構成案の整理からスライドのデザインまで支援でき、PowerPointと連携させられます。基本的な構成が短時間で整うため、企画段階からスムーズに動き出せるでしょう。
グラフや図の挿入もAIがサポートできるため、資料の完成度を上げやすくなります。
パッケージや広告の画像を作成
商品の魅力を伝えるパッケージや広告は、デザイン制作に手間と費用がかかる分野です。
画像生成AIを使えば、製品のイメージに合ったビジュアルを短時間で複数案作成できます。
少人数のチームでも販促物をスピーディーに用意できるようになり、外注コストを抑えながらデザインの選択肢を広げられるでしょう。
チャットボットで顧客対応を自動化
少人数の体制で多くの問い合わせに対応するのは大きな負担です。
AIチャットボットをWebサイトやLINEに導入すれば、よくある質問への対応を24時間自動でできます。電話やメールの対応件数を減らすことで、スタッフの手が空きやすくなり、対応の遅れや見落としを防ぎやすくなるでしょう。
予約の取りこぼしや機会損失も避けられるようになります。なお、個人情報を扱う場合は、自社開発やセキュリティ対策も検討が必要です。
Excel関数を自動で作成
複雑なExcel関数やマクロの作成には、専門知識と時間が求められます。
生成AIに計算内容や条件を入力するだけで、関数やマクロを自動で作成できます。作業の効率が上がり、時間に余裕が生まれるでしょう。
さらに、グラフや集計表も自動で作成できるため、報告や分析業務もスムーズに進められます。
商品アイデアやコンセプトを提案
新商品の企画やマーケティングの立案では、アイデア出しに時間がかかる場合もあります。
生成AIにターゲット層やテーマを入力すると、多様なアイデアを短時間で提案してくれます。思いつきにくい視点のヒントを得やすくなり、限られた時間でも新しい企画が進めやすくなるでしょう。
コンセプトメモやネーミングのたたき台としても使えます。
社内マニュアルやノウハウを要約して共有
蓄積されたマニュアルや業務ノウハウが社内で整理されずに放置されていると、情報を探すのに時間がかかります。
生成AIで社内資料を学習させたチャットボットを活用すれば、従業員の質問にすぐ対応できます。必要な情報をすぐに引き出せるため、業務のムダが減り、属人化の解消にもつながるでしょう。
結果として、仕事のスピードや精度が安定しやすくなります。
ショート動画を自動で作成
SNSで注目を集めるには、短くインパクトのある動画が効果的です。
動画生成AIを使えば、テーマや構成を指示するだけで、SNS向けのショート動画を自動で作成できます。編集スキルがなくても、見栄えの良いコンテンツをスピーディーに用意できるため、継続的な発信がしやすくなるでしょう。
動画を活用することで、問い合わせやサイトへのアクセス数も増やしやすくなります。
中小企業で生成AIを導入する際の5つの課題

ここでは、中小企業で生成AIを導入する際の課題を5つ紹介します。
- 初期導入費や運用コストが経営負担になりやすい
- AIに詳しい人材が社内に不足している
- 利用に必要なデータの管理に手間がかかる
- ハルシネーションによるリスクがある
- 情報漏えいの懸念がある
それぞれ詳しく見ていきましょう。
初期導入費や運用コストが経営負担になりやすい
生成AIの導入には、システム購入や初期設定費に加えて、月額利用料や保守費用などの継続的なコストがかかります。
業務内容に応じたカスタマイズが必要な場合、費用が高額になりやすく、中小企業にとっては重い負担となるケースもあります。また、生成AIの導入直後に効果が出にくい場合もあるため、投資に見合う成果が得られるかどうかを事前に見極めましょう。
なお、既存の汎用AIツールを活用すれば、独自開発よりも費用を抑えやすくなります。
AIに詳しい人材が社内に不足している
生成AIを導入・活用するには一定の知識が求められますが、社内にITやAIのスキルを持つ人材がいない企業では、ツールの選定や運用がうまく進まない可能性があります。
外部の専門家に依頼する方法もありますが、その分コストがかかる点には注意が必要です。
ただし、近年はノーコードで操作できるツールも登場しており、専門知識がなくても扱いやすい環境が少しずつ整ってきています。
利用に必要なデータの管理に手間がかかる
生成AIの性能を十分に引き出すためには、データの整備が欠かせません。
高精度なアウトプットを得るには、目的に合ったデータを収集し、フォーマットを整えておく必要があります。しかし多くの中小企業では、情報が部門ごとに分散していたり、そもそも記録が十分に残されていなかったりするケースもあるでしょう。
大量のデータが必須というわけではありませんが、質の高い情報を整理できる体制は不可欠です。
ハルシネーションによるリスクがある
生成AIには、事実とは異なる内容をそれらしく出力してしまう「ハルシネーション」のリスクがあります。
この現象が社内資料や顧客対応文書に紛れ込むと、判断ミスや信頼の損失につながる恐れがあります。そのため、生成された文書は内容を確認し、正確性を担保する運用ルールをあらかじめ設けておく必要があるでしょう。
担当者によるチェック体制が欠かせません。
情報漏えいの懸念がある
生成AIを業務に取り入れる場合、社外に出せない情報がAIの学習に使われてしまうリスクがあります。特にクラウド型のAIサービスでは、セキュリティ体制が不十分な場合、データが第三者に漏れる恐れが生じます。
たとえば、顧客情報や契約内容が外部に流出すれば、企業の信頼や取引関係に大きな影響を及ぼします。こうした事態を防ぐため、生成AIの導入前にセキュリティ方針や提供元の安全対策を確認しておきましょう。
中小企業が生成AI導入に活用できる補助金4選
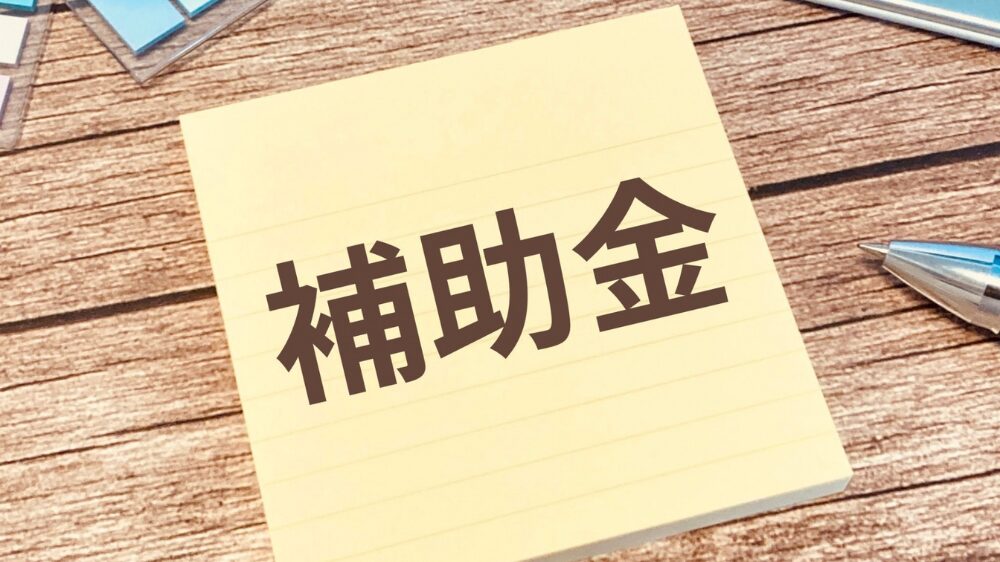
最後に、中小企業が生成AI導入に活用できる補助金を4つ紹介します。
- 中小企業省力化投資補助金
- 新事業進出補助金
- ものづくり補助金
- 小規模事業者持続化補助金
それぞれ詳しく見ていきましょう。
中小企業省力化投資補助金
中小企業省力化投資補助金は、人手不足の課題を抱える事業者に向けて、生産性向上や省力化を目的とした設備導入を支援する制度です。AIを活用して業務を自動化・効率化する取り組みは、補助対象の一例とされています。
なかでも「一般型」は、事業内容や業種に応じた柔軟な設備投資に対応しており、自社の業務プロセスに合ったAIシステムの導入も検討しやすくなるでしょう。
生産性が高まれば、付加価値の向上や従業員の賃上げにもつながる可能性があるため、AI活用を検討中の企業にとって有力な選択肢のひとつです。
ただし、補助の対象となるAIソリューションや申請要件・補助金額の上限などの詳細情報は、最新の公募要領を確認しましょう。
参考:中小企業省力化投資補助金とは|独立行政法人中小企業基盤整備機構
新事業進出補助金
新事業進出補助金は、既存事業とは異なる分野での新たな収益源を創出する取り組みに対して、設備やシステム導入費などの支援が受けられる制度です。
たとえば、AIを活用した市場分析システムの構築や、パーソナライズ技術を活かした新サービスの展開などが想定されます。こうした取り組みによって、高付加価値なビジネスを新たに構築しようとする企業にとっては、導入コストを抑えながらスタートを切る手段となるでしょう。
補助対象となる経費の範囲は広く、クラウドツールやシステム開発費なども含まれるため、AI導入を通じて新分野に進出する際に活用しやすい制度です。
参考:中小企業新事業進出補助金とは?|独立行政法人中小企業基盤整備機構
ものづくり補助金
ものづくり補助金は、中小企業が製品やサービスの開発・改善に取り組む際に活用されている代表的な補助制度です。AIを用いた新たな生産体制の構築や、デジタル技術による業務プロセスの刷新も対象になり得ます。
ただし、単純なAI導入だけでは補助対象にならない場合もあり、製品・サービスの開発を伴う必要があるのに注意しましょう。
補助金の利用を検討する場合は、AI技術を活かしてどのように業務や提供価値が変わるのかを明確にし、事業計画に落とし込む必要があります。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、販路拡大や業務効率化の取り組みに必要な経費を支援する制度です。比較的導入コストの低いAIツールの活用が想定されており、SNS運用支援ツールやチャットボットの導入も補助対象となる可能性があります。
AIを活用して顧客層を分析し、Web広告を最適化したり、店舗サイトにパーソナライズ機能を導入したりするケースが考えられるでしょう。
補助上限額は通常枠で50万円ですが、インボイス特例(50万円上乗せ)や賃金引上げ特例(150万円上乗せ)を活用することで、両特例併用で最大250万円まで拡充されます。コストを抑えてAI活用を始めたい事業者にとって、第一歩として活用しやすい制度です。
中小企業における生成AIの導入・活用事例を参考に自社ビジネスを効率化させよう

本記事では、中小企業が生成AIを導入するべき理由や活用状況、具体的な事例、そして導入時の課題と補助金について解説いたしました。AIは人手不足や業務負担の軽減、コスト削減に大きく貢献し、貴社の競争力を高める強力なツールとなるでしょう。
【生成AIを自社ビジネスに活用するポイント】
- 解決したい業務課題を明確にして、小規模な導入から始める
- 自社に近い活用事例を参考に、具体的な導入イメージを持つ
- 情報管理や誤出力の対策をして、補助金も併せて検討する
生成AIの導入は、業務効率化や生産性向上に留まらず、中小企業の成長を後押しする戦略的な投資といえるでしょう。ぜひ本記事を参考に、AI活用を活用してビジネスを効率化してください。