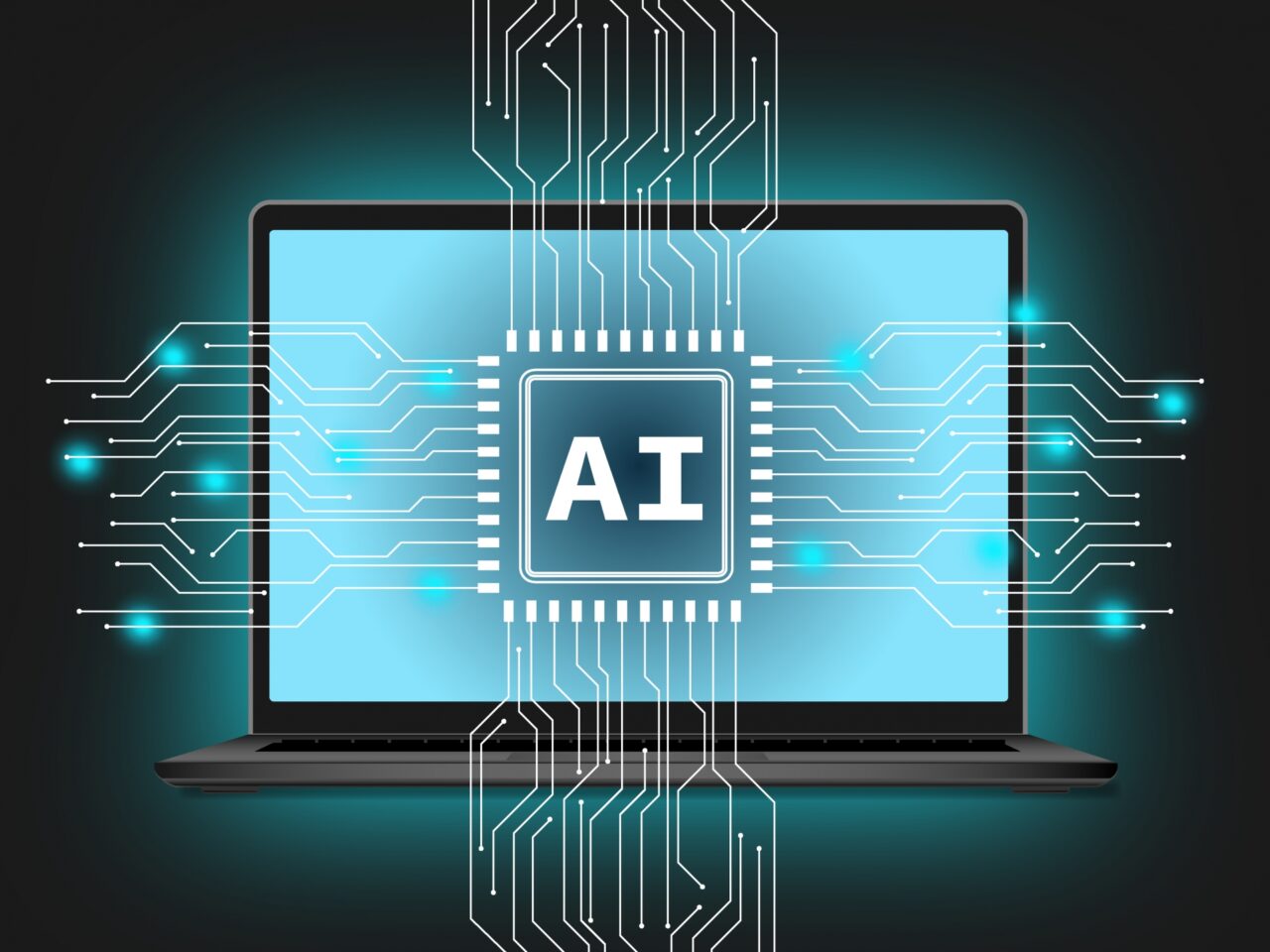AIは様々な業界で活用方法が見出されており、不動産業界にもその波は広がっています。しかし、自社への導入を検討しつつ、以下のような悩みから導入に迷う方も少なくありません。
「不動産業界でのAI活用事例が知りたい」
「具体的なメリット・デメリットがわからない」
そこで今回は、不動産業界におけるAI活用事例を解説します。
【記事を読んで得られること】
- 不動産業界でのAI活用事例
- AI導入のメリット・デメリット
- 実際に導入している業者
実際に導入している企業も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
不動産会社がAIを活用する方法5つ
不動産会社がAIを活用する5つの方法を見ていきましょう。
- データ分析による提案物件の最適化
- データ分析による価格査定
- チャットボット導入による顧客対応の自動化
- 建物管理業務の効率化
- 定型的な文書作成業務等の効率化
- 空室率予測の自動化
- 写真や間取りからのニーズ解析
- 契約書のチェック業務の効率化
それぞれ詳しく見ていきましょう。
データ分析による提案物件の最適化
顧客の検索履歴や閲覧傾向、問い合わせ履歴といった行動データをAIが分析することで、興味・関心の高い物件を精度高くレコメンドできるようになります。
これにより、従来の営業担当の勘に頼った提案ではなく、データに基づいた最適な物件提案が実現可能です。営業現場での成約率向上や顧客満足度の改善にも大きく役立つでしょう。
データ分析による価格査定
過去の取引履歴、エリアごとの需要と供給、築年数や面積、周辺環境など多角的な情報をもとに、AIが物件価格を予測します。人間による主観的な評価を排除し、透明性のある査定を実現することが可能です。
精度の高い価格提示は顧客との信頼関係構築にもつながり、スムーズな商談進行に役立つでしょう。
チャットボット導入による顧客対応の自動化
WebサイトやLINEなどにチャットボットを導入することで、24時間365日、顧客からの問い合わせに即時対応が可能になります。
空室情報や内見予約、初期費用の確認など、定型的な問い合わせにはAIが自動応答。対応スピードが上がることで機会損失の防止や顧客満足度の向上にもつながります。
建物管理業務の効率化
AIは建物の劣化状況や修繕履歴、設備の稼働データなどを分析し、最適なタイミングでのメンテナンスや設備更新を提案します。
これにより、管理業務における人手やコストの削減、トラブルの予防といった効果が得られます。マンションやオフィスビルなど複数物件を管理する企業において、AIの導入は大きな効率化に役立つでしょう。
定型的な文書作成業務等の効率化
契約書や重要事項説明書といった定型文書の作成にAI-OCRや生成AIを活用することで、手作業による入力作業やミスを削減できます。
特に同一フォーマットの書類が多い不動産業務では、AIを組み込んだ業務フローの構築により、事務作業の大幅な省力化が実現可能です。
空室率予測の自動化
AIは過去の入退去データや周辺エリアの需要動向、季節要因などをもとに、将来の空室率を高精度で予測することができます。
この予測結果をもとに、賃料の最適化や広告出稿タイミングの見直しが可能になり、空室期間の短縮と収益最大化を実現できます。
写真や間取りからのニーズ解析
物件の写真や間取り図をAIが解析することで、どのようなユーザーに刺さるかを自動で判別できます。
たとえば、「明るさ」「収納の多さ」「リビングの広さ」といった特徴を抽出し、ニーズとマッチングさせることで、より精度の高いレコメンドが可能になります。
契約書のチェック業務の効率化
不動産取引における契約書類は膨大で、確認作業にも時間がかかります。
AIは自然言語処理を活用し、契約書の条項チェックや不備の検出、重要語句の強調などを自動で行うことができるため、ヒューマンエラーの防止と業務の効率化が実現できます。
不動産会社がAI活用を始めるためのステップ4つ
次は、不動産会社がAIを導入するための4つのステップを解説します。
- 活用業務の選定
- 活用範囲と業務プロセスの設計
- 試験開発・運用
- 本開発・運用
それぞれ詳しく見ていきましょう。
STEP1:活用業務の選定
まずは、自社の業務フローを洗い出し、AIの活用によって効率化・高度化が見込める領域を特定します。業務量が多く、かつ反復性が高い分野(例:チャット対応、査定業務など)は導入の優先度が高いといえるでしょう。
初期の段階では、スモールスタートで成果が可視化しやすい業務から始めるのが効果的です。
STEP2:活用範囲と業務プロセスの設計
AIを活用する業務が決まったら、具体的にどのようなプロセスでAIを導入するかを設計します。既存の業務フローとの整合性を保ちつつ、AIが自然に組み込まれるようにする必要があります。
また、導入後のオペレーションも見据えて、現場担当者の負担が最小限となるよう調整することが重要です。
STEP3:試験開発・運用
本格的な開発に入る前に、PoC(概念実証)を通じて小規模にAIをテスト運用します。
PoCによってAIの有効性や精度、業務への適合度などを確認し、問題点があれば早期に対処できるのが利点です。関係者全体で期待値を揃えることも、このフェーズで行うべき重要なポイントといえるでしょう。
STEP4:本開発・運用
PoCを経て導入の方向性が定まったら、本格的にAIの開発・導入フェーズに入ります。外部ベンダーと連携しながら、要件に応じたAIシステムを構築します。
導入後は、運用体制の整備と継続的なデータ学習・改善が求められます。導入して終わりではなく、日々の業務の中でブラッシュアップを続けていくことが成功の秘訣です。
AIを導入している不動産会社10選
ここからは、AIを導入している不動産会社を10社解説します。
- 三井不動産
- 住友不動産販売
- 東急リバブル
- 大東建託
- 野村不動産ソリューションズ
- レオパレス21
- ハウスドゥ(HouseDo)
- リブセンス(IESHILなど)
- LIFULL(LIFULL HOME’S)
- スタイルポート(3D内覧サービス開発)
それぞれ詳しく見ていきましょう。
三井不動産

三井不動産は、グループ全体でデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進しており、AIの活用も積極的に進めています。
たとえば、オフィスや商業施設の開発・運営において、AIによる人流解析や空室リスクの予測を導入。都市の価値やテナント誘致戦略の最適化に役立てています。
さらに、不動産投資や運用の判断材料としてもAIを活用しており、ビッグデータと連携させることで、より精緻なエリア分析や収益予測が可能となっています。
住友不動産販売

参照:stepon
住友不動産販売では、AIを活用した不動産価格査定サービスを導入し、過去の売買データや市場動向から高精度な価格提示を実現しています。
顧客は売却の意思決定を迅速かつ納得感を持って行うことが可能です。また、営業支援ツールとしてもAIを取り入れており、顧客属性やエリア特性に基づいた最適な提案を自動化。営業担当者の負担を軽減し、提案の質を均一化することで、成約率向上にもつながっています。
東急リバブル

参照:livable
東急リバブルでは、顧客対応の自動化と価格査定の精度向上を目的に、AIチャットボットや査定アルゴリズムを積極的に導入しています。
オンラインでの査定依頼や相談に対して、24時間対応が可能になり、顧客満足度を高めると同時に、業務の効率化を実現しています。さらに、蓄積された応対データをAIが学習し続けることで、提案の精度やスピードが日々向上しており、非対面営業の強化に大きく寄与しています。
大東建託

参照:kentaku
大東建託は、全国で展開する賃貸住宅事業においてAIを幅広く活用しています。入居希望者の属性やエリア情報をもとにAIが需要予測を行い、物件開発や募集計画の最適化に反映。
これにより空室リスクを抑えた安定経営を支援しています。また、入居者対応や契約管理においてもAIチャットボットを導入しており、業務の自動化・省力化が進んでいます。今後は建物の保守・管理領域でもAI活用が拡大していく可能性もあるでしょう。
野村不動産ソリューションズ

参照:nomura
野村不動産ソリューションズは、売却査定や営業支援の高度化を目的にAI技術を取り入れています。
たとえば、顧客の閲覧履歴や問い合わせ履歴などの行動データを分析し、AIが自動で最適な物件提案を行う仕組みを構築。営業担当者の提案活動をサポートし、顧客ごとの個別最適なアプローチが可能となっています。また、今後は業務フロー全体へのAI統合を見据えたデジタル戦略も加速していくかもしれません。
レオパレス21
参照:leopalace21
レオパレス21では、AIチャットボットを導入して入居者からの問い合わせ対応を24時間体制で実施することで、コールセンター業務の負担軽減と対応品質の平準化を図っています。
加えて、過去の問い合わせデータをAIが分析してトラブルの傾向や入居者のニーズを可視化し、物件改善やサービス開発に活かしています。入退去に関する手続きの自動化や、設備点検の最適スケジューリングにもAIを活用しているため、活用用途は幅広い印象です。
ハウスドゥ(HouseDo)

参照:housedo
ハウスドゥは、不動産売却支援サービスの中核にAIを据え、ビッグデータを活用した自動査定システムを展開しています。全国の取引事例を基にAIが物件の市場価値を算出し、精度の高い価格提示を可能にしています。
また、営業担当者が持つノウハウをAIに学習させることで、提案の質とスピードを均一化。さらに、顧客管理や追客の自動化にも取り組んでおり、業務全体の効率化と成約率の向上を達成しました。
リブセンス(IESHILなど)

参照:livesense
リブセンスが運営するIESHIL(イエシル)は、AIを用いた不動産価格推定エンジンを提供しています。物件ごとにリアルタイムの価格情報や将来の価格推移を提示することで、ユーザーの意思決定をサポートしています。
価格算出には、膨大な取引データやエリア特性、建物の状態などを総合的に評価。ユーザーは仲介業者を通さずに、透明性のある情報を基に物件探しを進めることができ、情報格差の解消にも役立っているようです。
LIFULL(LIFULL HOME’S)

参照:lifull
LIFULLでは、ユーザーの検索行動データをAIで解析し、物件のレコメンド精度を高める技術を導入しています。
たとえば、ユーザーがよく閲覧する条件やエリアを学習し、希望にマッチした物件を自動で表示。ユーザー体験の向上と問い合わせ数の増加につながっています。また、問い合わせ対応の一部をAIが代行することで、営業担当者の負担を軽減。その他、AIを活用した需要予測や賃料相場分析にも取り組んでいます。
スタイルポート(3D内覧サービス開発)

参照:styleport
スタイルポートは、3D内覧ツール「ROOV(ルーブ)」を開発・提供しており、AIを活用してユーザーに最適な物件提案や視点切り替えナビゲーションを行っています。これにより、現地に足を運ばなくても実際の空間感覚を体験できる革新的なサービスを実現。
営業担当者の説明負担を軽減するとともに、契約率向上にも貢献しています。また、ユーザーの閲覧履歴や関心エリアをもとに、より関心の高い物件を推薦する機能も搭載しています。
不動産会社がAI活用を成功させるためのポイント5つ
次は、不動産会社がAI活用を成功させるためのポイントを見ていきましょう。
- 中長期で戦略を練る
- 投資対効果の高い活用方法を選定する
- アジャイルアプローチで開発・導入する
- リスク管理を徹底する
- 社員のAI活用リテラシー向上が必要になる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
中長期で戦略を練る
AIは短期的な成果よりも、データの蓄積や継続的な学習によって徐々に効果を発揮する技術です。そのため、「すぐに成果を出す」ことを前提にすると、途中で評価が難しくなる可能性があります。
導入の初期段階では定量評価しにくい場面もあるため、1〜2年単位の中長期視点でプロジェクトを設計することが重要です。
投資対効果の高い活用方法を選定する
すべての業務にAIを導入するのではなく、費用対効果の面で特にメリットの大きい領域に絞って導入することがポイントです。
たとえば「1件あたりの問い合わせ対応にかかるコストが高い」業務や「属人化している査定業務」など、課題の明確な業務から取り組むことで、早期に効果を実感しやすくなります。
アジャイルアプローチで開発・導入する
AI活用は、仮説検証を繰り返しながら改善していく「アジャイル型」の導入が効果的です。
はじめから完璧なものを求めるのではなく、小さく始めて、現場の声を取り入れながらスピーディーに調整していくことで、実用性の高いシステムに成長させることができます。
リスク管理を徹底する
AIによる判断ミスや情報の誤認識、ハルシネーション(事実ではない出力)など、導入にあたってのリスクも存在します。誤った情報で顧客に不利益が発生しないよう、必ず人による最終確認プロセスやログの取得体制を設けることが必要です。
業務によってはAIと人の役割分担を明確に設計することも重要になってくるでしょう。
社員のAI活用リテラシー向上が必要になる
AIを導入しても、活用する現場の社員がツールを理解していなければ真価を発揮できません。ツールの操作方法だけでなく、AIがどんな判断ロジックを持っているか、どんな限界があるのかといった理解も必要です。
定期的な研修やナレッジ共有を通じて、現場のスキルアップを図ることが成功への近道といえるでしょう。
不動産会社がAI活用するメリット
次は、不動産会社がAI活用するメリットを見ていきましょう。
- 業務効率化
- ライフワークバランスの改善
- 顧客満足度の改善
それぞれ詳しく見ていきましょう。
業務効率化
AIを活用することで、膨大な作業時間がかかっていた業務を短時間でこなせるようになります。たとえば、問い合わせ対応をチャットボットで自動化すれば、営業時間外でも即時対応が可能になり、スタッフの負担を軽減できるでしょう。
また、物件情報の入力・整理・更新といった事務作業も自動化の対象となり、全体の生産性が向上します。
ライフワークバランスの改善
AI導入により、これまで人手でこなしていた業務が軽減され、従業員の残業時間やストレスの低減につながります。
繁忙期の業務負荷をAIが一部吸収することで、ワークライフバランスの向上が期待できます。離職率の改善や人材の定着にも好影響を与える可能性があるため、積極的に導入を検討してみてください。
顧客満足度の改善
AIによってユーザーに対するレスポンスが迅速かつ的確になることで、顧客満足度が向上します。
たとえば、チャットボットやレコメンド機能を活用すれば、ユーザーのニーズに合わせた提案が自動で行えるため、「待たされる」「的外れな提案をされる」といった不満を軽減できるでしょう。
不動産会社がAI活用するデメリット
次は、不動産会社がAI活用するデメリットを見ていきましょう。
- AIではカバーしきれない業務がある
- ハルシネーションのリスクがある
- AIを扱える人材が必要になる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
AIではカバーしきれない業務がある
AIは過去のデータやパターンに基づいて判断するため、イレギュラーな案件や人間の感覚を要する判断には不向きです。たとえば、「お客様との信頼関係構築」や「空気を読んだ提案」などは、今のAIでは対応が困難です。
現場の経験や人の感情を伴う業務は人間が担うものとし、その他の領域をAIに任せるのがおすすめです。
ハルシネーションのリスクがある
AIは、事実とは異なる情報をもっともらしく提示することがあります。いわゆるハルシネーションと呼ばれる事象であり、不動産のように法的リスクが絡む業務では、この誤情報が大きなトラブルにつながる恐れがあるのです。
そのため、導入にあたっては、必ず生成結果を人の手でチェックするなど、一定の体制を設けるようにしてください。
AIを扱える人材が必要になる
AIを正しく活用するためには、ツールを操作するスキルだけでなく、AIの仕組みや特性を理解した人材が必要です。
外部に委託する場合も、社内に一定の知識を持った担当者がいないと、期待通りの活用が難しくなることがあります。リテラシー教育や採用戦略も重要な課題として、導入時に対策を練っておくと良いでしょう。
AI活用で不動産の業務を効率化させよう
本記事では、不動産会社がAI活用する事例やメリットなどを解説してきました。
AIは不動産業務に関しても有用性が高いツールですが、きちんとデメリットを把握しなければ十分な効果は見込めません。また、以下のステップも事前に押さえ、スムーズに導入していきましょう。
【不動産会社が生成AIを導入するステップ】
- 活用業務の選定
- 活用範囲と業務プロセスの設計
- 試験開発・運用
- 本開発・運用
AIは不動産事業におけるDXでも役に立つので、本記事を参考にぜひ検討してみてください。