AIによる需要予測は注目されているものの、以下のような悩みから導入に迷う方も少なくありません。
「AI需要予測って、実際どれくらい精度で活用できるのか」
「自社のデータ量で、AI需要予測は本当に使えるのか」
そこで今回は、AIを活用した需要予測の仕組みや導入メリットを解説します。
【記事を読んで得られること】
- AIによる需要予測の代表的な手法と特徴
- 活用によって得られる5つのメリット
- 導入前に押さえたい注意点や成功のポイント
小売・製造業を中心とした企業事例も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
AIを使用した需要予測とは

AIを使った需要予測は、今後の販売数やサービス利用数をデータに基づいて推定する分析手法です。
商品別の在庫調整や仕入れ計画の精度向上につながるため、業務効率化を図りたい企業に適しています。
過去は勘や経験に頼っていた予測も、AIが複雑なパターンを高速で処理することで客観的な意思決定が可能になるでしょう。
AIによる需要予測の代表的な手法7選

ここでは、AIによる需要予測の代表的な手法を7つ紹介します。
- 時系列分析
- 移動平均法
- 指数平滑法
- 回帰分析
- ロジスティック回帰やロジスティック曲線
- 機械学習モデル(ランダムフォレスト・サポートベクターマシンなど)
- ディープラーニング(ニューラルネットワーク)
それぞれ詳しく見ていきましょう。
時系列分析
時系列分析は、売上や利用データの時間的な変化をもとに将来を予測する方法です。
AIを活用することで、曜日・季節・トレンドといった複数の要因を同時に処理し、より精度の高い予測が可能になります。特に多店舗展開している小売業では、業績予測や在庫調整に役立つでしょう。
移動平均法
移動平均法は、一定期間の平均値を使って需要の推移をなだらかに捉える手法です。
短期的な変動に左右されにくく、中長期の傾向を把握するのに有効です。AIと組み合わせれば、仕入れや棚卸の作業を効率化でき、原価の把握や資産管理にもつながります。
指数平滑法
指数平滑法は、直近データを重視する予測手法です。変動の激しい需要にも対応しやすい点が特長といえるでしょう。
過去データを滑らかに調整しながら、最新の傾向を強く反映するため、日々の売上がばらつくケースで有効です。
AIと併用すれば、反応の速い販売予測が実現します。
回帰分析
回帰分析は、価格や季節、販促などの要因と売上との関係を数式で表す予測手法です。
単一の要因で分析する単回帰と、複数の要素を組み合わせる重回帰があります。どの要因が需要に影響しているかを定量的に把握できるため、販売戦略の立案にも役立つでしょう。
ロジスティック回帰やロジスティック曲線
ロジスティック回帰は、特定の成長曲線をもとに将来の需要を予測する方法です。非線形の関係性を表現できるため、成長が鈍化・安定化する商材の分析に向いています。
関数が複雑なため、扱いには数学的知識が必要ですが、高い予測精度が期待できるでしょう。
機械学習モデル(ランダムフォレスト・サポートベクターマシンなど)
機械学習は、大量のデータから需要に影響するパターンを自動で学習する手法です。
ランダムフォレストやSVMなどは、複雑な条件下でも高精度な予測を実現します。AIが自動でモデルを更新するため、環境変化やニーズの移り変わりにも対応しやすいのが特長といえるでしょう。
ディープラーニング(ニューラルネットワーク)
ディープラーニングは、多層構造のニューラルネットワークで複雑なパターンを学習する技術です。
RNN(再帰型ニューラルネットワーク)やLSTM(長短期記憶)を用いれば、気温や時間帯など複数要因を同時に処理して高精度な短期予測が可能になるでしょう。
電力需要や交通量予測など、高度な分析が求められる場面で効果を発揮します。
AIで需要予測する5つのメリット

ここでは、AIで需要予測するメリットを5つ紹介します。
- 在庫量を適正にコントロールできる
- 売れ筋や需要の波を先読みできる
- 生産や仕入れの計画が立てやすくなる
- 経験に頼らず安定した意思決定ができる
- データ分析で経営判断を後押しできる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
在庫量を適正にコントロールできる
AIによる需要予測は、将来の販売数をもとに在庫を自動で最適化できます。
欠品による販売損失を防ぎつつ、過剰在庫によるロスやスペース圧迫も軽減。食品など賞味期限がある商材でも、廃棄削減により利益率の改善が期待できるでしょう。
市場変動への対応力も高まり、在庫管理コストの抑制にもつながります。
売れ筋や需要の波を先読みできる
AIは、過去データや気象・SNSトレンドなど多様な要素を分析し、売れ筋や需要の変化を先読みします。
非線形なパターンも自動で抽出できるため、複雑な消費傾向にも対応可能です。小売業では、曜日や季節の影響をふまえた予測により、より具体的で実行しやすい販売戦略を立てられるでしょう。
需要の波を見極め、競合より早く施策を打つ体制を整えられます。
生産や仕入れの計画が立てやすくなる
AIによる予測結果を活用すれば、生産・仕入れ計画の精度が向上し、過不足のリスクを減らせます。
原材料や製品量の調整も容易になり、無駄な在庫や欠品を防げるでしょう。人員配置や設備の調整にも活用できるため、サプライチェーン全体の効率化に直結します。
在庫調整が重要な業界では特に有効です。
経験に頼らず安定した意思決定ができる
AIを使えば、ベテランの経験や勘に依存せず、誰でも一貫性のある予測が可能になります。
膨大なデータをもとに客観的な判断ができるため、ばらつきのない安定した意思決定を支えます。担当者の異動や退職によるノウハウの断絶も回避でき、業務品質の維持にもつながるでしょう。
データ分析で経営判断を後押しできる
AIの予測結果は、根拠となるデータとセットで提示されるため、経営判断の信頼性を高めます。プロモーションの効果測定や価格調整の根拠としても活用可能です。
変化の兆しを早期にとらえることで、スピーディーな意思決定を実現し、競合との差別化にもつながるでしょう。
AIで需要予測する3つの注意点

ここでは、AIで需要予測する注意点を3つ紹介します。
- 精度の高い予測には十分な量のデータが必要になる
- 想定外の事態や例外的な変動には対応が難しい場合がある
- 出力された結果を人が検証し運用管理する手間がかかる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
精度の高い予測には十分な量のデータが必要になる
AIの予測精度を高めるには、質の高い大量データの蓄積が前提です。
学習に使う「教師データ」が少なかったり偏っていたりすると、AIは正しい傾向をつかめません。導入初期はデータが不十分になりがちで、誤った予測につながる恐れがあります。
100件以上のデータ収集と、整備された保存環境が求められるため、事前準備に一定の工数がかかります。
想定外の事態や例外的な変動には対応が難しい場合がある
AIは過去データを学習して予測する仕組みのため、前例のない変化には対応しきれない場合があります。
自然災害やパンデミックなど突発的な要因により、AIが判断を誤るケースも想定されるでしょう。短期的な変動を長期トレンドと誤認する恐れもあるため、最終判断は人が行う必要があります。
異常値や外的要因は人の目で補完する意識が欠かせません。
出力された結果を人が検証し運用管理する手間がかかる
AIの予測はあくまで数理モデルに基づく出力であり、実際のビジネス判断にそのまま使えるとは限りません。
出力内容が適切かどうか、定期的に人が検証・監視する作業が必要です。予測精度のばらつきやデータの偏りを見逃さず、必要に応じてモデルの調整や改善する体制が求められるでしょう。
継続的な運用には、専門知識をもつ担当者の配置も重要です。
AIで需要予測の精度を高める3つのポイント

ここでは、AIで需要予測の精度を高めるポイントを3つ紹介します。
- 予測の目的やゴールを明確にしたうえで適切な手法を選ぶ
- ノイズの少ない正確なデータを十分に集めて丁寧に整える
- 定期的な検証と修正を重ねてモデルの精度を維持する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
予測の目的やゴールを明確にしたうえで適切な手法を選ぶ
AI予測の精度を高めるには、予測の目的とゴールを明確にし、目的に合った手法を選びましょう。
短期的な在庫調整と中長期の需要分析では、使うモデルが異なります。事業内容や予測対象に合わせて、時系列分析・回帰分析・機械学習などの手法から適切なものを選定しましょう。
目的が不明確なまま導入すると、精度が上がらず分析効果も薄れるおそれがあります。
ノイズの少ない正確なデータを十分に集めて丁寧に整える
AIの予測精度は、データの量と質に大きく左右されます。
100件以上の正確なデータを収集・整備することが前提であり、不足や偏りがあると誤った予測につながります。リアルタイム性のある情報に加え、SNSトレンドや気象データなどの外部情報も取り入れると、より現実に即した予測が可能になるでしょう。
古くて信頼性の低いデータでは、精度の向上は見込めません。
定期的な検証と修正を重ねてモデルの精度を維持する
AIは導入後も継続的な検証とチューニングが必要です。
想定外の出来事が起きた際、過去データをもとにしたモデルでは対応が難しくなるため、運用後も定期的に実績と予測値の差異を確認し、改善を繰り返す必要があります。予測誤差の原因を分析し、モデルに反映させれば、精度を維持・向上できるでしょう。
PDCAをまわす仕組みと、人による最終判断の体制づくりが欠かせません。
AIによる需要予測を活用している企業事例13選
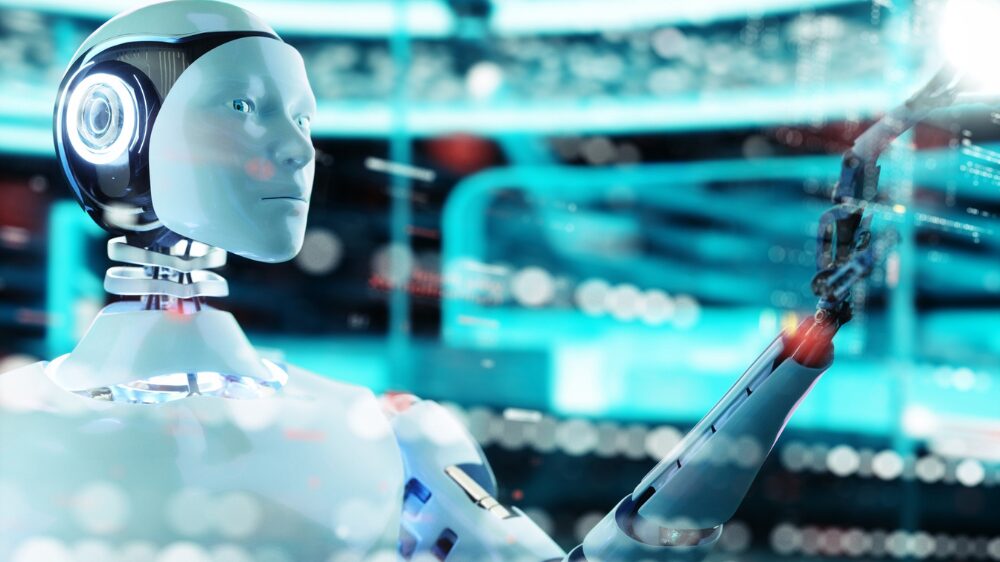
最後に、AIによる需要予測を活用している企業事例を13社紹介します。
- ファミリーマート:AI発注システム「AIレコメンド発注」の導入
- イトーヨーカドー:AI商品発注システムで発注作業を3割短縮
- ライフコーポレーション:需要予測AIで発注業務を半減
- マルイ(岡山):AI需要予測で客数・販売精度向上、発注時間50%削減
- 中部薬品(Vドラッグ):需要予測型自動発注で在庫最適化と作業600時間削減
- リンガーハット:緊急事態にも対応するAI需要予測システム
- 丸亀製麺(トリドールHD):AI需要予測で来客数を予測し業務効率化
- キッコーマン:2000種の商品需要をAI予測し業務効率化
- 森永乳業:新製品の需要予測にAIを活用
- サッポロビール:AI需要予測システムで生産出荷を高度化
- キリンビバレッジ:自販機運用にAIを導入し業務1割削減へ
- ヤマト運輸:AIで荷物取扱量を予測し物流効率化
- ヤマエ久野(食品卸):AI自動発注で発注業務を約50%短縮
それぞれ詳しく見ていきましょう。
ファミリーマート:AI発注システム「AIレコメンド発注」の導入
ファミリーマートは、販売実績や天候、曜日ごとの傾向などをAIが分析する発注システムを導入。従業員が勘に頼らず、数値に基づいて発注判断できるようになりました。
業務の属人化を防ぎ、欠品の回避や適正な在庫数の維持にもつながっています。
発注業務を効率化し、接客や売場づくりへの注力時間を増やす取り組みが進んでいます。
イトーヨーカドー:AI商品発注システムで発注作業を3割短縮
全国132店舗で導入されたAI商品発注システムは、気温・降水確率・客数などを分析し、最適な発注数を算出します。
テスト運用では発注作業が約3割短縮され、在庫切れの減少にも効果を発揮しました。
浮いた時間は、接客や売場改善などの業務に活用され、現場力の強化と効率化の両立を実現しています。
ライフコーポレーション:需要予測AIで発注業務を半減
ライフコーポレーションは、日本ユニシスと共同開発した「AI-Order Foresight」を全店舗に導入。販売実績や気象情報をもとにAIが日々の発注数を自動算出し、作業時間を5割以上削減しました。
牛乳など日配品も高精度で予測でき、属人化の解消と業務品質の平準化が実現。
削減された時間は、接客や売場の改善に充てられています。
マルイ(岡山):AI需要予測で客数・販売精度向上、発注時間50%削減
岡山のスーパーマーケット・マルイは、日本IBMのAI予測モデルを活用し、天候や催事などの要因をもとに商品別に最適な予測を実施。
客数の予測精度は90%を超え、販売機会損失や廃棄ロスも大幅に減少しました。
発注作業は半分に短縮され、空いた時間はサービス強化に転換。今後は精肉・惣菜・ベーカリー分野への応用も予定されています。
中部薬品(Vドラッグ):需要予測型自動発注で在庫最適化と作業600時間削減
中部薬品は、日立システムズの需要予測型AI発注システムを全400店舗に導入。特売や季節要因を含む30種の変動要因を分析し、精度の高い自動発注を実現しました。
導入後、日配品の発注精度が大幅に向上し、1週間あたり600時間の作業時間削減も達成。
在庫の過不足が抑えられ、商品回転率の改善にもつながっています。
リンガーハット:緊急事態にも対応するAI需要予測システム
リンガーハットは、パロアルトインサイトと連携し、自然災害や感染症など緊急時の需要変化にも対応するAI予測システムを開発。気象データだけでなく、災害・社会変動にも対応する柔軟な予測が可能になりました。
在庫管理や仕込み調整の最適化により、食品ロスと人件費の削減を目指しています。
飲食業界の課題解決にもつながる取り組みです。
丸亀製麺(トリドールHD):AI需要予測で来客数を予測し業務効率化
トリドールHDは、全国の丸亀製麺に富士通のAI需要予測を導入。POSデータや天候をもとに、時間帯別の来客数や販売数を高精度に予測します。
AIモデルを自動で最適化する「動的アンサンブル技術」により、発注や仕込みの効率化、空調の最適運転を実現しました。
食品ロス削減・人員配置の最適化・省エネの3軸で、業務全体の無駄を抑えています。
キッコーマン:2000種の商品需要をAI予測し業務効率化
キッコーマンは、日立ソリューションズ東日本の「Forecast Pro」を導入し、約2000アイテムの需要をAIで予測。統計知識がなくても最適な分析が可能なシステムを活用し、需給担当者の負担を軽減しました。
瞬時の予測はAIに任せ、人は判断の難しい製品に注力できる体制へ移行。業務効率と精度の両立が進んでいます。
森永乳業:新製品の需要予測にAIを活用
森永乳業は、NECのAIソリューションを活用し、新製品の需要予測に取り組んでいます。
過去の販売実績やマーケティング施策、担当者の知見を組み合わせて予測を実施。実証実験では人と同等の精度が確認され、属人化を防ぎつつ早期判断が可能になりました。
発売前から精度の高い計画を立てることで、欠品や在庫過多のリスクを抑えています。
サッポロビール:AI需要予測システムで生産出荷を高度化
サッポロビールは、日鉄ソリューションズのAI予測を導入し、ビールやRTDの需給ギャップ解消に活用しています。
従来は担当者の経験に依存していた予測を、AIにより数値化・標準化することで、判断の再現性と業務効率を向上。
短期間で予測精度を高めるため、DataRobotを活用し、変化するニーズにも迅速に対応できる体制を構築しました。
キリンビバレッジ:自販機運用にAIを導入し業務1割削減へ
キリンビバレッジは、ソフトバンクのAIサービス「Vendy」を導入し、自販機の補充・巡回業務を効率化しています。
リアルタイムの売上・在庫データをもとにAIが補充ルートや商品配置を提案し、ベテラン頼みの業務から脱却。
導入から2ヶ月で、業務時間の1割削減と売上5%増の効果が見込まれており、全国8万台への展開を進めています。
ヤマト運輸:AIで荷物取扱量を予測し物流効率化
ヤマト運輸は、アルフレッサと連携し、AIによる荷物取扱量予測と配車最適化システムを構築しました。
販売や物流データ、道路状況などをもとにAIが業務量を予測し、効率的な配車計画を自動作成します。
システム構築により生産性が20%向上し、CO2排出量・走行距離を25%削減。医療機関との対面作業時間も短縮され、現場負担の軽減が進んでいます。
ヤマエ久野(食品卸):AI自動発注で発注業務を約50%短縮
ヤマエ久野は、日立と連携し、食品卸業にAI発注システムを導入。消費期限の短い商品も含め、販売傾向や気象条件など多様な要因を分析し、精度の高い発注数を自動算出します。
導入後は、発注作業を約50%削減でき、スタッフは提案営業など付加価値業務に時間を振り向けられるようになりました。
スポット需要対応機能や在庫調整機能も備え、属人化しない運用が可能です。
AIにおける需要予測を理解して自社ビジネスを効率化しよう

本記事では、AIを活用した需要予測の仕組みや手法、導入メリットや注意点などを解説しました。
AIは業務効率化や在庫管理の最適化に役立ちますが、十分なデータ整備や適切な運用体制がなければ、効果を発揮しにくい場合もあります。導入後に成果を出すためには、事前の準備と継続的な見直しが欠かせません。
【AI需要予測を成功させるためのポイント】
- 目的に合った手法を選定する
- 正確で十分なデータを整える
- 定期的な検証とモデルの見直しをする
AIを活用した需要予測の企業事例も参考に、自社でのAI導入を前向きに検討し、ビジネスを効率化しましょう。












