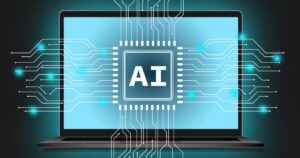自治体でもAIを導入していると聞いても、本当に効果があって民間でも参考になるのか、と疑問を抱く方も少なくありません。
「自治体でもAI導入しているって本当なのか」
「実際に自治体でAIを活用して何がどう変わったのか知りたい」
そこで今回は、自治体における生成AIの導入状況や活用事例をわかりやすく解説します。
【記事を読んで得られること】
- 自治体がAIを導入している具体的な事例と背景
- 業務効率化・コスト削減など3つの導入メリット
- 導入前にやっておくべき準備
自治体のAI導入状況を参考に、自社にAI導入を検討している方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
自治体における生成AIの導入状況

生成AIの導入は、行政サービスの質を維持しながら人手不足に対応する手段として注目されているのはご存じでしょうか。
文書作成や問い合わせ対応といった定型業務で活用が広がっており、人的負担の軽減や処理スピードの向上につながっています。ただし、情報漏えいリスクや初期コストの負担、AIを扱える職員の育成といった課題も避けて通れません。
課題に対応するには、セキュリティ強化や段階的な導入、ガイドラインの整備が不可欠です。生成AIの活用は、限られたリソースでも持続可能な行政運営を実現するための具体策として期待されています。
自治体で生成AI導入が進む背景

ここでは、自治体で生成AI導入が進む背景を5つ紹介します。
- 職員の人手不足により業務効率化が急務になっている
- 行政サービスの質を維持する手段として生成AIが注目されている
- 生成AIの進化により実務への活用が現実的になってきている
- 国の支援制度やガイドラインが導入の後押しとなっている
- スマート自治体への移行が行政改革の流れとして進んでいる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
職員の人手不足により業務効率化が急務になっている
自治体では、少子高齢化や若手人材の確保難により、職員数の減少が深刻化しています。2040年には職員数が現在の約半分に減ると予測され、従来通りの業務体制を維持するのは難しいでしょう。
限られた人員でも行政サービスの質を維持するため、生成AIによる業務効率化や自動化への期待が高まっています。定型作業の負担軽減に加えて、職員の残業削減や労働環境の改善にもつながることから、生成AI活用の選択肢は欠かせません。
行政サービスの質を維持する手段として生成AIが注目されている
人口減少や高齢化が進む中でも、住民は迅速かつ丁寧な行政サービスを当然のように求めているのが現状です。こうしたニーズに応える手段として、生成AIが持つ24時間対応やデータ処理能力への注目が高まっています。
住民問い合わせの自動応答やデータ分析による政策立案支援など、AIの導入によって利便性と業務効率を両立できる環境が整いつつあります。職員は創造的な業務に集中でき、全体のサービス品質も向上するでしょう。
生成AIの進化により実務への活用が現実的になってきている
ChatGPTの登場以降、自然言語処理やコンテンツ生成の精度が大幅に向上し、自治体業務でも活用可能なレベルに達しているのはご存じでしょうか。
従来のAIは分類や予測に特化していましたが、生成AIは文章作成や応答生成など幅広い用途に対応しています。問い合わせ文の自動作成や複雑な行政文書の下書きなど、実務での具体的な利用シーンも拡大しています。
民間企業の導入実績も、自治体の活用推進に影響を与えていると言えるでしょう。
国の支援制度やガイドラインが導入の後押しとなっている
総務省は「自治体戦略2040構想研究会」において、生成AIなどの先端技術を活用した行政改革を推進すべきと提言しています。
また、「自治体におけるAI活用・導入ガイドブック」では、導入手順や留意点が明確に示されており、現場職員の不安軽減にも一役買っているのです。
国による制度的な後押しと具体的な支援策の整備は、自治体が安心してAI活用に踏み出せる環境づくりに欠かせません。
参考:自治体戦略2040構想研究会_自治体戦略2040構想研究会|総務省
参考:自治体におけるAI活用・導入ガイドブック|総務省
スマート自治体への移行が行政改革の流れとして進んでいる
新型コロナウイルスをきっかけに、自治体でも行政DXの必要性が強く認識されるようになりました。紙ベースや属人的な業務体制からの脱却が求められる中、生成AIはスマート自治体への転換を支える中核技術として位置づけられています。
問い合わせ対応や文書作成の自動化により、業務の質を高めながら住民サービスの持続性も確保できるでしょう。行政改革の一環として、AI導入はもはや避けて通れない流れです。
自治体における生成AIの導入事例14選

ここでは、自治体における生成AIの導入事例を14つ紹介します。
- 総合案内サービス(愛知県内39市町村)
- 申請受付・審査支援システム(戸田市・川口市)
- 市民の健康管理の手助け(兵庫県神戸市)
- 児童虐待対応支援システム(三重県)
- 保育入所選考の自動化(埼玉県さいたま市)
- 介護予防(福島県いわき市)
- ケアプラン作成(愛知県豊橋市)
- 未納者への催告業務(神奈川県川崎市)
- 職員業務実態の分析・可視化(兵庫県宝塚市)
- リアルタイム議事録(青森県)
- 音声テキスト化サービス(埼玉県内19市町)
- 職員からのICT関連の問合せに関するナレッジ管理(長崎県)
- AI-OCRによる行政文書の読取・データ化(茨城県つくば市)
- 漏水箇所検知(愛知県豊田市)
それぞれ詳しく見ていきましょう。
総合案内サービス(愛知県内39市町村)
愛知県内39市町村は、住民からの生活関連の問い合わせ対応を効率化するためにAI総合案内サービスを導入しました。
このサービスでは、引っ越し・出産などに関する質問へ、24時間365日対応のチャット形式でAIが回答します。職員は単純業務から解放され、複雑な対応に集中できるようになりました。
導入当初はQAデータ作成に手間がかかったものの、39市町村での共同利用により、費用を抑えながら応対品質の平準化が実現しています。
申請受付・審査支援システム(戸田市・川口市)
戸田市と川口市は、申請から審査・支払いまでをスマートフォン上で完結できるAI連携システムを導入しました。
市民は来庁せずに手続きができ、大幅な時間短縮と利便性向上を実現。職員側はAIとRPAの併用で、年間最大2万時間の業務削減効果が見込まれています。
導入にあたっては、個人情報管理や条例対応、同意取得などの制度整備も重要なポイントとなりました。
市民の健康管理の手助け(兵庫県神戸市)
神戸市は、市民の行動変容を促す目的で健康管理アプリ「MY CONDITION KOBE」を提供しています。
アプリでは、生活データや健診結果をAIが分析し、個別の健康アドバイスを自動生成。市民は自分の状態を可視化できるようになり、5,000人以上が利用を開始しています。
個人情報の適正利用については、審議会を通じてPHRデータの活用目的を明確化し、法的整理をしました。今後は、予防医療分野でのAI活用拡大が期待されています。
児童虐待対応支援システム(三重県)
三重県は、児童虐待への対応力向上と人材育成を目的にAI支援システムを導入しました。
AIは過去事例を学習し、リスク予測や類似ケースの提示により職員の判断を支援。経験の浅い職員がシミュレーションを通じて実践的に学べる仕組みが評価されています。
機密性の高い情報を扱うため、閉域ネットワークや専用端末での厳重なセキュリティ体制も構築。今後は他自治体との連携により、精度向上と導入コストの低減を目指しています。
保育入所選考の自動化(埼玉県さいたま市)
さいたま市では、煩雑な保育所入所選考業務をAIで自動化し、大幅な効率化を実現しました。
AIは児童情報や空き定員に基づき、最適な割り当てを短時間で判断。これにより、従来1,500時間かかっていた作業が数十分で完了するようになりました。
この機能は、既存の保育業務システムに統合されており、通知の早期化など保護者対応にも効果を発揮しています。
介護予防(福島県いわき市)
福島県いわき市は、将来的に介護が必要になる高リスク者を早期に把握する目的で、AI抽出システムを導入しました。
住民基本台帳や介護認定履歴、健診の受診状況など複数の部門にまたがる情報をAIが統合的に学習し、従来は職員の勘に頼っていた抽出作業の精度が向上。約9.7万人分の高齢者データを扱うため、個人情報保護審議会の承認を経て運用を開始しています。
訪問が難しい地域でも効率的な対応が可能となり、職員の負担軽減にもつながっています。
ケアプラン作成(愛知県豊橋市)
愛知県豊橋市は、要介護者に適した介護計画を効率的に提案するため、AIによるケアプラン作成支援を導入しました。
このAIは、過去の有効事例をもとに最適なプランを提示し、ケアマネジャーの判断を補助します。提案の幅が広がることで新たな気づきが生まれ、業務効率化にも貢献しています。
過去データの取り扱いについては、匿名化や委託先との管理契約を徹底し、個人情報保護にも配慮されています。
未納者への催告業務(神奈川県川崎市)
神奈川県川崎市は、国民健康保険料の滞納者に対する電話催告業務をAIで最適化し、接触率の向上を図っています。
AIは、過去の折衝記録から曜日や時間帯ごとの接触傾向を分析し、職員が効果的なタイミングで架電できるよう支援します。出力には根拠が示されるため、現場でも納得して活用されており、接触率は約5.45%改善。
データ保護のため、AIシステムは大手ベンダー内で管理され、専用回線やデータ消去ソフトを活用したセキュリティ対策が施されています。
職員業務実態の分析・可視化(兵庫県宝塚市)
兵庫県宝塚市では、職員の働き方を見直すため、AIを活用して業務内容の可視化と分析を実施しました。
パソコン操作ログをAIが解析し、繰り返し業務の比率や利用頻度の高いアプリを数値で把握。RPA導入の優先順位付けや業務再設計の根拠として庁内で共有されています。
対象職員には事前説明をして、データ利用目的の明示や機密保持契約によって情報管理にも細心の注意が払われました。
リアルタイム議事録(青森県)
青森県は、職員の会議録作成の負担を軽減するため、AIを活用したリアルタイム議事録システムを本格導入しました。
会議中の音声を即時でテキスト化し、文字起こし作業時間は実証段階で4割削減。音声認識の精度とリアルタイム性が評価され、庁外会場でも利用可能な仕様となっています。
セキュリティ対策として、個人情報が記録に残らないよう、定期的なデータ完全消去も実施。今後は、教育現場や多言語対応など住民サービスへの展開も検討されています。
音声テキスト化サービス(埼玉県内19市町)
埼玉県と19市町は、会議録作成の効率化を目的に、音声テキスト化サービスの共同利用を開始しました。
AIが会話内容を自動で文字起こしすることで、議事録作成時間を約50%削減した自治体もあり、誤記や記録漏れも防止されています。
単独導入に比べてコストと事務負担を抑えられる点も共同利用の利点です。セキュリティ面では、LGWAN環境下での運用に限定し、音声・テキストデータは一定期間後に自動削除される仕組みが整えられています。
職員からのICT関連の問合せに関するナレッジ管理(長崎県)
長崎県は、年間1万件以上にのぼる職員からのICT関連の問い合わせ対応を効率化するため、AIナレッジ管理システムを導入しました。
AIは自然言語解析により問い合わせ内容を理解し、蓄積された情報から関連度の高い回答を自動で提示。担当者数の削減と対応の標準化を実現し、業務効率が向上しています。
他自治体でも導入しやすい汎用型ですが、ナレッジ様式の違いや個人情報管理の体制整備が今後の課題とされています。
AI-OCRによる行政文書の読取・データ化(茨城県つくば市)
茨城県つくば市は、紙の行政文書を効率的にデジタル化するため、AI-OCRを導入しました。
手書きや活字を高精度で読み取り、帳票単位で正読率93.41%を記録し、読めない文字は抽出して人が補完可能です。LGWAN-ASPの活用によりオンプレ構築と比べて費用を抑え、セキュリティも確保されています。
現在は保育や税務を含む24課で活用が進み、業務全体のデジタル化を強力に後押ししています。
漏水箇所検知(愛知県豊田市)
愛知県豊田市では、水道管の漏水調査にAIを導入し、調査効率と精度を大幅に向上させました。
衛星からの電磁波反射をAIが解析し、直径200mの漏水可能性区域を予測。5年分の調査委託費を削減し、全管路の60%を約7ヶ月で調査完了しています。
AIの予測は判断補助ツールとして位置づけられており、導入自治体側でも先入観を排除しつつ、活用方針の共有が進められています。衛星画像の調達が可能であれば他自治体でも利用でき、共同導入による費用圧縮も期待できます。
自治体に生成AIを導入する3つのメリット

ここでは自治体に生成AIを導入するメリットを3つ紹介します。
- 人件費や業務コストの削減につながる
- 繁忙期や問い合わせ集中時にも安定した対応が可能になる
- 住民サービスの質を高め満足度向上に貢献する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
人件費や業務コストの削減につながる
生成AIの導入は、職員数に依存しない業務運営を実現し、人件費や委託費の削減に効果を発揮します。
具体的には、AIによる電話対応や議事録作成の自動化により、臨時職員の雇用や外部委託の必要性が減少。AIは継続的にノウハウを蓄積できるため、人材の離職による知識の損失も回避可能です。
職員は単純作業から解放され、より高度な業務に時間を充てられるようになるでしょう。
繁忙期や問い合わせ集中時にも安定した対応が可能になる
生成AIは、業務が集中しやすい時期でも安定した対応を提供でき、臨時対応にかかる人件費を抑えられます。
ワクチン接種予約の開始時のように、短期間に問い合わせが殺到する状況でも、AIは時間帯や件数に関係なく柔軟に対応。チャットボットや音声応答システムを使えば、深夜や休日も含めて24時間の問い合わせ対応が可能となり、職員の負担軽減にもつながるでしょう。
住民サービスの質を高め満足度向上に貢献する
生成AIの活用により、住民はいつでも正確な情報にアクセスできるようになり、サービス満足度の向上が期待されます。
チャットボット導入によって、夜間や休日でも自治体の情報に簡単にアクセス可能となり、待ち時間や電話対応のストレスが軽減。多言語対応機能を備えれば、外国人住民への情報提供の質も向上し、より多様な住民にとって使いやすい行政サービスの提供が実現します。
自治体に生成AIを導入する際の5つの課題

ここでは、自治体に生成AIを導入する際の課題を5つ紹介します。
- 導入や運用に必要な人材が不足している
- 予算の確保が難しく費用対効果の判断が難しい
- ハルシネーションのリスクがある
- 個人情報や行政データの取り扱いに慎重さが求められる
- 業務フローの見直しが必要になる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
導入や運用に必要な人材が不足している
生成AIの効果的な運用には、AIに関する知識と活用スキルを持つ職員の存在が欠かせません。
しかし多くの自治体では専門人材が不足しており、日常業務の合間にAI導入の準備を進める余裕もないのが現実です。「どこから着手すべきか分からない」といった声も多く、初動の遅れにつながっています。
この課題に対応するには、定期的な職員向け研修やIT勉強会の実施が効果的。他自治体との共同導入や民間の支援付きAIツールの活用により、人的コストを抑えつつ導入のハードルを下げられます。
予算の確保が難しく費用対効果の判断が難しい
生成AIの導入には、システム費用やライセンス、保守運用などのコストが継続的に発生します。初期投資が高額になりやすく、効果の見える化が難しいことから、導入判断が後回しになるケースもあります。
この課題に対しては、削減可能な人件費や作業時間を具体的に数値化し、効果を定量的に示すのが有効です。まずは小規模な業務から段階的に導入を進めれば、リスクを抑えつつ実績を積み上げるアプローチが求められるでしょう。
ハルシネーションのリスクがある
生成AIは正確な情報を出力するとは限らず、誤情報(ハルシネーション)を生成するリスクがあります。
行政では制度説明や手続き案内の誤りが、住民からの信頼失墜や法的問題につながる可能性もあるため、注意が必要です。
リスクを抑えるには、AIの利用を要約・分類・翻訳など限定用途に絞り、出力内容は必ず職員が確認する運用体制を整えましょう。万が一の誤情報に備えた修正・対応フローの明文化も欠かせません。
個人情報や行政データの取り扱いに慎重さが求められる
住民の個人情報や行政データを扱う自治体にとって、生成AIの活用には高度な情報管理が求められます。
クラウド型AIの活用時は、送信データの取り扱いが外部に依存するため、厳しいセキュリティ対策が不可欠です。データの暗号化やアクセス権限の制御、操作履歴の記録など、多層的な防御策が求められます。
必要に応じて、オンプレミス環境や自治体専用クラウドの導入を検討すれば、より高い安全性を確保できるでしょう。
業務フローの見直しが必要になる
生成AIを有効に活用するためには、既存の業務フローやシステム構成の見直しが欠かせません。基幹システムとの連携、データ形式の統一、API整備など、技術的課題が多く、導入初期には一時的に職員の負担が増えるケースもあります。
しかし、業務工程の見直しを通じてAIが機能しやすい仕組みを構築できれば、将来的に大幅な効率化が見込めます。適用範囲を明確にし、段階的に進めると良いでしょう。
生成AIを自治体に導入する前にやっておくべきこと

最後に、生成AIを自治体に導入する前にやっておくべきことを5つ紹介します。
- AI導入によるリスクや課題を事前に洗い出す
- 業務のどの部分に生成AIを活用するかを明確にする
- 小さな業務から段階的に導入して検証する
- 現場の職員と連携し活用イメージを共有する
- 行政のガイドラインや導入事例を参考に導入計画を立てる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
AI導入によるリスクや課題を事前に洗い出す
住民への誤情報提供や、個人情報漏えいといったリスクを想定しておくのが不可欠です。
生成AIは誤った情報を出力する場合があり、自治体の信頼低下につながる恐れがあります。
行政データの取り扱いでは、暗号化やアクセス制限など高度なセキュリティ対策が必要です。費用対効果の不明瞭さも障壁になるため、総務省の資料などをもとにリスクと対策を明確化しましょう。
業務のどの部分に生成AIを活用するかを明確にする
生成AIの導入により何を改善したいのか、目的と対象業務を明確にすると良いでしょう。
総務省の事例では、挨拶文や議事録の作成など、定型業務からの導入事例が多く見られます。チャットボットの活用も、住民対応の効率化に効果的です。
まずはAIの適性が高い業務領域を絞り込み、段階的な導入を進めましょう。
小さな業務から段階的に導入して検証する
大規模な導入ではなく、スモールスタートで効果を検証する方法が現実的です。
具体的には、一部署にチャットボットを導入し、成果を観察することから始めます。少しずつ実績を積めば、職員の理解と導入への抵抗感を和らげる効果も期待できるでしょう。
初期段階の成功体験が、全庁的な展開の土台になります。
現場の職員と連携し活用イメージを共有する
AIを導入する目的や活用方法を職員と共有し、導入後の混乱を防ぎましょう。
AIは人手の代替ではなく、職員の業務を支援するツールであるという認識を広める必要があります。勉強会や研修を通じて知識を底上げし、職員が安心して使える環境づくりを意識するのがおすすめです。
行政のガイドラインや導入事例を参考に導入計画を立てる
総務省のガイドブックや他自治体の先行事例を参考に計画を練ると、失敗を防げます。
たとえば、愛知県や兵庫県などの導入事例から、プロセスや効果を学べます。事前に全体像を描き、目的・予算・スケジュールを明確にした導入ロードマップを策定しましょう。
自治体の生成AI導入事例を参考にしてビジネスを効率化させよう

本記事では、自治体の生成AI導入状況や、実際に導入されている活用事例を紹介しました。
生成AIは人手不足や住民対応の負担軽減に役立ち、行政サービスの質を維持しながら業務を効率化する手段として活用されています。国の支援制度や事例が増えたことで、導入のハードルも下がりつつあります。
【自治体AI導入のヒントになるポイント】
- 導入前に活用範囲やリスクへの対応方針を明確にする
- まずは小規模な業務からテスト的に活用を始める
- 国のガイドラインや他自治体の事例を参考に導入を検討する
自治体のAI導入事例を参考にしながら、自社にとって最適なAI活用のかたちを模索してみてください。