ChatGPTは業務効率化やアイディア創出に役立つ一方、以下のような悩みから利用をためらう方も少なくありません。
「ChatGPTに入力した情報が漏えいしないか心配」
「著作権侵害やサイバー攻撃のリスクが怖い」
「ChatGPTの回答が本当に正しいのか不安」
そこで今回は、ChatGPTの利用にともなうリスクについて、具体的な事例や対策を詳しく解説します。
【記事を読んで得られること】
- ChatGPTのセキュリティ、倫理、社会的なリスク
- 具体的な情報漏えい、著作権侵害、サイバー攻撃事例
- リスクを軽減するための具体的な対策
ChatGPTのメリットを最大限に活かしつつ、リスクを最小限に抑えるためのポイントを紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
ChatGPTの主なリスク6選

ここでは、ChatGPTの利用にともなう主なリスクについて、下記の側面からそれぞれ3つずつ解説します。
- セキュリティリスク
- 倫理的・社会的リスク
ChatGPTを安全かつ効果的に活用するには、リスクを理解して適切に対策する必要があります。特に企業単位で導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
セキュリティリスク
ChatGPTのセキュリティリスクに関しては、以下3つを押さえておくと良いでしょう。
- 情報漏えいのリスク
- 著作権侵害のリスク
- サイバー攻撃のリスク
セキュリティリスクは個人や企業にとって重大な損害につながる可能性があるため、事前に対策を打っておくのがおすすめです。
情報漏えいのリスク
ChatGPTを利用する際は、情報漏洩に最大の注意を払いましょう。ChatGPTに入力された情報はAIの学習データとして利用される可能性があり、他人のプロンプトに対する回答として流用されるリスクがあります。
もし社内の独自ソースコードや顧客データが流出すれば、その被害は自社だけに留まりません。
そのため、機密情報に関する記述を禁止したり、ChatGPTの学習機能を制限したりして対策してみてください。
学習機能(オプトイン)を制限するやり方については、以下の記事を参考にしてください。

著作権侵害のリスク
ChatGPTはすでにネットなどで公開されている著作物も学習データとして利用しているため、生成されたコンテンツが似通ってしまうリスクがあります。
特に商用目的で利用する場合は注意が必要であり、あまりにコンテンツが酷似し過ぎていると著作権侵害にあたる可能性もゼロではありません。
また、ChatGPTで生成された文章は、基本的に参考元がわからないため、あくまで自社で生成内容をチェックし、事前に対策する必要があります。まずは著作権に関する知識を身につけ、適切に引用をつけるルールなども設けるようにしてください。
サイバー攻撃のリスク
ChatGPTを利用するうえで注意する必要はないものの、ChatGPT自体がサイバー攻撃に悪用されるリスクについても把握しておくべきです。具体的には、フィッシング詐欺のメール作成や機密情報を抜き取るプログラム生成などがあげられるでしょう。
実際のところ、ChatGPTは非常に高い言語能力を持つため、ユーザーが違和感を抱かないような精度の高いメールを生成できます。加えて、知識のない人でも簡単にプログラミングコードを作れるので、そういった危険性を秘めている点も踏まえて利用してください。
なお、自社がサイバー攻撃のリスクに対処するには、セキュリティ対策ソフトを導入するか、そもそも不審なメールを開かないルール付けも徹底しましょう。
倫理的・社会的リスク
次は、倫理的・社会的な側面からChatGPTのリスクを解説していきます。
- 誤情報拡散のリスク
- 差別的表現のリスク
- 依存による能力低下のリスク
SNSが発達した昨今、倫理性を欠いたコンテンツを発信すると瞬く間に拡散され、企業のブランド性を損なう結果になりかねません。事前にリスクを把握し、対策を講じていきましょう。
誤情報拡散のリスク
ChatGPTは学習データにもとづいて自律思考する機能を持つ一方、誤った情報を生成するリスクがあります。偏った情報を拡散するケースもゼロではなく、ChatGPT自身では情報の審議を判断しきれないため、最大限に注意した方が良いでしょう。
専門的な情報やトレンド系の内容は特に誤った回答を生成しやすいため、ChatGPTによる生成結果を鵜呑みにせず、必ずファクトチェックを行ってください。誤った情報を拡散しないよう、ネットに公開する際のチェックリストなどを設けるのもおすすめです。
差別的表現のリスク
学習データに偏りがある場合、ChatGPTは差別的な表現を含む文章を生成するリスクがあります。人種差別や性差別、ジェンダーに関する表現は非常にセンシティブなので、こまめに生成内容を確認するべきです。
また、ChatGPTは優れた機能を持つものの、人間ほどの理解力は持っていません。つまり、文章の背景にある感情や本心は理解できないため、その観点からも注意した方が良いでしょう。
生成された文章は必ず人間がチェックし、不適切な表現がないかを確認するようにしてください。
依存による能力低下のリスク
ChatGPTは文章や画像生成、分析能力などに長けているものの、過度に依存すると人間の思考力・想像力が伸びにくくなる懸念があります。たとえば、新入社員にChatGPTの使い方をレクチャーすれば、始めから本格的な水準で業務を進められますが、あまりに簡単過ぎて自己学習する意欲を失うリスクもあるのです。
無論、これはベテランの社員にも共通する問題ですから、ChatGPTはあくまでも補助的なツールとして利用し、最終的なチェックやクリエイティブな要素は人間が行うように心がけましょう。
ChatGPTのリスク事例3選

次に、ChatGPTのリスクに関連する具体的な事例を3つ解説します。
- 機密情報の流出事例
- 著作権侵害訴訟事例
- マルウェアによるサイバー攻撃事例
自社の利用傾向、頻度と近いものを参考にし、安全に活用できる体制を整えていきましょう。
機密情報の流出事例
ChatGPTでは情報漏洩リスクに最大限注意する必要があり、実際に複数の企業で情報漏えいが発生しています。
たとえば、韓国のサムスン電子ではエンジニアが社内機密のソースコードをChatGPTにアップロードし、情報が外部に流出しました。
また、ある企業の半導体事業部では、エラー解決のためにソースコードをChatGPTに入力した結果、同様の流出事故が複数回発生したケースもあります。
上記の通り、ChatGPTに機密情報を入力するのはリスキーであり、先ほど触れた事前のルール作りやAPI版を利用するなどの対策が必要です。もしAPI版について知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。

著作権侵害訴訟事例
著名なSF作家が、自身の著作物をChatGPTの学習に利用され、著作権を侵害されたとしてOpenAIを提訴する事例も発生しています。これは商用目的でChatGPTを利用する企業全体にあり得る事例なので、生成されたコンテンツはよく確認するようにしましょう。
やや手間はかかりますが、Googleの画像検索で調べたり、専門スタッフを配置して関連性の高いメディアを調べさせた方が安全です。
マルウェアによるサイバー攻撃事例
ChatGPTは、マルウェアを利用したサイバー攻撃にも悪用される可能性があります。
2023年6月には、マルウェアに感染したデバイスからChatGPTのアカウント情報が盗まれ、10万件以上のアカウント情報がダークWebで売買される事件が発生しました。
これは単に悪用されるうえでの注意喚起だけでなく、そこから情報漏洩につながるリスクも浮き彫りになった事例と言えます。
ChatGPTのリスク対策6選

ここからは、ChatGPTを安全に利用するためのリスク対策を6つ紹介します。
- 情報漏えい対策
- 著作権侵害対策
- マルウェア対策
- 誤情報対策
- 不適切な表現対策
- 依存対策
それぞれの対策を理解し、適切な対応策を講じることで、ChatGPTのメリットを最大限に引き出し安全に利用できるでしょう。
情報漏えい対策
ChatGPTで最も注意するべき情報漏洩を防止するには、そもそも機密情報を入力しないようにするのがおすすめです。
顧客の個人情報、社内に留めるべき伝達事項、独自のプログラミングコードなどは特に入力するべきではなく、社員一人ひとりの教育が必要不可欠になってきます。
ただ、社員全員を教育する余裕がなければ、APIか企業向けプラン「Enterprise」を検討してみてください。これはChatGPTの学習機能「オプトイン」が始めから制限されており、通常プランよりも機密性・セキュリティ性に長けています。
以下の記事でさらに詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

ChatGPTの「情報漏洩」や「意図しない情報共有」について、本当に防げているのか不安に感じる方も少なくないのではないでしょうか?
もしセキュリティ面で不安を感じる場合には、AIによる業務効率化やセキュリティ対策のプロである株式会社エヌイチに相談をしてみてください。
現在エヌイチではAIの活用に不安を感じている人の力になるために、「業務効率を10倍にする現場ですぐ使えるプロンプト20選」の無料受け取りをしてくれた企業様に向けて、無料相談のご案内をしています。
セキュリティ対策も含めてAIについて相談をしてみたい方や、業務効率化に役立つプロンプトが必要な方は、ぜひ気軽に資料を受け取ってみてください。
著作権侵害対策
ChatGPTの利用における著作権侵害のリスクを減らすには、生成されたコンテンツが既存の著作物を模倣していないか確認しましょう。先ほど触れた通りGoogleでの画像検索や専門スタッフによる人力でのチェックが効果的となります。
もし会社全体でChatGPTを商用利用するなら、社内での研修や教育プログラムを設け、著作権に関する知識を教育するのもおすすめです。
マルウェア対策
ChatGPTを悪用したマルウェア攻撃を防ぐには、セキュリティ対策ソフトの導入が不可欠です。
しかし、ただセキュリティソフトを導入するだけでは十分ではありません。常に最新の状態にアップデートし、必要に応じてソフトを切り替えるのも忘れないようにしましょう。また、不審なメールやリンクを開かない点については、社員への教育がなにより重要。こちらも定期的に注意喚起するなど、組織的に取り組んでみてください。
誤情報対策
ChatGPTが生成する誤情報(ハルシネーション)に対処するには、普段から回答内容を鵜呑みにしない姿勢が大切です。ChatGPTはインターネット上の情報を学習していますが、情報の真偽を判断する能力はありません。
たとえ「ファクトチェックして」と指示を出しても完璧な精査は難しいでしょう。そのため、生成された情報は人間の手で必ず確認し、複数の情報源と照らし合わせるようにしてください。ChatGPTの利用ルールを定め、回答結果をどのように利用するかを明確にするのも有効です。
不適切な表現対策
ChatGPTの生成内容に差別的、倫理的に問題のある表現が含まれないかどうかも重要なチェックポイントです。どれだけ精度が高いとは言え、人間の感性まで判断する能力は備わっていませんから、こちらも人間の手で確認するようにしましょう。
加えて、不適切な表現を問題のない形に修正するための知識・技術的な教育も事前に行うのがおすすめです。
依存対策
ChatGPTへの過度な依存を防ぐには、ChatGPTと人間の役割を明確に区別するようにしてください。ChatGPTはあくまでサポートツールであり、最終的な意思決定は人間が行うべきです。
新入社員などがChatGPTに頼りすぎて成長を止めないよう、上記の意識を最初に教育し、利用できるタスクや時間も制限した方が良いでしょう。
そして、社員が自ら考えた内容や分析をしっかり評価し、自主的に向上していくモチベーションを維持することも、社内体制として整備するのがおすすめです。
ChatGPTのメリット

ChatGPTは高度な自然言語処理能力を持ち、まるで人間と対話しているかのような応答が可能なAIツールです。情報検索、文章作成、翻訳、プログラミングコード生成など、多岐にわたる業務を効率化するサポートツールとして、多くの企業や個人に利用されています。
もちろん、ビジネスでも顧客対応の自動化、メールや資料作成の効率化、新しいアイディアの創出など、活用範囲は徐々に広がっています。
その他にも様々なメリットがあるため、今後利用する際はぜひ押さえておきましょう。
- リサーチを効率的に行える
- 回答をさらに深掘りできる
- 文章の要約・翻訳
- プログラミングコード作成
なお、今回はChatGPTのリスクをメインに解説しましたが、以下の記事では具体的な使い方やより多くのメリットを掲載しています。

ChatGPTのリスクを理解して適切に使いこなそう
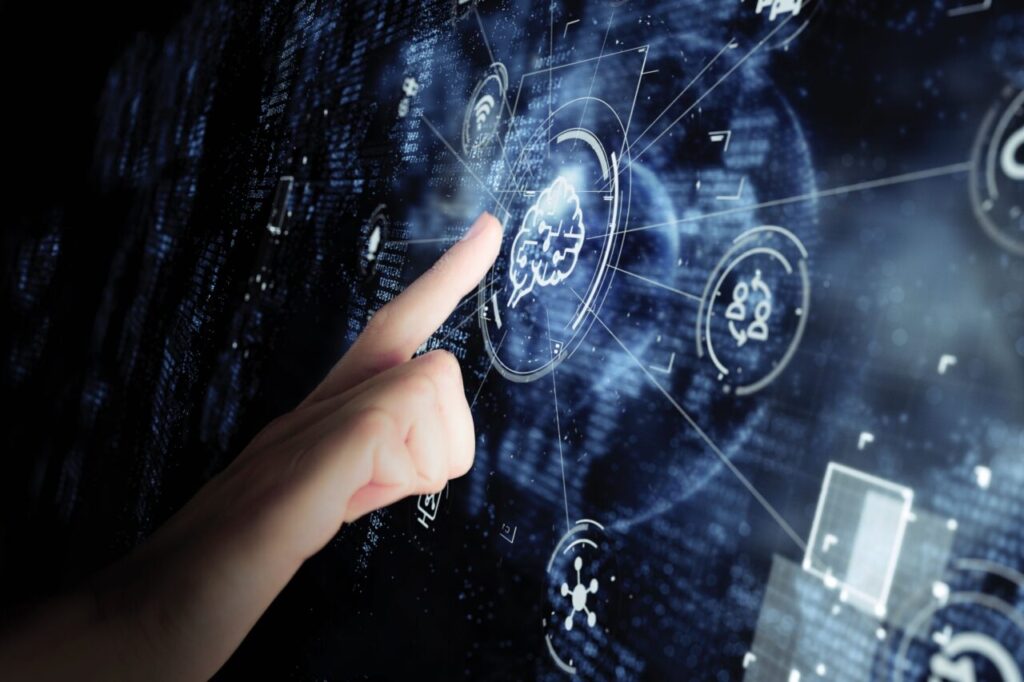
この記事では、ChatGPTの利用にともなう様々なリスクと対策について解説しました。
ChatGPTは便利なツールですが、情報漏えい、著作権侵害、誤情報拡散、依存による能力低下など、さまざまなリスクが存在します。これらのリスクを理解したうえで、適切に対策していきましょう。
【ChatGPTのリスクを軽減するための対策】
- 個人情報や機密情報を入力しない
- 生成されたコンテンツの著作権関連を必ず確認する
- 必ずファクトチェックを行う
ChatGPTはサポートツールとして適切に活用すれば心強い味方になります。ぜひ本記事を参考に、リスク管理をしながら安全にChatGPTを活用してみてください。












