病院にAIを導入したいと考えていても、以下のような悩みによって判断を迷っている方も少なくありません。
「病院にAIを導入したいが、ROIや現場とのギャップが見えない…」
「病院の人手不足を補いたいけれど、AI活用を失敗するリスクが怖い…」
そこで今回は、病院におけるAI活用のメリット・デメリット・事例を詳しく解説します。
【記事を読んで得られること】
- AI導入による業務効率化と医療精度の向上
- 実際にAIを活用している病院の事例7選
- 病院でAIを導入する際の注意点と進め方
AI導入のステップも解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
病院にAI導入が求められる背景

まず、病院にAI導入が求められる背景を以下の3点で解説します。
- 医療人材の慢性的不足
- 現場の過重労働や業務負担の増大
- 高齢化による医療需要の急拡大
それぞれ詳しく見ていきましょう。
医療人材の慢性的不足
日本では少子高齢化によって医療従事者の減少が深刻化しています。
地方では特に顕著で、救急外来や外科など負担の大きい診療科では医師の離職も見られているのです。現場では専門外の診療に対応するケースも増えており、業務の偏りが発生しているのはご存じでしょうか。
AIを導入すれば、問診や診断支援を通じて医療従事者の負担を軽減でき、専門性の高い業務に集中しやすくなります。限られた人員でも、一定の医療水準を保てる体制構築につながるでしょう。
現場の過重労働や業務負担の増大
医療現場では長時間労働が常態化しており、人員不足と相まって時間外労働の抑制が困難な状況が続いています。「働き方改革」により労働時間の制限は強化されていますが、業務量は変わっていません。
AIは退院サマリーの自動作成・カルテ記録補助・診療報酬の計算支援などを担い、事務負担を軽減します。医師や看護師が患者との対話や処置に集中しやすくなり、結果的に医療サービスの質を向上させられるでしょう。
高齢化による医療需要の急拡大
高齢者の増加によって生活習慣病や慢性疾患の治療ニーズが急増しています。重症化リスクが高い高齢者の入院対応には介助や観察業務が多く、医療スタッフの負担がさらに増しているのが現状です。
AIは来院前の問診や診断支援、治療方針の提案などで効率化を図れます。また、医療データの解析によって医師の判断を補い、専門外の領域でも適切な診療が可能になるでしょう。
AIにより、医師の少ない地域でも質の高い医療提供が可能になります。
病院にAIを導入する5つのメリット

ここでは、病院にAIを導入するメリットを5つ紹介します。
- 診断精度を高められる
- 病気の早期発見が可能になる
- 患者の状態に応じた適切な治療や予防策を提示できる
- 事務作業やデータ処理を自動化できる
- 医療スタッフの業務負担を軽減できる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
診断精度を高められる
AIは医療画像や診療情報を分析し、疾患の判別や異常の検出に活用されています。過去の症例や診断結果を学習すれば、医師の判断が分かれやすいケースでも一貫性のある分析を支援できるでしょう。
画像診断においては、CTやMRIで検出が難しい微細な病変に対しても数値や確率で根拠を提示できます。診断時の見落としを防ぎ、判断のばらつきを抑える補助として有効です。
病気の早期発見が可能になる
医療データを用いて、疾患のごく初期に表れるわずかな異常もAIは見逃さず検出します。特に、進行すると治療が難しくなる病気では、初期段階での判断が患者の予後に直結するため、早期対応の精度が重要です。
AIは症状が軽微な段階でも、過去のパターンをもとにリスクを数値化できます。早期の発見と対応が可能になれば、治療機会を逃さず医療の質を高める結果につながるでしょう。
患者の状態に応じた適切な治療や予防策を提示できる
AIは患者の検査データ・年齢・既往歴などをもとに状態を分析し、個別に最適な治療や予防策を提案する仕組みに応用されています。標準的な治療だけでは対応が難しいケースにも柔軟に対応できます。
また、リアルタイムに収集された体調データから健康状態の変化を把握し、早めの対策に役立てることも可能。画一的な対応ではなく、患者ごとの特性を反映した医療提供が実現できるでしょう。
事務作業やデータ処理を自動化できる
カルテ入力・退院サマリーの下書き作成・診療報酬の算定などの定型業務は、AIによる自動処理が可能です。医療スタッフが手作業でしていた作業を短時間で処理でき、負担軽減につながるでしょう。
記録ミスの抑制や、情報整理の手間を削減する効果もあります。事務作業を効率化すれば、医療従事者が患者ケアや専門性の高い業務に集中しやすくなるでしょう。
医療スタッフの業務負担を軽減できる
AIを導入すれば、問診支援・診療記録の補助・文書作成などの業務を自動化できます。AI導入により、スタッフが担当する作業量が軽減され、長時間労働の抑制にもつながるでしょう。
また、情報整理や確認作業の手間が減ることで、ミスを防ぎ業務効率を高められます。さらに、人が担うべき処置や患者対応に集中できる体制が整い、働きやすい環境づくりにもつながるでしょう。
病院にAIを導入する際の3つのデメリット
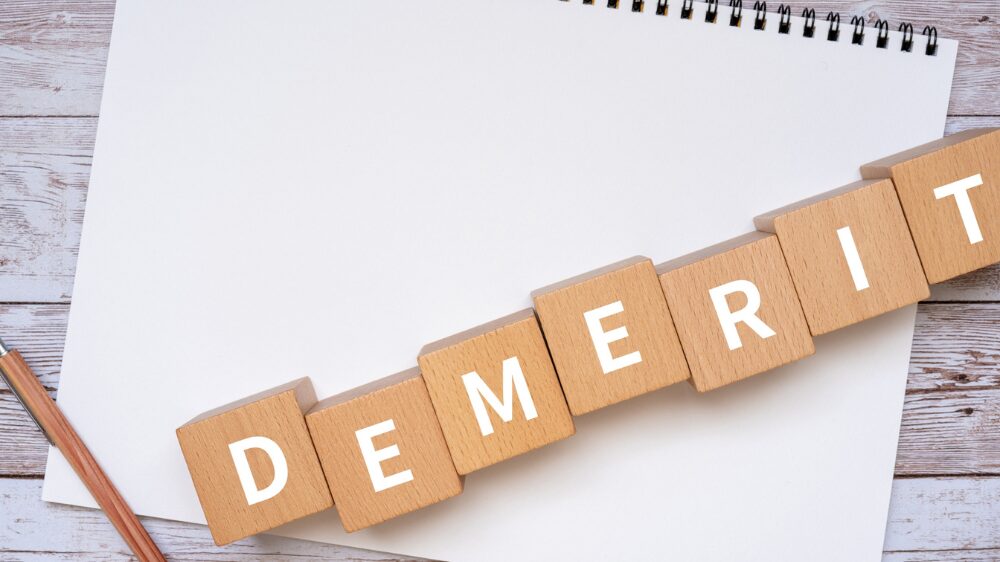
ここでは、病院にAIを導入する際のデメリットを3つ紹介します。
- AIにすべての業務を任せられない
- 学習に必要な症例データの確保が難しい
- 導入・維持コストが高額になりやすい
それぞれ詳しく見ていきましょう。
AIにすべての業務を任せられない
医療現場の多様な業務をAIで支援できますが、すべてをAIだけで完結させる運用は現実的ではありません。技術には得意分野と不得意分野があり、法的リスクや判断ミスを避けるためにも、運用範囲を適切に定める必要があります。
AIは学習データをもとに診断支援が可能ですが、最終的な判断は医師が担うべきです。誤診のリスクがある以上、人間とAIの役割を明確に分けて活用しなければなりません。AIはあくまで補助ツールであり、医師の判断を支える存在として活用することが前提です。
学習に必要な症例データの確保が難しい
AIの精度向上には、正確かつ大量の症例データを用いた学習が欠かせません。しかし、医療分野では教師データの質が診断結果に直結するため、信頼性の高いデータを収集・整備する作業が大きな負担となるでしょう。
アノテーション作業には医師の関与が必要なケースも多く、業務量の増加によって本来の目的である負担軽減が実現しない恐れもあります。そのため、AI導入にあたっては、データ整備の役割分担や作業工程の効率化があらかじめ設計されていなければ、逆に現場の負荷を増やす結果になりかねません。
導入・維持コストが高額になりやすい
AIの導入にかかる初期費用や維持費は、医療機関にとって大きな負担になりがちです。システム開発や導入には、医療・AI・データ分析の専門知識を持つ人材の確保も必要であり、その分コストが上昇する傾向があります。
また、システムそのものの費用だけでなく、運用体制の整備や人材育成にかかる継続的な支出も見込まなければなりません。費用対効果を正しく評価できなければ、導入判断が難航する要因となります。
投資の検討にあたっては、短期的な成果だけでなく、中長期的な視点で運用コスト全体を精査する必要があるでしょう。
医療業界でのAI活用事例7選

ここでは、医療業界でのAI活用事例を7つ紹介します。
- エルピクセル株式会社により開発された画像診断支援AI「EIRL(エイル)」シリーズ
- 昭和大学横浜市北部病院の工藤教授らが開発した「EndoBRAIN」
- 国立がん研究センターと日本電気株式会社が共同開発した「WISE VISION 内視鏡画像解析AI」
- アステラス製薬とホルター心電図解析ベンチャーが共同で開発した「マイホルターII」
- メディカロイド社により開発された国産初の手術支援ロボット「hinotori(ヒノトリ)」
- Ubie株式会社が提供する「ユビーAI問診」
- 株式会社medimoが開発した診療支援ツール「medimo(メディモ)」
それぞれ詳しく見ていきましょう。
エルピクセル株式会社により開発された画像診断支援AI「EIRL(エイル)」シリーズ
EIRL(エイル)は、医療画像の診断を支援するAIシリーズで、医師の作業を効率化し精度も高めます。エルピクセル社が開発し、脳動脈瘤の検出から始まり、頭部・胸部・大腸の3領域で9製品を展開しています。
全国47都道府県の900超の医療機関に導入され、解析件数は1,000万件を超えました。特に健康診断施設では胸部X線解析で導入が進み、大量データの短時間処理と高精度な診断が実現されています。
医師はAI解析を参考にすることで、診断のスピードと正確性を両立でき、業務の負担も軽くなるでしょう。
昭和大学横浜市北部病院の工藤教授らが開発した「EndoBRAIN」
「EndoBRAIN®」は、大腸内視鏡検査中にポリープの性質を識別し、診断を支援するAIです。
開発には昭和大学の工藤教授に加え、名古屋大学大学院とサイバネットシステムが連携し、2013年から研究が進められました。国内5施設での臨床試験を経て、クラスⅢの高度管理医療機器として承認を取得しています。
AIが検査中に腫瘍性・非腫瘍性を判別し、医師は見落としを減らしながら安定した判断が可能になります。
診断精度が向上すれば、大腸がんの早期発見にもつながる体制が整うでしょう。
国立がん研究センターと日本電気株式会社が共同開発した「WISE VISION 内視鏡画像解析AI」
「WISE VISION」は、内視鏡検査中にがんや前がん病変を検出するAI画像解析ソフトです。
国立がん研究センターとNECが共同開発し、1万件以上の内視鏡画像を学習したAIが非典型な病変にも対応できます。
検査中に疑わしい部位を通知音とマークで表示すれば、医師が見落としやすい箇所にも注意を向けやすくなるでしょう。
技術差に左右されにくく、検査時間を延長せずに診断精度を高められる点も特徴です。大手内視鏡メーカー3社の機器と連携可能で、既存設備でも導入しやすい構成です。
アステラス製薬とホルター心電図解析ベンチャーが共同で開発した「マイホルターII」
アステラス製薬とエムハートが開発した「マイホルターII」は、心電図データをAIで解析するクラウド型サービスです。
10万拍以上の心拍データをAIが自動で処理し、心房細動の早期発見や解析の負担軽減につながるでしょう。
医療従事者は場所を選ばずリモートで解析でき、業務効率の向上にも直結します。国際規格準拠のデータ形式を採用し、複数メーカーの心電計と互換性がある点も現場向きです。
慢性疾患の重症化を防ぐためのツールとして、アステラスのRx+®事業の中で本格展開されています。
メディカロイド社により開発された国産初の手術支援ロボット「hinotori(ヒノトリ)」
「hinotori(ヒノトリ)」は、メディカロイド社が開発した国産初の手術支援ロボットです。
川崎重工業とシスメックスが共同出資し、2020年に開発。慶應義塾大学病院では、米国製の「da Vinci」と並行して導入されています。
術者は3D画像を確認しながら遠隔でロボットを操作し、人間の手では難しい繊細な動作も再現可能。ロボット鉗子は多関節構造かつ手ぶれ補正機能を持ち、精度の高い操作を実現します。傷口が小さく済めば、患者の回復期間も短縮されるでしょう。
Ubie株式会社が提供する「ユビーAI問診」
「ユビーAI問診」は、患者がスマートフォンやタブレットで症状を入力できる問診支援ツールです。
紙の問診票を置き換える形で導入されており、入力内容は自動で文章化され、病名候補と共に医師に提供されます。カルテ記載の手間が削減されれば、医師は診察や対話など本来の業務に専念しやすくなるでしょう。
一部の導入クリニックでは、診察前の待機時間が平均10分短縮された事例もあります。
全国1,000超の医療機関で活用されており、生活者向け「症状検索エンジン ユビー」との連携により認知向上も図られています。
株式会社medimoが開発した診療支援ツール「medimo(メディモ)」
「medimo(メディモ)」は、音声認識と生成AIにより診療記録を効率化する支援ツールです。
医師と患者の会話を院内専用スマートフォンで録音し、文字起こしと要約をリアルタイムで実施。生成AIが約1,000字にまとめた内容は2次元バーコードに変換され、電子カルテ端末で読み取れば1分ほどで記録作業が完了します。
兵庫医科大学病院では、大学病院で初めて正式導入されました。医師の記録時間と精神的負担の両方を減らすとともに、要約しやすい話し方を意識することで説明スキルの向上にもつながります。
病院でAI活用を進める5つのステップ

ここでは、病院でAI活用を進めるステップを紹介します。
- 【STEP1】AI導入の目的と適用する業務を明確化する
- 【STEP2】活用範囲と既存業務との連携方法を決める
- 【STEP3】小規模な試験運用や概念実証(PoC)を行う
- 【STEP4】試験結果をもとに改善点を反映して本格導入する
- 【STEP5】運用後も効果測定と定期的な見直しを実施する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
【STEP1】AI導入の目的と適用する業務を明確化する
AI導入を進めるには、業務上の課題を洗い出し、解決すべき内容を明確にするのが前提になります。人件費の削減や業務効率化を目指す場合は、医療文書の作成、問診、診療報酬の算定といった定型業務を対象に検討するのが一般的です。
医療文書関連などの反復作業をAIで自動化すれば、医師や看護師が専門的な診療や看護に専念しやすくなるでしょう。
【STEP2】活用範囲と既存業務との連携方法を決める
適用業務が決まったら、AIが担う業務範囲と既存システムとの連携方法を設計します。特に電子カルテとの連携は重要で、カルテ情報を活用して文書作成やデータ抽出する仕組みが求められます。
AI導入は職員の役割にも影響するため、人とAIの役割分担を明確化し、ツールとしての利点を共有しましょう。従業員の理解を得ることが、導入後の定着とDX推進の基盤になります。
【STEP3】小規模な試験運用や概念実証(PoC)を行う
AIを本格導入する前に、対象業務を限定した小規模なPoC(概念実証)を実施するのが有効です。PoCにより、リスクを抑えながらAIの有効性や実現性を検証できます。
退院サマリー作成時間の短縮など、具体的な改善効果が確認できれば、導入判断の根拠になるでしょう。PoCで得た課題や改善点を反映させれば、本導入後のシステム精度や運用効率も高められます。
【STEP4】試験結果をもとに改善点を反映して本格導入する
PoCの結果を踏まえて、本格導入に向けたAIシステムの調整と運用設計を進めます。開発フェーズでは、アジャイル型で機能を改善しながら最適化する方法が効果的です。
同時に、職員向けトレーニングや運用マニュアルの整備も必要です。技術面だけでなく、人や組織全体が対応できる体制を構築すれば、継続的な改善にもつながります。
【STEP5】運用後も効果測定と定期的な見直しを実施する
AI導入後は、効果測定と定期的に見直しをする体制が求められます。AI技術の進化に合わせて、新たな活用法の導入や機能拡張の検討も視野に入れる必要があります。
また、患者データの安全管理や誤診リスクへの対策も欠かせません。システム面でのセキュリティ強化と、職員向けの利用ルール整備を両立させれば、AIを継続的な資産として活用できます。
病院でAIを導入する際の5つの注意点

最後に、病院でAIを導入する際の注意点を5つ紹介します。
- AI診断や予測の誤りによる医療リスクに備える
- 十分な精度を確保できる学習データを収集・整備する
- 患者情報の漏えいや不正利用を防ぐ管理体制を構築する
- 導入目的や活用範囲を明確にし定期的に見直す
- AI運用や保守を担える専門人材を確保・育成する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
AI診断や予測の誤りによる医療リスクに備える
AIは医療診断や予測を支援できますが、常に正確な判断ができるとは限りません。学習データに偏りがある場合や、想定外の症例では、誤診や不適切な予測が発生する可能性があります。
AIに全依存せず、最終的な判断は必ず医師が担うべきです。AIは業務を補助する手段であり、使い方を誤るとリスクを高めかねません。診断支援の役割を明確にし、医師とAIの責任範囲を事前に整理しておく必要があるでしょう。
十分な精度を確保できる学習データを収集・整備する
AIの精度は、学習に使用するデータの質に大きく左右されます。医療分野では機密性の高い情報を扱うため、質の高いデータを収集し、適切に整備する作業が欠かせません。
データには正確なラベル付けが必要で、医師によるアノテーションが発生する場合、業務負担の増加につながります。学習用データを確保する際には、医師の負担を軽減する体制づくりも併せて検討すべきでしょう。
患者情報の漏えいや不正利用を防ぐ管理体制を構築する
AIシステムは個人の診療情報を扱うため、情報漏えいや不正利用のリスクに常に注意が必要です。セキュリティ対策が不十分な場合、信頼性の損失や法的責任が発生する恐れがあります。
暗号化やアクセス管理の徹底、オプトアウト設定の有効化などが求められます。加えて、職員への運用ルールの周知や定期的なセキュリティ教育によって、安全な運用体制を維持する仕組みを構築しましょう。
導入目的や活用範囲を明確にし定期的に見直す
AIを導入する際は、適用対象と期待する成果を明確に定める必要があります。すべての業務に適しているわけではなく、業務特性に応じた使い分けが不可欠です。
導入後は、技術動向や課題の変化を踏まえて運用方法を定期的に見直します。一度きりの設計で終わらせず、柔軟に活用範囲や手法をアップデートしていく体制を整えましょう。
AI運用や保守を担える専門人材を確保・育成する
AIを安定運用するには、医療知識とAI技術の両面に精通した人材が欠かせません。スムーズな導入とトラブル対応のためにも、専門スキルを持つ担当者の確保が必要です。
外部人材の登用に加えて、既存職員の育成も同時に進める必要があります。社内研修や実践的なトレーニングを通じて、現場全体がAIに対応できる体制を構築してください。
株式会社エヌイチでも生成AI研修サービスや支援を提供しています。実践的なAIスキルを身につけたい方や興味のある方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
実務に役立つDX人材育成_生成AI研修サービス|株式会社エヌイチ
病院でのAI活用事例を参考に自社ビジネスを効率化させよう

本記事では、病院におけるAI活用の背景や、導入メリット・注意点・成功事例などを解説してきました。
人材不足が深刻化するなかで、AIは医療の質と業務効率を支える有力な手段となりつつあります。一方で、導入コストやリスク管理など検討すべき要素も多く存在します。
【病院でAIを活用するためのポイント】
- AI導入による効果を定量的に見極める
- 活用範囲と業務フローを明確にする
- 導入後も定期的な見直しと人材育成を続ける
医療現場のAI事例を自社の参考にしながら、慎重かつ柔軟に導入を検討してみてください。







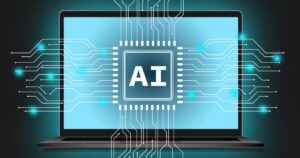





コメント