ChatGPTはビジネスでも役立つ生成AIツールですが、以下のような悩みによって導入に踏み切れない企業や経営者も少なくありません。
「AI投資の必要性は感じるが、具体的にどうビジネスに活かせるのか」
「ChatGPTをビジネスに活用する費用対効果はどうなのか」
といった疑問を抱えていませんか。
競争が激化する現代において、業務効率化は不可欠です。
ChatGPTなどの生成AIは有力なツールとして注目され、多くの企業が検討していますが、具体的な活用法やROIに迷う経営者の方も多いでしょう。
本記事では、ChatGPTの多様なビジネス活用事例を詳細に解説します。
【記事を読んで得られること】
- ChatGPTをビジネスでどのように活用できるか理解できる
- 具体的なビジネス活用事例を知れる
- ChatGPTで業務を効率化するヒントが得られる
ChatGPTをはじめとするAI活用成功の戦略や注意点もご紹介しますので、ぜひ参考にしてみて下さい。
ChatGPTはビジネスシーンで活用できる?
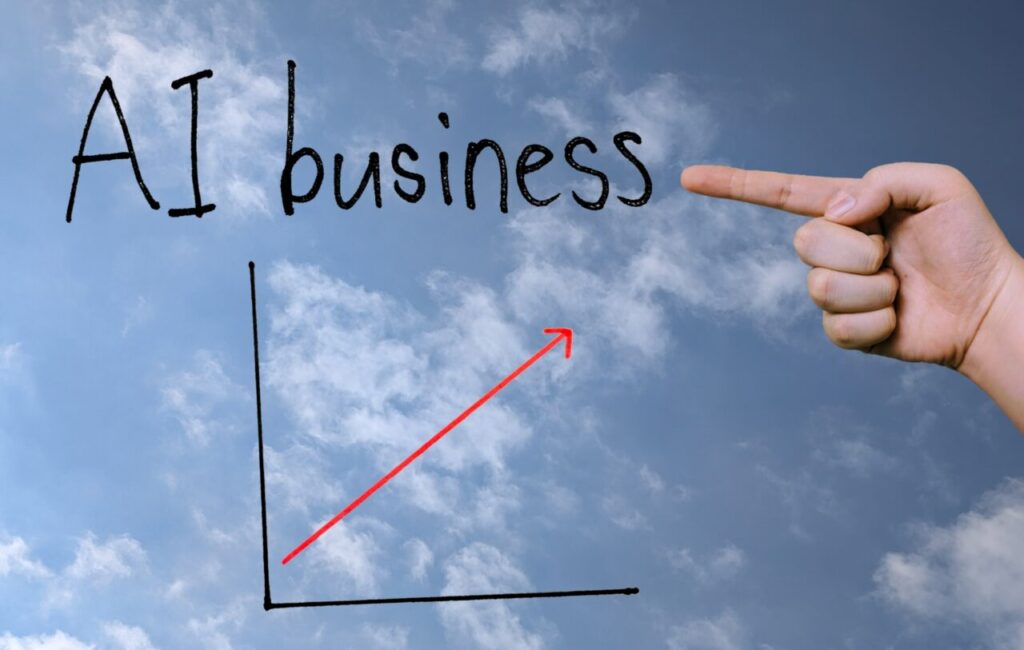
最近では、AIチャットサービスの代表例であるChatGPTが、ビジネスの現場で多様な形で活用できる存在として注目されています。
企業規模や業種にかかわらず、業務効率を高め、生産性を大きく改善できる可能性を秘めているのが、AI導入が進んでいる背景にあるでしょう。
特に、定型業務や情報収集、文章作成のように時間のかかるタスクをAIが担当すれば、人件費の削減だけでなく、従業員がより創造的で価値の高いコア業務に集中できる環境づくりにもつながります。
ChatGPTの汎用性の高さと、自然な文章を生み出す能力を活かせば、これまでの常識を覆すような業務改革が実現できるかもしれません。
ただし、導入を検討する際には、具体的な費用対効果や組織文化、社員スキルなどについて慎重に考える必要があります。競合に後れを取らず、かつ早まった失敗を防ぐためには自社の業務内容を正確に分析し、ChatGPTが得意とする領域を見極めると良いでしょう。
ChatGPTの部門別ビジネス活用事例20選

ここでは、ChatGPTのビジネス活用事例を8つの部門別に紹介します。
- マーケティング部門
- 営業部門
- カスタマーサポート部門
- 人事部門
- 製品開発部門
- 法務部門
- IT部門
- 経営企画部門
それぞれ詳しく見ていきましょう。
マーケティング部門
まず、マーケティング部門でのビジネス活用事例を3つ紹介します。
- メルマガ用の文章生成
- SNS投稿の効率化
- キャッチコピーなどの広告文案の生成
ChatGPTを活用すれば、マーケターは分析や戦略立案といった、より付加価値の高い業務に専念できるでしょう。
メルマガ用の文章生成
ChatGPTは、顧客セグメントごとに最適な件名や本文を作成する作業にも効果を発揮します。たとえば、30代女性や学生など、ターゲット層の特性に合わせた表現を、指示するだけで生成できます。
個別対応にかかる工数を大幅に削減できるため、セミナー告知メールでは反応率が約3倍に向上した例も見られました。メール配信にかかる作業時間を短縮しつつ、開封率やクリック率の向上も期待できるでしょう。
SNS投稿の効率化
SNS運用においては、ChatGPTを使って投稿文やハッシュタグを効率的に作成できます。発信したい情報やターゲット、文体を具体的に伝えると、目的に沿った投稿案を提案してくれるでしょう。
日々の投稿作業にかかる時間を短縮できるため、マーケターは新たな施策立案に時間を使えるようになります。実際に、HubSpotでは障害情報や海外ニュースを積極的に発信し、投稿数を増やすのに成功しています。
キャッチコピーなどの広告文案の生成
商品やサービスの魅力を伝えるキャッチコピーの作成にも、ChatGPTは役立ちます。商品の特徴やターゲット、伝えたいメッセージを指示すれば、複数のコピー案を瞬時に生成できるでしょう。
一から考えるよりもスムーズにアイデアを得られるため、質の高い広告戦略を効率よく組み立てられます。生成された案を組み合わせたり磨き上げたりすれば、より創造的な表現にもつなげられるでしょう。
営業部門
ここでは、営業部門でのビジネス活用事例を3つ紹介します。
- プレゼン資料の作成
- 企画提案の壁打ち
- 営業ロールプレイングの相手役
ChatGPTを活用すれば、営業担当者は顧客との関係構築や提案内容のブラッシュアップにより多くの時間を割けるようになるでしょう。
プレゼン資料の作成
営業資料の構成案やたたき台の作成には、ChatGPTの活用が効果的です。製品情報やサービスの特徴、プレゼンの目的を入力すれば、骨組みのしっかりした構成をすばやく提案してくれます。
さらに、図表の挿入やレイアウトの整理も支援できるため、資料作成にかかる工数とコストの削減にもつながるでしょう。提案された内容に人の手を加えれば、より完成度の高い資料へと仕上げられます。
企画提案の壁打ち
ChatGPTを壁打ちの相手として使えば、アイデアを言語化したり、思考を整理したりする作業が進めやすくなります。頭の中にある構想を言葉にすれば、新たな視点や切り口に気づくきっかけにもなるでしょう。
ChatGPTにターゲットや目的を指定すれば、より的確なフィードバックも得られます。個人で抱えがちな思考を広げる補助役として、企画段階から力を発揮します。
営業ロールプレイングの相手役
営業スキルを磨く場面では、ChatGPTに顧客役を演じさせれば、ロールプレイングの相手として活用できます。たとえば、クレーム対応や厳しい質問への応答など、実際のシチュエーションを想定した練習が可能です。
また、トークスクリプトを入力すれば、改善点やより効果的な表現についてフィードバックを得られます。過去のやり取りを再現するかたちで活用すれば、より実践的な訓練ができるでしょう。
カスタマーサポート部門
ここでは、カスタマーサポート部門のビジネス活用事例を3つ紹介します。
- 24時間365日対応のチャットボット導入
- 翻訳機能を活用した多言語対応
- FAQ作成による問い合わせ対応の効率化
ChatGPTが定型的な問い合わせに対応すれば、オペレーターは複雑な問題や高度な対応に集中できる体制を整えられるでしょう。
24時間365日対応のチャットボット導入
ChatGPTを活用したチャットボットを導入すれば、顧客からの問い合わせに24時間365日対応できる体制が整います。リアルタイムでの回答が可能になるため、顧客の待ち時間を大幅に短縮できるでしょう。
一般的な問い合わせはチャットボットが処理し、オペレーターはより高度な対応に専念できます。さらに、独自データを学習させたチャットボットであれば、社内知識の検索ツールとしても活用可能です。
翻訳機能を活用した多言語対応
ChatGPTには多言語に対応する機能が備わっており、カスタマーサポートのグローバル展開にも役立ちます。従来型の翻訳ツールに比べて文脈理解に優れ、自然な対話ができるため、外国語での問い合わせにもスムーズに対応できるでしょう。
多言語対応チャットボットを導入し、人材不足を補いながら、売上向上につなげた事例も報告されています。ChatGPTは継続的に学習するため、時間の経過とともにサポート品質の向上も期待できます。
FAQ作成による問い合わせ対応の効率化
ChatGPTを活用すれば、頻繁に寄せられる問い合わせ内容をもとに、網羅性の高いFAQデータベースを効率よく作成できます。既存のドキュメントや応対履歴をもとに、自動的に質問と回答をまとめられます。
ChatGPTの活用により、顧客は自己解決しやすくなり、サポート担当者への問い合わせ件数も削減できるでしょう。応用例として、顧客向けだけでなく社内向けのFAQも作成でき、情報共有の効率化にも貢献します。
人事部門
ここでは、人事部門のビジネス活用事例を3つ紹介します。
- 履歴書・職務経歴書の一次スクリーニングを自動化
- リファレンスチェックの効率化
- 社内FAQチャットボットによる問い合わせ対応の効率化
採用プロセスの効率化や従業員からの問い合わせ対応の自動化に、ChatGPTが活用できるでしょう。
履歴書・職務経歴書の一次スクリーニングを自動化
大量に届く履歴書や職務経歴書の一次スクリーニング作業は、ChatGPTによって大幅に効率化できます。求人要件と応募者のスキル情報を入力すれば、適合度の高い候補者を迅速に抽出できるでしょう。
応募書類をすべて手作業で確認する負担が減るため、面接や候補者とのコミュニケーションといった本来優先すべき業務に集中できます。ただし、個人情報を取り扱う以上、セキュリティ対策を徹底した環境での運用が欠かせません。
リファレンスチェックの効率化
採用活動の一環として実施するリファレンスチェックにおいても、ChatGPTの活用はビジネスに効果的です。エントリー者の実績や勤務状況に関する情報を入力するだけで、リスク情報の自動抽出や質問項目の自動生成が可能になります。
これまで時間がかかっていたチェック作業を短縮できるため、採用スピードの向上にもつながるでしょう。実際に、リファレンスチェックサービスへChatGPTを組み込んだAIサポート機能が導入されるケースも増えています。
社内FAQチャットボットによる問い合わせ対応の効率化
従業員から寄せられる休暇申請や給与明細、福利厚生に関する問い合わせ対応にも、ChatGPTを活用したチャットボットが効果を発揮します。基本的な質問には即時対応できるため、人事担当者の負担を軽減できるでしょう。
従業員自身が疑問点をすぐに解消できれば、業務の停滞も防げます。独自データを学習させたチャットボットを導入すれば、自社特有のルールや制度にも正確に対応できるようになります。
製品開発部門
ここでは、製品開発部門のビジネス活用事例を2つ紹介します。
- 革新的なアイデア創出
- ペルソナ設定のサポート
ChatGPTの活用で、短時間で多様なアイデアを出せるため、初期段階での選択肢拡大に役立つでしょう。
革新的なアイデア創出
新製品やサービスのアイデア出しには、ChatGPTが有効です。特定のテーマやターゲット層、解決したい課題を指定すれば、多様な視点から短時間でアイデアを提案してくれます。
人間同士のブレインストーミングに取り入れれば、発想の幅を広げるきっかけになるでしょう。開発初期段階で幅広い選択肢を持てば、イノベーションを加速させる効果が期待できます。
ペルソナ設定のサポート
ターゲットユーザーを具体的にイメージするためのペルソナ設定でも、ChatGPTは役立ちます。製品やサービスの特徴、想定する利用者層を伝えるだけで、多様なペルソナを素早く生成できるでしょう。
作成したペルソナは、開発チーム内での顧客理解を深め、よりニーズに沿った設計につなげられます。設定作業にかかる時間を短縮すれば、製品の市場適合性の向上にも貢献できるはずです。
法務部門
ここでは、法務部門のビジネス活用事例を2つ紹介します。
- 契約書チェックの効率化
- コンプライアンス教育用のコンテンツ作成サポート
煩雑な書類業務をChatGPTで効率化すれば、法務担当者は戦略的リスク管理や企業ガバナンスの強化に集中できるでしょう。
契約書チェックの効率化
大量の契約書を扱う場面では、ChatGPTによる一次レビューが有効です。契約書の内容を分析し、非標準的な条項や重要な期日、金額条件などを自動抽出してくれます。
リスクが高い条項を指摘する設定も可能なため、レビュー作業の精度とスピードを同時に高められるでしょう。一次レビュー後に人間が精査すれば、ミスを防ぎつつ作業時間を短縮できます。
コンプライアンス教育用のコンテンツ作成サポート
従業員向けのコンプライアンス教育教材を作成する際にも、ChatGPTは頼りになります。業界特有の法令遵守事項に関する説明資料や、ケーススタディ、シナリオベースの問題集などを短時間で作成できるでしょう。
加えて、理解度を測るためのクイズやテスト問題も自動生成できます。さまざまな資料を活用し、コンプライアンス関連のFAQチャットボットを構築すれば、従業員の自己解決率も高まります。
IT部門
ここでは、IT部門のビジネス活用事例を2つ紹介します。
- プログラミングコード作成の補助
- コードのバグチェックや修正案の作成
プログラム開発プロセス全体の効率化に、ChatGPTが役立つでしょう。
プログラミングコード作成の補助
ChatGPTは、特定のプログラミング言語や機能要件に合わせてコードを作成する支援が可能です。設計意図や要件を具体的に伝えれば、コードのたたき台をすばやく用意してくれるでしょう。
ChatGPTの活用により、開発スピードが向上し、リソースの最適化にもつながります。非エンジニアが簡単なツール開発に取り組む場面でも、強力なサポート役となるでしょう。
コードのバグチェックや修正案の作成
プログラム開発中に発生したエラーや不具合に対しても、ChatGPTは効果的なアシスタントになります。エラー内容を入力すれば、原因の推測や修正方針をアドバイスしてくれるでしょう。
デバッグ作業の効率が上がるため、開発スケジュールの遅延リスクも低減できます。ただし、最終的なコード品質の保証は人間が責任を持つ必要があります。
経営企画部門
ここでは、経営企画部門のビジネス活用事例を2つ紹介します。
- 市場分析の迅速化
- 経営会議の効率化
煩雑な情報収集作業をChatGPTで効率化すれば、経営層の迅速な意思決定をサポートできるでしょう。
市場分析の迅速化
市場や競合に関するリサーチ業務では、ChatGPTの力が発揮されます。Web上の最新情報を集め、翻訳や要約まで一貫して対応できるため、必要なデータを素早く整理できます。
ChatGPTの活用により、市場の動向や競争環境を迅速に把握し、経営戦略の立案に役立てられるでしょう。情報収集の効率化は、もはや競争力強化に欠かせない要素になりつつあります。
経営会議の効率化
経営会議の準備においても、ChatGPTは大きな助けとなります。議題に沿った説明資料の構成案を作成したり、膨大なレポートや議事録の要点を分かりやすくまとめたりできます。
会議の事前準備にかかる時間を大幅に短縮できるため、参加者は議論そのものに集中できるでしょう。正確な指示を与えれば、より精度の高い資料作成も可能です。
ChatGPTビジネスプランの選び方

ここでは、ChatGPTビジネスプランの選び方について解説します。
- ChatGPT各プランの料金表
- API連携によるシステム構築
それぞれ詳しく見ていきましょう。
ChatGPT各プランの料金表
ChatGPTには、ビジネス活用を視野に入れた複数の利用プランが用意されています。まず、無料で使えるプランは主に個人利用を想定した内容です。日常会話や文章作成、翻訳といった基本的な用途であれば、無料プランでも十分に活用できるでしょう。
ChatGPTをどのように使えるか試してみたい場合には、無料プランから始めるのがおすすめです。
個人でビジネス活用を積極的に進めたい場合は、有料版のChatGPT Plusが候補に挙がります。無料版と比べて応答の精度や速度が向上しており、資料の読み取りやデータ分析など、より幅広い用途に対応できるでしょう。
チームや組織で利用する場合には、ChatGPT Teamプランが適しています。メンバー全員で共有できるワークスペースが提供され、カスタマイズしたAIチャットボットを活用できるようになります。料金も比較的抑えられているため、中小企業やスタートアップにとって使いやすい選択肢といえるでしょう。
大量の機密情報や個人情報を扱い、かつ複雑な業務をする大企業には、ChatGPT Enterpriseが推奨されています。セキュリティ対策や性能面、カスタマイズ性が大幅に強化されているため、組織の要件に柔軟に対応できるでしょう。
| プラン名 | 主な特徴 | 料金(目安) |
|---|---|---|
| 無料版 | 個人利用向け。日常会話・文章作成・翻訳など基本機能が利用可能 | 無料 |
| ChatGPT Plus | 応答精度・速度向上。資料読み取りやデータ分析など多用途に対応 | 月額20ドル程度 |
| ChatGPT Team | チーム用ワークスペース。カスタマイズ可能なAIチャットボットを全員で共有 | 1ユーザーあたり月額25ドル程度 |
| ChatGPT Enterprise | セキュリティ強化、カスタマイズ性向上、大企業向け高性能プラン | 要問い合わせ(カスタム対応) |
ChatGPT Enterpriseに関しては以下の記事でも解説しているので、ぜひ参考にしてみて下さい。

API連携によるシステム構築
開発者向けのAPIを利用すれば、既存システムや独自プログラムと連携させられ、より高度な活用や新しいサービス構築が可能になります。独自データを学習させたチャットボットを開発し、社内の専門知識をリアルタイムで共有したり、業務支援に役立てたりできるでしょう。
APIを利用したシステム構築は、情報漏泄リスクへの対策を取りやすいというメリットもあります。一方、APIの導入には高度な技術力が求められます。社内にエンジニア人材がいる企業や、開発系企業にとっては特に魅力的な選択肢となるでしょう。
API利用は従量課金制のため、事前にコスト計算をしておくのがポイントです。自社の技術力や目的に合わせて、API連携によるシステム構築を前向きに検討してみてはいかがでしょうか。
APIに関しては以下の記事でも解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

企業がChatGPTのビジネス活用を成功させる5つの戦略
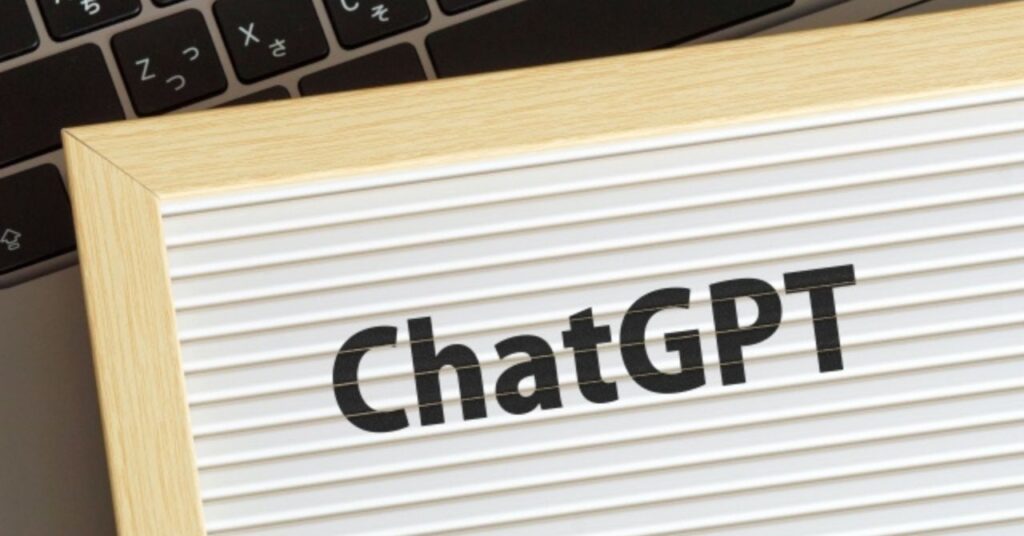
ここでは、企業がChatGPTのビジネス活用を成功させる戦略を5つ紹介します。
- 業務の棚卸しをしてAI活用による効果を試算する
- 費用対効果の高い業務課題と活用方法を見極める
- アジャイル型でスピーディーに導入・検証する
- ガイドライン策定によりリスクを管理する
- 社内研修などを通じて社員のAI活用スキルを高める
それぞれ詳しく見ていきましょう。
業務の棚卸しをしてAI活用による効果を試算する
ChatGPTを活用してビジネスを効率化するには、まず自社の業務内容やプロセスを正確に把握することが欠かせません。やみくもにツールを導入しても、期待した成果を得るのは難しいでしょう。
どの業務にAIを適用すれば、どれだけ業務効率が向上し、生産性向上につながるのかを具体的に試算しておくのがポイントです。試算作業は、AI投資に対するリターンを明確にするうえで欠かせないプロセスといえるでしょう。
ChatGPT活用の成否は、ツールの特性を活かせる効果が期待できる業務に導入できるかどうかに左右されるため、業務の棚卸しを丁寧に行い、AI活用のポテンシャルが高い領域を見極めていきましょう。
費用対効果の高い業務課題と活用方法を見極める
ChatGPTは非常に多機能ですが、すべての業務に万能とはいえません。たとえば、大量のデータに基づいたコンテンツ作成は得意である一方、複雑な問いに対する正確な回答は苦手とする傾向があります。
つまり、自社の業務現状とChatGPTの特性を十分に理解したうえで「どの課題に対して、どのように活用すれば最も効果的か」を慎重に見極める必要があるでしょう。この判断を誤らなければ、投資対効果を最大化し、事業価値を高める活用法を見つけ出せるはずです。
急ぎすぎた導入による失敗を防ぐためにも、適切なAI活用領域を見極めるステップを大切にしていきましょう。
アジャイル型でスピーディーに導入・検証する
AI技術は日々進化しているため、ChatGPTの導入も一度開発すれば完了ではありません。初期段階では簡易的なプロトタイプを素早く構築し、実際の業務に組み込みながら検証と改善を繰り返す「アジャイル開発」の考え方が効果的でしょう。
短いサイクルで試行錯誤を重ねれば、自社によりフィットした使い方を見つけやすくなります。コストを抑えつつ効果を検証できるこの手法は、導入リスクを管理しながらスピーディーな展開を可能にします。変化に柔軟に対応し、競争に遅れを取らないためにも、アジャイル型で導入・検証を進めてみてください。
ガイドライン策定によりリスクを管理する
企業がChatGPT活用に慎重になる大きな要因の一つが、機密情報の漏洩や著作権侵害リスクへの懸念です。社員が無秩序に一般的なChatGPTを利用すれば、重要な情報が意図せず外部に漏れるリスクも否定できません。
機密情報の漏洩や著作権侵害のリスクを最小限に抑えるには、システム面と運用ルール面の双方でしっかり対策しましょう。たとえば、API連携によって入力データが学習対象にならないようにする設定や、機密情報の取り扱いに関する明確なガイドライン策定が効果的です。
仕組みを整え、セキュリティを確保しながら安心して業務活用できる環境を整えましょう。
社内研修などを通じて社員のAI活用スキルを高める
ChatGPTのような対話型AIは、ユーザーが与える指示の質によって出力結果が大きく左右されます。つまり、従業員一人ひとりのAI活用スキルが、ツールから引き出せる価値に直結するといえるでしょう。
社員がChatGPTの基本的な仕組みや適切な使い方、リスク管理のポイントを正しく理解することが欠かせません。社内研修や実践的なトレーニングを通じて、AIリテラシーを段階的に高めていきましょう。
AIリテラシーを高めれば、AIを単なる代替手段ではなく、能力を拡張するパートナーとして活用し、組織全体の生産性向上と競争力強化を実現できるはずです。
ビジネスでChatGPTを活用する際の注意点
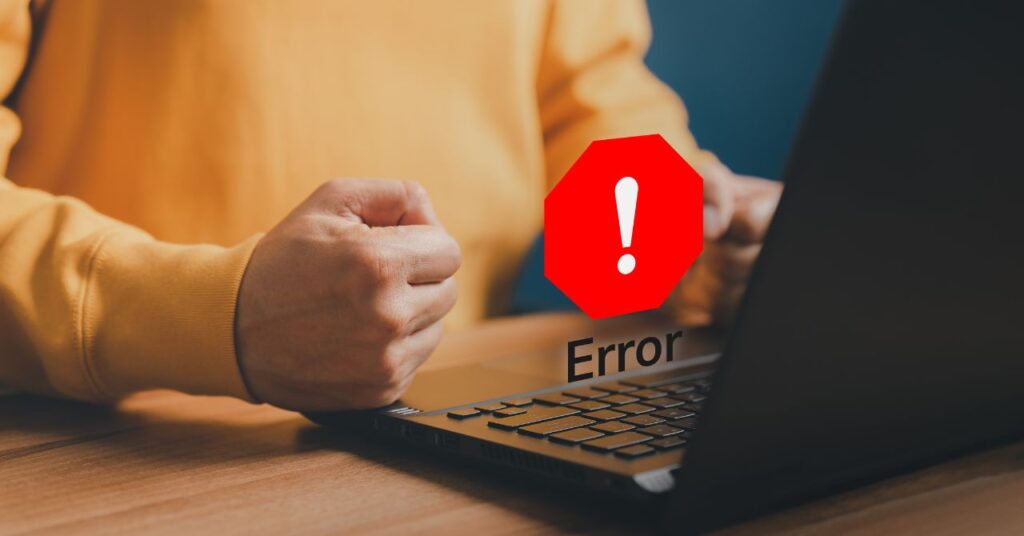
ここでは、ビジネスでChatGPTを活用する際の注意点を5つ紹介します。
- サービスの不具合なども想定して使う
- 言葉のニュアンス理解は不十分だと認識しておく
- プロンプト次第で生成結果は大きく変わる
- 機密情報は扱わないようにする
- 最終的な判断はきちんと人の目でする
それぞれ詳しく見ていきましょう。
サービスの不具合なども想定して使う
ChatGPTはWebサービスとして提供されているため、アクセス集中などによって出力が遅くなったり、動作が停止したりするリスクが伴います。ChatGPTの活用を業務に組み込む際は、万が一ChatGPTが使えなくなった場合にも、業務が進められるスケジュール設計を心がける必要があります。
RPAや他の自動化ツールと同様に、予期せぬ停止時の復旧フローや代替手段を事前に整備しておく必要があります。業務停止リスクを最小限に抑えるためにも、利用環境の安定性に注意を払いましょう。
言葉のニュアンス理解は不十分だと認識しておく
ChatGPTは、膨大なデータセットに基づき単語間の確率的なつながりをもとに文章を生成しています。ただし、単語の意味やニュアンスを人間のように深く理解しているわけではありません。
気の利いた回答ができるように見える最新モデルであっても、人間であれば当たり前に答えられる質問を誤るケースが少なくありません。出力された回答は確率的に導き出された結果にすぎない点を理解したうえで、慎重にChatGPTを利用する姿勢が求められるでしょう。
プロンプト次第で生成結果は大きく変わる
ChatGPTの出力精度や質は、ユーザーが入力するプロンプト(指示文)の内容によって大きく左右されます。求めるアウトプットを引き出すためには、プロンプトの工夫や研究が欠かせません。
ターゲット、文字数、期待する出力形式などを具体的に指定すれば、ChatGPTの性能を最大限に引き出しやすくなるでしょう。多忙な場合でも、あらかじめ最適化されたプロンプト(たとえば深津式プロンプトやReActプロンプト)を活用するのは、有効なアプローチといえます。
機密情報は扱わないようにする
ChatGPTを業務に活用する際には、機密情報や個人情報の取り扱いに特に注意しなければなりません。一般公開されているChatGPTでは、入力したデータがAIの学習対象に使用される可能性があるためです。
AIの学習対象に使用されるリスクを低減するためには、入力データが学習されない設定をするか、利用範囲を明確に定めた運用ルールの策定が欠かせません。API連携型ツールや、ChatGPT Enterpriseなどの企業向けプランを利用すれば、情報漏洩リスクを抑えた運用が可能になります。自社のセキュリティ要件に合った方法を選択しましょう。
最終的な判断はきちんと人の目でする
ChatGPTは広範な知識に基づき多様な質問に回答できる反面、誤った情報を出力するリスクもあります。最新情報や固有名詞に関しては、知識が不正確である可能性が高いでしょう。
生成された内容をそのまま鵜呑みにせず、必ず人間がファクトチェックや校正をして、最終的な判断を下すのが不可欠です。著作権侵害リスクにも配慮し、出力された文章に問題がないかを慎重に確認しましょう。
大手企業におけるChatGPTのビジネス活用事例5選
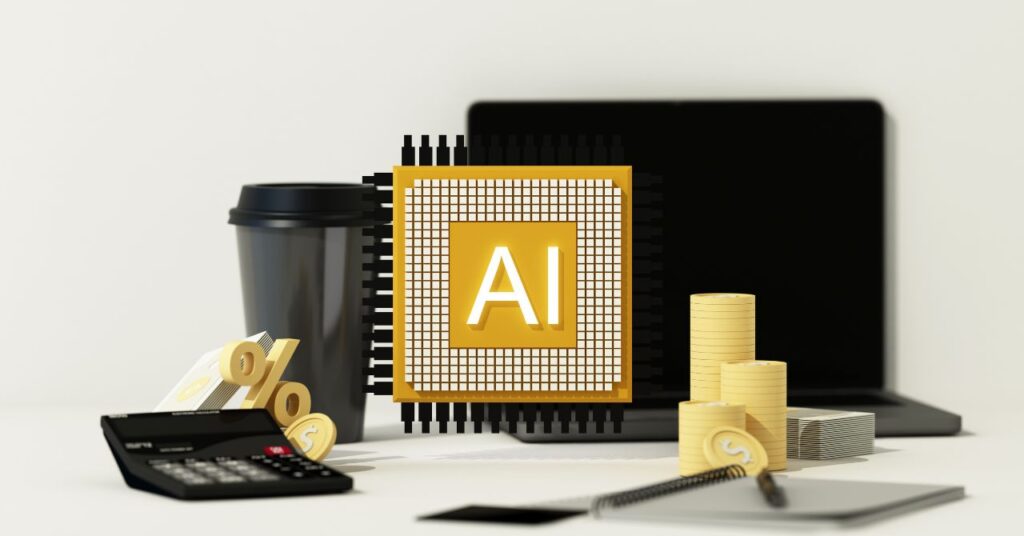
最後に、大手企業におけるChatGPTのビジネス活用事例を5つ紹介します。
- SMBCグループ
- SUNTORY
- 三菱UFJ銀行
- パナソニック コネクト
- サイバーエージェント
それぞれ詳しく見ていきましょう。
SMBCグループ
SMBCグループでは、大手銀行グループとしていち早く、従業員専用AIアシスタント「SMBC-GAI」を開発し、業務に活用しています。このツールはMicrosoftのAzure基盤上にAzure OpenAI Serviceと連携して構築されており、セキュアな環境で利用できる点が特徴です。
行員はTeamsに組み込まれたAIアシスタントを通じて、専門用語の検索、メールや文章の下書き作成、資料の要約、翻訳、プログラミングコードの生成など、多様な業務を効率化しています。開発自体はわずか数日で行われ、残りの期間をルール整備に充てるなど、アジャイルなアプローチで推進されました。
リリース後は利用が順調に拡大し、現在では1日あたり約12,000件、約2秒に1回のペースで活用されています。今後は、社内規程の検索やコールセンター業務支援、通話記録作業の自動化なども視野に入れているといいます。
参考元: [SMBCグループが独自に生み出したAIアシスタント「SMBC-GAI」開発秘話|三井住友フィナンシャルグループ]
SUNTORY
Suntory Wellnessでは、顧客応対業務の効率化を目指して、ChatGPTを活用した対話要約の自動化に取り組んでいます。コンタクトセンターでは、通話内容を要約してシステムに登録する作業に時間がかかるうえ、オペレーターによって要約の粒度が異なったり、重要な情報が抜け落ちたりする課題がありました。
課題を解決するため、通話を音声認識でテキスト化し、そのテキストからプロンプトを生成、ChatGPTで要約する自動化フローのPoC(概念実証)を進めています。サントリーシステムテクノロジー、コンタクトセンター、DX推進部が連携し、内製体制で取り組んでいます。
PoCを通じて、コスト試算の重要性や要約目的の抽象化・言語化が必要であるケースなど、多くの学びが得られました。
参考元: [【顧客応対業務効率化】お客様との対話要約をChatGPTで自動化する | Suntory Wellness TechBlog]
三菱UFJ銀行
三菱UFJフィナンシャル・グループも、独自のMUFG版「ChatGPT」開発を進めています。このシステムはMicrosoft Azure基盤上に構築されており、一般公開版ChatGPTのように入力データがOpenAI社の学習に使われる心配がなく、セキュアな利用が可能です。
開発プロセスは通常とは異なり、役員レベルの支援を受けながら、異例のスピード感で推進されました。同行では、稟議書作成の補助、金融レポート要約、社内手続き照会など、110以上のユースケースを想定しています。
プロジェクト推進における強みは、行員全体の情報セキュリティ意識の高さにあり、リスク対応をスムーズに進められました。今後は、年内に全行員が利用できる環境を整備し、効果的な活用を促すためのガイドライン策定にも取り組む予定です。
参考元: [MUFG版「ChatGPT」の開発秘話に迫る|三菱UFJフィナンシャル・グループ]
パナソニック コネクト
パナソニック コネクトでは、自社向けAIアシスタント「ConnectAI」を国内全社員約12,400人に展開し、導入から1年で労働時間を合計18.6万時間削減する成果を上げました。活用範囲は、検索エンジン代替から戦略策定、商品企画といった高度な領域まで広がっており、製造業特有の事例も増加しています。
情報漏洩や著作権侵害といった問題は発生しておらず、シャドーAI利用リスクの低減にもつながっています。また、自社独自の公開情報や社外秘データを参照できる特化型AIの実用化も開始しており、特に品質管理分野での効果が確認されています。
今後は、自社データ整備を進め、AIが自律的に業務遂行する「オートノマスエンタープライズ」実現に向けた取り組みも強化する方針です。
サイバーエージェント
サイバーエージェントは、インターネット広告事業本部内に「ChatGPTオペレーション変革室」を設立し、デジタル広告運用に関わるオペレーション作業の抜本的な削減を目指しています。OpenAI社が提供するChatGPTを安全かつ適切に活用し、まずは社内コミュニケーション補助を中心に作業時間の効率化を推進しています。
月間約23万時間に及ぶ広告オペレーションの30%、約7万時間の削減を目標に掲げており、セキュリティには最大限の配慮を施しています。API連携のみを利用し、顧客情報を含まない形で運用し、品質向上や広告効果改善にもつなげていく計画です。
ChatGPTのビジネス活用事例を参考に自社でも業務効率化しよう

本記事では、ChatGPTのビジネス活用事例に加え、注意点や成功のポイントも解説しました。大手企業の取り組みが示すように、ChatGPTはさまざまな業務の効率化に大きく貢献できます。
ただし、情報の正確性やセキュリティへの配慮は不可欠です。リスクを管理し、社員のリテラシー向上にも取り組めば、ChatGPTは心強いビジネスパートナーとなるでしょう。
【ChatGPTを活用してビジネスを効率化するために】
- 自社業務に活かせる活用領域を見つける
- 大手企業の事例から導入イメージを具体化する
- 成功のポイントとリスク管理策を押さえて実行する
ぜひ本記事の内容を参考に、自社でのChatGPTのビジネス活用を検討してみてください。












