人手不足が深刻になっている現在、社内の業務を効率化したいと考える方も多いでしょう。
とくに、文章作成や市場リサーチ、社内の問い合わせを効率化するためには「ChatGPT Team Plan(チームプラン)」がおすすめです。
【記事を読んで得られること】
- ChatGPTチームプランの特徴
- ChatGPTチームプランの登録方法
- ChatGPTチームプランの活用事例
ChatGPTチームプランの特徴や登録方法などを詳しく解説するので、日々の業務に追われている方は、本記事を参考にしてください。
ChatGPTのTeam Plan(チームプラン)とは?対応人数は?

ChatGPTのチームプランは、多人数での活用を想定した有料プランです。管理や権限設定がまとめてできるため、個人版と比べて共同作業が円滑になります。
チームで利用する前提のプランなので、複数人が同時にアクセスしても速度が落ちにくく、ストレスなく業務をこなせるでしょう。
ChatGPTのチームプランに対応する人数は、2人から149人までです。支払い形態は利用者数ごとの月額・年額で設定され、組織の規模に応じて柔軟に利用できます。
無料版やChatGPT Plusと違い、チーム全員が同じワークスペースを共有できるので、ナレッジを一元化しながら議事録作成やアイデア検討などを効率化できます。
ChatGPTのチームプランとその他有料プランとの違い

ChatGPTのどのプランに加入したらいいかわからない方のために、以下のプランを比較します。
- チームプランとChatGPT Plusとの違い
- チームプランとChatGPT Proとの違い
- チームプランとChatGPT Enterpriseとの違い
それぞれのプランの特徴を把握し、最適なプランに加入しましょう。
チームプランとChatGPT Plusとの違い
ChatGPT Plusは、月額20ドルで提供されている個人ユーザー向けの有料プランです。チームプランには共同ワークスペースが用意されますが、Plusにはありません。
Plusを選んだ場合、ユーザーがそれぞれ個別にChatGPTと契約してAIを利用します。Plusの場合、メンバーが増えるほど社内での請求管理が複雑になるのが難点です。
さらに、チームプランならメンバー追加や削除、権限設定も一括でできます。共同作業に必要な会話やファイルをワークスペース内に集約できるため、スムーズに情報共有が可能です。
チームプランとChatGPT Proとの違い
ChatGPT Proは、月額200ドルで提供されている個人ユーザー向けの最上位プランです。
Proでは個人が高度なo1 Pro modeを使えますが、チームプランではo1 Pro modeは利用できません。
Proはワークスペースを共有できず、個人の裁量に依存する領域が多々ありました。一方、チームプランは「オーナー」「管理者」「メンバー」などの役割を割り当てて共同で運用できます。
一般社員には閲覧やメッセージ送信のみの権限を設定し、管理者だけがメンバー追加や分析などを行えるようにする方法もあります。
チームプランとChatGPT Enterpriseとの違い
チームプランとChatGPT Enterpriseは、どちらも法人利用を想定した有料プランですが、用途と機能には明確な違いがあります。
チームプランは中小規模の企業やプロジェクトチーム向けで、導入コストを抑えつつ、共同作業や権限管理を実現できます。
一方、Enterpriseは大企業や高いセキュリティ要件を求める組織向けに設計されており、SSO(1回の認証で複数のアプリケーションやサービスにログインできる仕組み)対応、専用インフラの提供、カスタマーサポートの優先対応など、チームプランの機能が大幅に強化されています。
チームプランは、必要最小限の管理機能とセキュリティを備えながら、比較的低価格で利用できるのが強みです。
まずはチームプランでAIを試し、人数や機能面の必要に応じてEnterpriseへの移行を検討しましょう。
ChatGPTチームプランの5つの特徴

ChatGPTチームプランには、以下のような特徴があります。
- チームでの共同作業ができる
- GPTsを利用できる
- 回数制限が緩和される
- 送ったデータが学習に利用されない
- 新機能と改善への早期アクセス権がある
使用したデータが学習に利用されないので、情報漏洩を懸念している企業におすすめのプランです。
チームでの共同作業ができる
ChatGPTチームプランは、メンバー全員が同じチャット画面を共有できるのが大きなメリットです。
例えば、誰かが入力したメッセージを別のメンバーが参照し、必要に応じて提案書や企画書の追加提案を生成できます。
全員が共通のAIモデルへアクセスするため、バージョンの違いで品質にムラが生じる心配がありません。
さらに、ブログ記事の執筆や修正なども、ChatGPTがサポートしてくれます。会議の内容を要約するときにも、チーム全員が同じ要約文をリアルタイムで見られるため、意思疎通が早くなります。
ファイルのやり取りも管理者が制限可能なので、機密性の高い情報を扱う場面でも安心です。
GPTsを利用できる
チームプランでは最新のGPT-4oモデルやo3シリーズなどを利用できます。
例えば、文章の生成や要約には4oを使い、コードの生成や分析にはo3シリーズを使うのが効果的です。
また、すでにプロンプトが組み込まれているGPTsを活用すると、会議資料の作成やメール下書きの作成などを効率化できるため、重要なタスクに集中できます。
チーム内で作成したプロンプトやAIの回答例はいつでも閲覧できるので、AI活用のノウハウを蓄積可能です。チームプランを活用すると、個々のアイデアが埋もれず、組織全体で知見や成果を共有しやすくなります。
回数制限が緩和される
無料版や個人向けプランでは、GPT-4やGPT-4oへの問い合わせ回数やトークン数に制限があります。
チームプランは、無料版やPlusと比べると、利用可能枠が十分に確保されます。
| モデル | GPT-4 | GPT-4o |
|---|---|---|
| 無料版 | 選択不可 | 5時間10回 |
| ChatGPT Plus | 3時間40回 | 3時間80回 |
| ChatGPT Pro | 無制限 | 無制限 |
| ChatGPT チームプラン | Plus以上(回数非公開) | Plus以上(回数非公開) |
| ChatGPT Enterprise | 無制限 | 無制限 |
営業資料や内部文書などの大規模テキストを扱う場合、回数制限があると作業が止まる可能性がありますが、チームプランならその懸念を減らせます。
文字数が多い原稿の校正やプログラムコードのレビューなども、文字数を気にせず連続してリクエストを送信できます。
実務で積極的にChatGPTを活用する際は、回数制限が緩いチームプランがおすすめです。
送ったデータが学習に利用されない
チームプランの強みは、やり取りした情報がモデルの学習に使われないことです。顧客名や社内文書などの機密情報を送信しても、外部に漏れないので安心して使用できます。
機密性の高い文書を共有するときも、メンバー以外はアクセスできません。重要な競合情報や顧客データを扱う企業にとって、情報漏洩のリスクがないのは重要な要素です。
個人プランの場合、学習に使用されないように設定しない限り、送った情報が学習用データに取り込まれる可能性があります。
ChatGPTのチームプランは、コンプライアンス上の懸念を減らしながらAIを活用できる仕組みとして評価されています。
新機能と改善への早期アクセス権がある
チームプランでは新機能や改善がリリースされた際に優先的なアクセス権が提供されています。
個人プランより先に新しいモデルの試験運用が可能となるケースもあり、事前に社内でテストを実施して適用範囲を検討できます。
生成AIのトレンドを素早くキャッチしたい企業にとって、早期アクセスはメリットの1つです。
最新のGPTエンジンや画像生成機能などに触れやすくなるため、サービス開発やマーケティング施策もスピード感を持って取り組めます。
リリース直後の機能に不具合があった場合でも、チームプラン利用者としてサポートを受けやすい点もメリットであり、AI技術の進化スピードが速い現在、企業として新機能へいち早く対応する意義は大きくなっています。
ChatGPTチームプランの料金
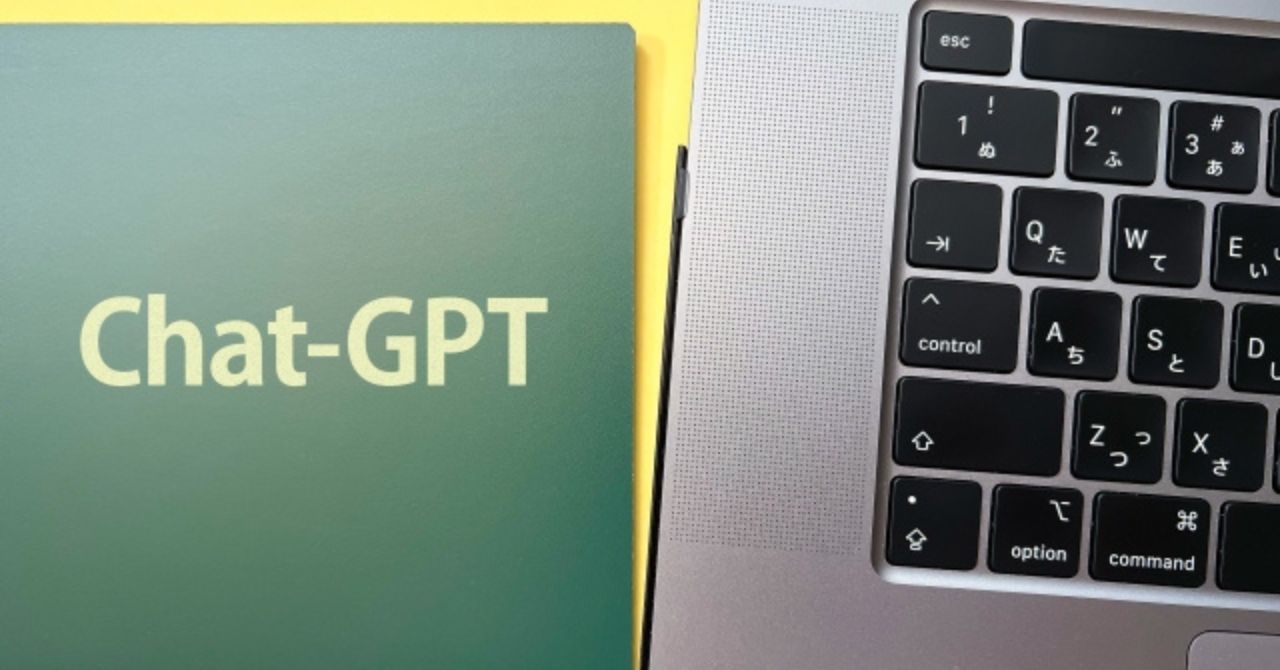
ChatGPTチームプランの料金は、ユーザー数と契約期間によって変動します。
- 月額課金:30ドル/1ユーザー
- 年額課金:1ヵ月25ドル/1ユーザー
チームプランの料金体系は、「メンバー数×定額」で算出される方式です。初期費用は不要なので、導入コストを抑えながら生成AIを試したい企業にもおすすめです。
複数名が同時にGPT-4へアクセスしても速度が落ちにくく、追加料金が発生しづらい仕組みになっています。しかし、API呼び出しなどの拡張的な利用は別途費用がかかるので注意しましょう。
ChatGPTチームプランの始め方

最初にCahtGPTの公式サイトへアクセスして「新規登録」からアカウントを作成します。
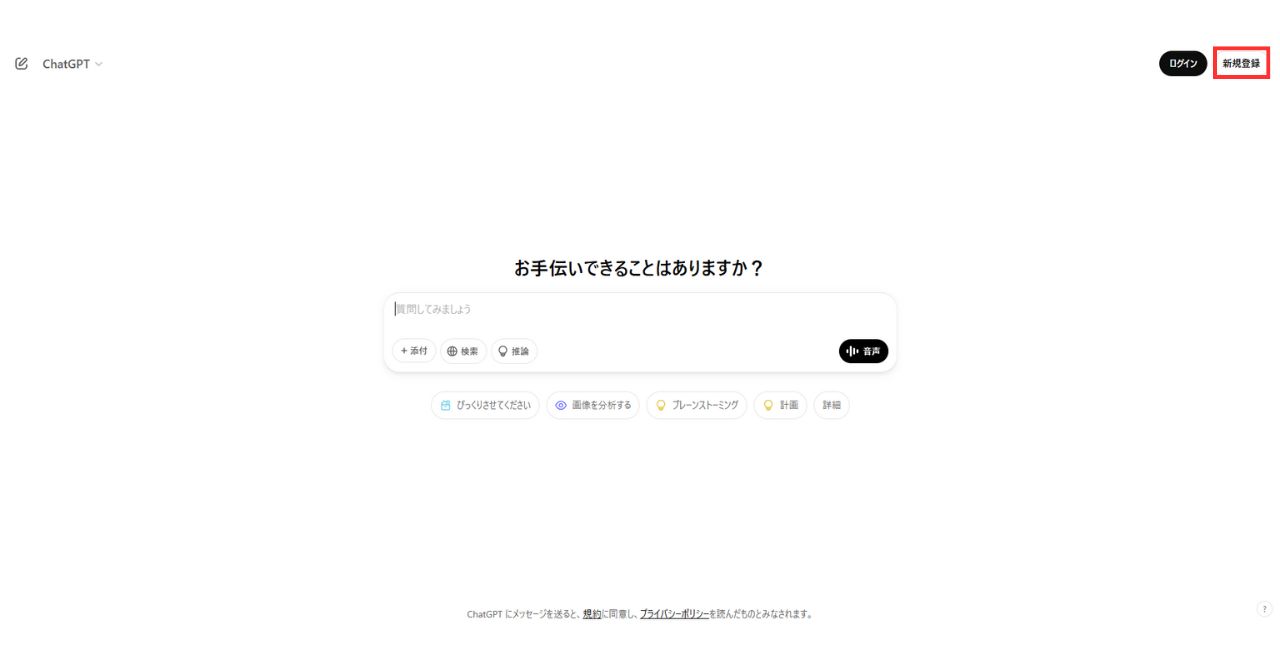
クレジットカードを登録し、支払いプランを選択します。
支払いサイクルには月額か年額を選択してください。年額プランのほうが1カ月あたりの料金が安くなります。
アカウントを作成したら「ワークスペース追加」からチームのワークスペースを新規作成し、メンバーを招待します。
メンバーにはオーナー・管理者・一般ユーザーなどの権限を割り当てるため、ユーザー個別の設定が不要です。
招待されたユーザーはワークスペースにログインし、チャット画面で業務を開始できます。
企業がChatGPTチームプランを利用する3つのメリット

企業がChatGPTチームプランを利用すると、以下のようなメリットを得られます。
- チームの業務を効率化できる
- コスト管理しやすい
- ChatGPT4o・o3‑mini・o3‑mini‑high・o1を利用できる
なぜチームプランに加入すると業務を効率化できるのか、それぞれ解説します。
チームの業務を効率化できる
一括でChatGPTを管理できる仕組みが整うと、雑多な手続きやチーム内での重複作業が減ります。
個人プランだと社員ごとにアカウント管理が必要になりますが、チームプランは請求やメンバー追加がひとつのアカウントで管理できます。
また、共有ワークスペースに投稿した内容を他のメンバーがすぐ確認できるため、会議前の下調べや社内報告の作成も容易です。
会議の議事録作成をChatGPTに任せて担当者が最終チェックする形にすると、担当者の負担が軽減できます。
管理面でも統制が取りやすく、誰がいつどのようなチャットを使っているのかを管理者が把握できるのもメリットの1つです。
コスト管理しやすい
ChatGPTチームプランは、月額や年額での支払い金額になっているため、予算を立てやすいのがメリットです。
個人アカウントの集合体では、利用人数が増えるほど請求が分散してしまいますが、チームプランだと一括契約になるので管理者が全体コストを一括で把握できます。
新しく部署が発足した場合や新しいスタッフが入社した際も、容易に人数を調整可能であり、請求書の発行や決済方法も企業向けに最適化されているため、経理担当者の手間を低減できます。
ChatGPT4o・o3‑mini・o3‑mini‑high・o1を利用できる
推論に特化したoシリーズやGPTsが利用範囲に含まれるのが、チームプランのメリットです。タスクに応じて最適なモデルで業務を効率化できます。
例えば、「o3‑mini」は軽めの計算や素早い要約に向いている一方、「o3‑mini‑high」は情報量が多い場面や、より高度な分析に適しています。
経営企画部は詳細レポート作成のため「o3‑mini‑high」を使い、サポート部門は日々の問い合わせ回答に「4o」を選択可能です。
チームプランでは管理画面を介してメンバーごとの使用状況をモニタリングしやすいため、必要に応じてモデルの切り替え方針を統一できます。
ChatGPTチームプランの活用方法
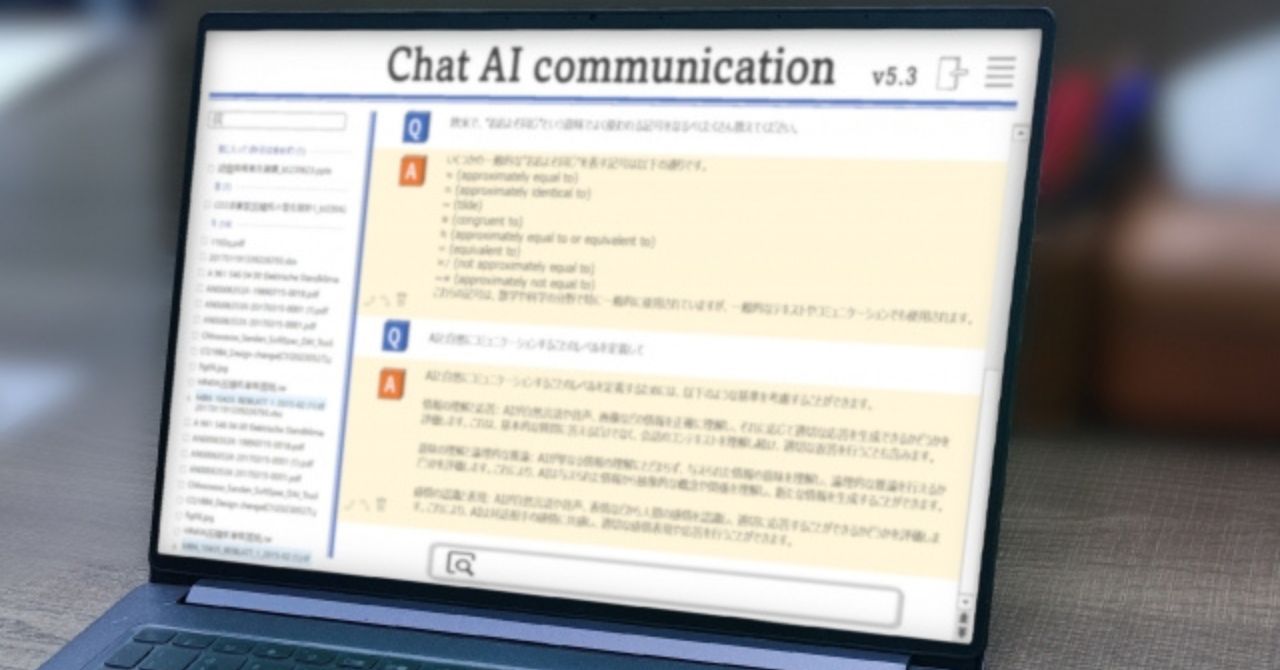
ChatGPTチームプランは、以下のような場面で活用できます。
- 議事録作成
- 社内FAQと問い合わせ対応の内製化
- マーケット調査とレポート作成
どのように業務を効率化できるか、それぞれの事例を解説します。
議事録作成
議事録作成は、以下の手順で行います。
- 会議内容を録音する
- 音声を文字起こしする
- ChatGPTに入力する
- 見直しと修正を行う
- 議事録を共有する
議事録を作成すると会議に参加していないメンバーが内容を把握しやすくなるため、後のコミュニケーションも円滑になり、会議数が多い企業や部署ほど、ChatGPTで議事録が作れるとチーム全体の業務を効率化できます。
社内FAQと問い合わせ対応の内製化
社内FAQと問い合わせ対応の内製化は、以下の手順で行います。
- 自社の規定やシステムに関する情報収集
- ChatGPTでFAQ形式にまとめる
- 新人や他部署からの問い合わせをChatGPTI対応する
- 回答に誤りがあれば修正する
管理者が社内マニュアルやよくある質問をChatGPTに入力すると、新人や他部署からの問い合わせに自動で返信できるようになります。
サポート担当者が手動で返答していた社内FAQや外部からの問い合わせを大幅に短縮し、本来の重要業務に集中できるでしょう。
マーケット調査とレポート作成
マーケット調査とレポート作成も、ChatGPTで効率化できます。
- 新規事業の検討や新製品リリース時に市場レポートや競合情報を収集する
- 収集した情報をChatGPTに入力して要約や分析を行う
- 担当者ごとに分担して収集した情報を整理する
- 整理した情報をチームのワークスペースで共有する
- 最終的なレポートをChatGPTにまとめる
チームプランなら、複数メンバーが並行して市場レポートや競合情報をChatGPTに要約させながら分析を進められます。
また、担当者Aが海外ニュースサイトの記事を読み込ませ、担当者Bが国内レポートを入力するように分担すれば、効率的に多面的なデータを整理できます。
チームでChatGPTを使いこなすための5つのポイント

チームでChatGPTを使いこなすためには、以下のポイントを押さえましょう。
- ChatGPTに役柄を指定する
- 数字や固有名詞を使って具体的に指示をする
- 質問の背景や文脈を伝える
- 回答の参考になる情報や自社データを共有する
- 何度も修正して理想の回答を得る
指示の出し方がわからないという方は、それぞれのポイントを参考にしてください。
ChatGPTに役柄を指定する
ChatGPTが生成する文章の語調や切り口は、指示の仕方によって大きく変わります。
「あなたはマーケティング部の分析担当者です。」「あなたはベテランのライターです。」など具体的に役柄を示すと、役柄に合わせた文章や深掘りを期待できます。
会議レポートを作成する際は、「プロジェクトマネージャー目線でまとめて」という要望も効果的であり、役柄を決めると応答の文体や方向性が変化し、チーム内で複数パターンの案を比較できます。
チームプランのワークスペースなら、チームメンバーが作成したプロンプトテンプレートを共有でき、ほかのメンバーの作業も効率化するでしょう。
数字や固有名詞を使って具体的に指示をする
曖昧な質問を投げると、ランダム要素が増えて生成結果が意図しないものになりやすくなります。
必要な情報を得るには「製品Aの売上目標は年末までに10%増加させたい。現状データは昨年度の月平均300万円。どのようなキャンペーンが適切か、3案考えてください」のように明確な数値や対象名を提示しましょう。
数値にもとづいて、ChatGPTが具体的な提案をまとめてくれます。特に売上や利用者数のデータ、日付、具体的な商品名などを盛り込むと回答の精度が上がります。
ただし、機密性の高い数値や個人情報を入力するのは避けるのが無難です。チームプランはデータを学習に使用されない設定ではあるものの、社内ルールを決めてリスクマネジメントを徹底してください。
質問の背景や文脈を伝える
ChatGPTは、文脈を理解したほうが適切な回答を生成しやすいです。
「今、海外進出を視野に入れているが市場リサーチの初期段階なので広く情報を集めたい」など背景を伝えると、総括的な情報を提示してくれます。
チームで使う際も、誰かがその背景を省いたまま質問すると、求めていた情報と方向がズレる可能性があるので注意しましょう。
ワークスペース内のチャットには前のやり取りも残るため、どんな議論をしてきたかを把握し、新規でチャットを立ち上げるか追加質問するか判断するのが効果的です。
目的の回答を得るためには、ChatGPTに簡潔かつ要点を絞った背景説明を共有しましょう。
回答の参考になる情報や自社データを共有する
「競合他社の製品一覧」「先月の集計レポート」など、手元にある資料を提示すると回答の精度を高められます。
チームプランでは、この資料をワークスペース内で共有し、誰でも出力結果に反映でき、手入力で長い文章をコピーするより、まとめたファイルを提示するほうが作業時間を短縮できるのでおすすめです。
また、製品の特徴や顧客の声などを共有すると、生成される回答がより現実に即したものになります。
部署を横断したプロジェクトであれば、人事部や財務部など別の部門からもデータ提供を受ける場面があるかもしれませんが、チームプランならそれらを容易に統合することも可能です。
何度も修正して理想の回答を得る
ChatGPTの回答は一回で完璧になるとは限りません。意図と違う答えが返ってきたら、要望を調整して再度投げかけてみましょう。
生成結果をもとにどこが違うのか伝えると回答精度が高くなり、チームプランなら、このやり取りがワークスペース内に残ります。
そして、チームメンバー内で履歴を共有し、同じ改善手法を真似できるのがメリットです。
納得のいく成果物ができるまで修正するのは時間がかかるように思えますが、従来の手作業での修正を何度も繰り返すよりも効率的です。
最終的に完成度の高い回答が得られたら、そのやり取りをテンプレート化して他のプロジェクトに応用しましょう。
ChatGPTチームプランの注意点

ChatGPTのチームプランを利用する際、以下の点に注意が必要です。
- セキュリティ対策が必要になる
- 論理と著作権を侵害しないように配慮する
セキュリティ対策と権利侵害への配慮は、長期的に企業運営するために重要な要素です。
セキュリティ対策が必要になる
機密情報や個人情報を扱う際は、チームプランの非学習化設定だけに頼らず、社内規定を整えておく必要があります。
例えば「機密文書は一部伏せ字にしてから入力する」「ダミーデータを使用する」などの運用ルールを決めると、安全性が高まります。
チームプランはワークスペース外部からのアクセスが制限される設計ですが、メンバーがうっかりファイルを外部に流出する可能性はゼロではありません。
SSO未対応など、企業の大規模統合管理システムと連携しにくい点にも留意が必要です。ログ取得機能が限定的な場合、社員の利用状況を細かく追跡できない可能性もあります。
コンプライアンス部門やIT担当者が中心となり、データの範囲や権限管理を明確にすることで万が一の事態を防ぎやすくなるでしょう。
論理と著作権を侵害しないように配慮する
AIが生成した文章は、必ずしも正確とは限りません。論理面での不具合や事実誤認に注意し、必ず人間が最終チェックを行ってから外部へ公開しましょう。
さらに、著作権にも配慮が必要です。AIが他の情報源を参照した場合、そのテキストに権利があるかもしれないので、抜粋や引用を行う際は、法的に問題ないかどうかを検討しましょう。
ChatGPTチームプランで企業の業務を効率化しよう

ChatGPTのチームプランは、社内のさまざまな業務を効率化できる便利な料金プランであり、以下のような機能に加え、アカウントを一元管理し、チーム内でチャット履歴や情報を共有できます。
【ChatGPTチームプランでできること】
- 議事録の作成
- 社内FAQと問い合わせの内製化
- マーケット調査とレポート作成
今回は使用時の注意点も掲載したので、資料作成や社内の問い合わせを効率化したいと考えている方は、ChatGPTのチームプランを検討してみましょう。












