DeepResearchは、複雑な調査を効率化する強力なAIエージェントですが、以下のような悩みによって最先端のリサーチスキル習得に踏み切れない方も少なくありません。
「DeepResearchとは具体的にどのようなツールで、何ができるのかイメージできない」
「OpenAIのDeepResearchだけでなく、他のAIにも同様の機能があるのか比較検討したい」
そこで今回は、OpenAIのDeepResearchの機能や使い方、注意点を徹底解説します。
【記事を読んで得られること】
- DeepResearchの基本的な機能
- DeepResearchの具体的な使い方・料金プラン
- Geminiなど他のAIが提供するDeepResearch機能についても比較検討できる
DeepResearchを活用する上での注意点や、ビジネスや学術研究など多様な活用事例も解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
DeepResearchとは

DeepResearchとは、OpenAIが開発したChatGPTの機能で、詳細なリサーチをするAIエージェント機能です。
ユーザーの意図を対話で正確に把握したうえで、Web上から複数ステップにわたり情報を検索・分析・統合します。さらに、最大30分程の長時間思考をかけて処理をするため、専門家が作成するような、引用元が明記された高品質なレポートを生成できるのが特徴と言えるでしょう。
DeepResearchは、OpenAIの次世代推論モデル「o3」を基盤としていて、ChatGPT上で利用できます。市場調査や競合分析、論文調査など幅広い用途に対応し、Pythonツールによる計算やグラフ作成、ファイルや画像の参照や埋め込みにも対応可能です。
従来の一問一答型AIとは異なり、DeepResearchは複雑な情報収集や深い分析を担うアシスタントとして設計されています。ビジネスや学術分野においても高い実用性を備え、戦略的な意思決定を支えるリサーチ機能として今後の展開も注目されるでしょう。
DeepResearchの主な機能

ここでは、DeepResearchの主な機能を4つ紹介します。
- 段階的なリサーチタスクの実行能力
- 推論に基づく情報の統合や分析
- 多様な情報ソースへの対応
- 根拠と引用元の明示
それぞれ詳しく見ていきましょう。
段階的なリサーチタスクの実行能力
DeepResearchは、単なる情報検索ツールではありません。ユーザーが入力したプロンプトの意味や背景を理解し、調査プロセスを段階的に進められます。
まず、プロンプトからユーザーの質問の意図を読み取り、次にインターネット上のさまざまな信頼できる情報源から関連情報を収集します。この際、情報をただ集めるのではなく、それぞれの情報の整合性を確認したり、複数の情報を比較しながら論理的に分析を進めていくのです。
さらに、途中で必要があれば、検索方法や質問の内容自体を調整すれば、表面的な回答にとどまらないより深い理解と高精度な調査結果を導き出せるでしょう。
まるで人間の研究者のように自律的に思考を巡らせながら、複雑な調査タスクを一つずつ進められる点がDeepResearchの大きな強みとも言えます。従来のAIでは対応が難しかった複雑なリサーチ業務も、より正確かつ効率的に遂行してくれるでしょう。
推論に基づく情報の統合や分析
DeepResearchは、AIがインターネット上から集めた複数の情報を比べて、信頼性を確認しながら筋道を立てて一連の推論プロセスを通じて分析します。普通の検索では見落とされがちな、情報同士の矛盾や背景にある因果関係、さらには将来の予測に役立つような知見まで導き出せるのです。
また、異なる出典や種類の情報源から得た内容を比較して、内容の食い違いや関係性を見つけ出し、それを整理して一つの考えとして統合できます。
さらに、DeepResearchには内蔵されたPythonというプログラミング言語を使える機能もあります。統計処理やデータ可視化など、数字データを分析したりグラフを自動で作ったりといった作業もこなし、推論結果に客観性と説得力を加えられるでしょう。複雑なデータの処理や視覚的なまとめもスムーズに行えるのが特徴です。
DeepResearchを使えば、単なる情報のまとめだけでなく、客観的なデータと論理に基づいたしっかりした内容のレポートを短時間で作成できるでしょう。
多様な情報ソースへの対応
DeepResearchは、普通のWebサイトのテキストだけでなく、画像ファイルやPDFといった、形式の違うさまざまな情報も取り扱えます。具体的には、政府が公開しているPDF形式の統計データや報告書、会議の資料などもテキスト情報としてAIが抽出し、内容を読み取って分析が可能です。
また、画像に含まれる文字や図表の情報もAIが自動で読み取ってくれるため、従来の検索エンジンでは見つけにくい細かい情報まで調べられます。形式の異なる情報をまとめて扱い、複数の視点や情報源を横断しながら、幅広い視点でのリサーチが可能になったと言えるでしょう。
加えて、今後は学術論文のデータベースや企業の社内情報、公開範囲が限られた資料などにもアクセスできるようになると期待されています。今後は、より専門的で高度なリサーチにも対応可能なツールとして、DeepResearchが実務や研究の現場で広く活躍するでしょう。
根拠と引用元の明示
DeepResearchで作成されるレポートには、使用された情報の出典が明確に記載されているという特徴があります。どのWebサイトや公的な文書をもとに内容が書かれているかが具体的に記載されているため、ユーザーはその情報の信頼性を自分でチェックできるでしょう。
また、気になる部分があれば、出典にさかのぼってさらに詳しい内容を確認できます。引用元をしっかり示す仕組みは、AIが事実ではない情報を出してしまう「ハルシネーション」と呼ばれる現象を防ぐうえでも効果的です。
DeepResearchのように出典が明記されているので、AIがまとめた情報にも安心して活用できるようになるでしょう。
DeepResearchの使い方

OpenAIが提供するDeepResearchを使うには、ChatGPTの有料プランに登録している必要があります。利用できるプランには、Pro、Plus、Team、Enterpriseなどがあり、無料プランでは使えないため、事前にプランの確認をしておきましょう。
実際の使い方は次の通りです。
- ChatGPTにログインして、Plus以上の有料プランのアカウントでチャット画面を開きます。
- 入力欄の下にある「DeepResearch」というボタンをクリックして機能を有効にします。
- 調べたい内容を、できるだけ具体的に入力しましょう。
例としては以下のイメージです。
- 「最新のAIの動向について、信頼できる情報源をもとにした詳しいレポートを作ってください」
- 「マーケティング分野における生成AIの活用例を比較してほしいです」
- リサーチが始まると、画面の右側にあるサイドバーに次のような内容が表示されます。
- 実行された手順の一覧
- 参照された情報源の簡単な説明
- リサーチがどこまで進んでいるかの状況
- リサーチは通常5〜15分ほどで終わりますが、内容によっては最大30分ほどかかるケースもあります。終わるとChatGPTから通知が届き、結果を確認できます。
- 出てきたレポートにわからない点があったり、もっと詳しく調べてほしいことがあれば、チャットでそのまま追加の質問や指示を送るのも可能です。
DeepResearchには、次のような便利な機能もあります。
- アップロードした画像やPDFファイルの内容も読み取って分析できる
- できあがったレポートはGoogleドキュメント形式で出力可能
- チームメンバーと共有や編集もできる
DeepResearchは信頼性の高い情報源に基づいたリサーチを効率的に行えるだけでなく、業務レポートの作成や社内資料の検討・戦略立案のための情報収集など、ビジネスシーンでも幅広く活用できる実用的なツールです。
DeepResearchの料金プラン

OpenAIのDeepResearchの料金プランは、以下の通りです。
| プラン | 料金 | 利用制限 |
|---|---|---|
| ChatGPTPro | 月額200ドル | 月間120回 |
| ChatGPTPlus | 月額20ドル | 月10回 |
| ChatGPTTeam | (別途料金体系) | 順次拡大予定 |
| ChatGPTEnterprise | (別途料金体系) | 順次拡大予定 |
| 無料プラン | 無料 | ー |
DeepResearchを利用する際には、自身の予算や利用頻度などを考慮し、最適なプランを選択しましょう。
DeepResearchの活用事例

ここでは、DeepResearchの活用事例を4つ紹介します。
- ビジネスにおける分析
- 学術研究におけるリサーチ
- 商品などの市場調査
- 個人利用における情報収集
それぞれ詳しく解説していきます。
ビジネスにおける分析
ビジネスの分野では、DeepResearchは情報を集めて分析するためのとても便利なツールです。早く正確に、経営の判断をするのに役立つでしょう。
具体的には、次のような場面で使えます。
- 今どんな商品やサービスが注目されているかを調べる
- ライバル企業がどんな戦略をとっているかを知る
- 業界の変化や課題を、数字や傾向から読み取る
今まで企業が何週間もかけてしていた調査も、DeepResearchを使えば数分から30分ほどでレポートとしてまとめられます。そのため、会社の意思決定を速く、かつ正確にできるようになるでしょう。
仮に新しい事業を始めたいとき、市場の大きさや将来性、他社の特徴などをDeepResearchで調べると、主観に頼らずに客観的なデータに基づいた判断や分析ができるのでおすすめです。
学術研究におけるリサーチ
DeepResearchは、自分の研究テーマに関連する最新の学術論文や専門資料を効率よく収集し、短時間で要点を把握できます。
従来であれば、膨大な時間と労力を必要とした文献調査を、DeepResearchを使えば大幅に効率化できます。結果的に、研究者はより創造的で本質的な研究作業に専念しやすくなるでしょう。
さらに、異分野の文献やデータを横断的に調べれば、新たな仮説の構築や研究テーマの発見にもつながる可能性があります。
たとえば、特定の疾患に関する研究を進める場合、DeepResearchに「疾患名+最新の研究動向」といった具体的な指示を与えれば、下記のような情報を網羅的にかつ整理された形式で取得できます。
- 世界中でどのようなアプローチが試みられているか
- 現在の研究で未解決となっている課題は何か
- 研究の進展が期待される領域はどこか
DeepResearchは単なる情報収集ツールではありません。研究の質とスピードを高めるための実践的なアシスタントとして、学術研究においても十分な価値を発揮するでしょう。
商品などの市場調査
DeepResearchは、企業の製品開発やマーケティング戦略の立案においても、実用性の高いリサーチ支援ツールです。特に、消費者ニーズの把握や競合製品の分析、トレンド予測といった分野でその力を発揮します。
たとえば、次のような情報収集が可能です。
- 特定ターゲット層のニーズや嗜好の変化をリアルタイムで分析
- 競合製品の機能・価格・評価(レビューなど)を項目別に比較
- ニュースメディアなどからトレンドの兆しを抽出し、将来の需要を予測
これまで時間と労力をかけて行っていた市場調査を、DeepResearchによって効率化すれば、よりスピーディかつ根拠のある意思決定が可能になります。さらに、過去の市場データや現在の消費動向を組み合わせて分析することで、中長期的な予測を立てられるでしょう。
DeepResearchは単なる検索にとどまらず、意思決定の材料を論理的かつ多角的に収集するための実務的ツールとして、商品開発や市場戦略の現場でも活用されています。
個人利用における情報収集
DeepResearchは、ビジネスや学術的な場面だけでなく、個人が日常生活の中で行う情報収集においても重宝するでしょう。趣味や学習に関する情報を効率よく集めたり、生活の中で発生するさまざまな選択肢について、信頼性のある情報に基づいた判断をサポートしてくれます。
具体的には、以下のような活用が可能です。
- 関心のある分野についての最新情報や専門的な知見の取得
- 学びたいテーマに関連する資料や信頼性の高い情報源の探索
- 製品やサービスの比較情報の整理と可視化による購買判断のサポート
Web上に点在する情報をまとめて整理し、わかりやすい形でレポート化してくれるため、DeepResearchは検索の手間を省きながら知りたい情報にすばやくたどり着けるでしょう。
知りたいことを深掘りしながら、日々の調査や選択を効率よく進めるための実用的なツールとして、個人利用の場面でも信頼できる存在となるかもしれません。
DeepResearchの注意点
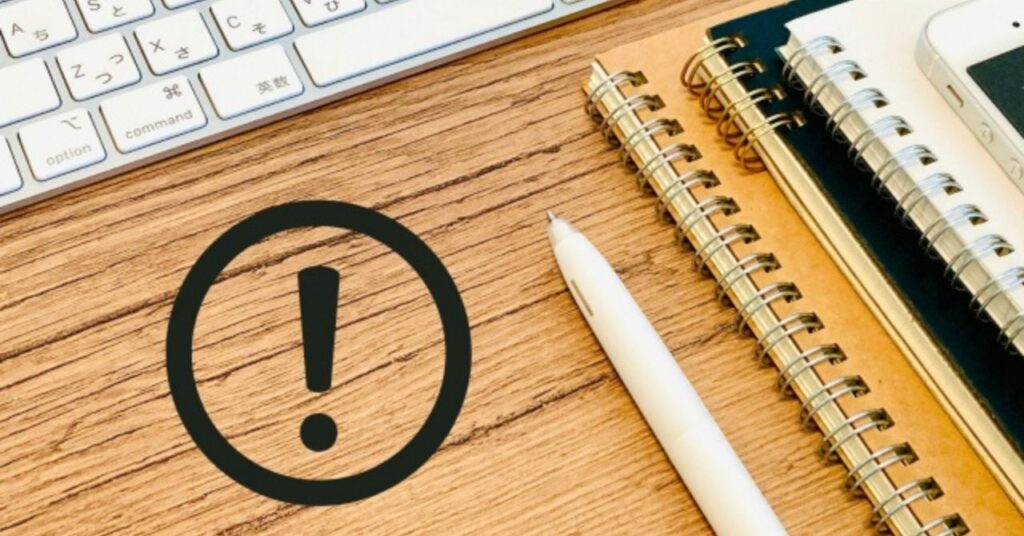
ここでは、DeepResearchの注意点を3つ紹介します。
- ハルシネーションの生成リスク
- 信頼性に乏しい情報源が引用される可能性
- 場合により回答までに時間がかかる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
ハルシネーションの生成リスク
DeepResearchは仕組み上、完全に誤った情報、いわゆる「ハルシネーション(AIによる虚偽の生成)」を100%回避するのは現状では難しいとされています。
理由としては、参照している情報源のデータが古かったり、現在では支持されていない理論や見解に基づいている場合、誤りを含むレポートが生成される可能性があるためです。
そのため、DeepResearchの出力内容をそのまま鵜呑みにするのではなく、人間の目による最終確認と内容の整合性チェックが欠かせません。特に、ビジネス上の意思決定や学術研究など、正確性が求められる場面では以下の点に留意しましょう。
- 専門家の意見やレビューを併用する
- 複数の信頼できる情報源と照らし合わせて検証する
- 引用元の更新日や信頼性にも注意を払う
ファクトチェックする姿勢を保てば、誤った判断やリスクを未然に防げるでしょう。
信頼性に乏しい情報源が引用される可能性
DeepResearchは、Web上の膨大な情報をもとに関連性の高いデータを抽出し、自動でリサーチレポートを作成するAIツールです。ただし、情報源の質には注意が必要です。
インターネット上には、個人ブログや匿名投稿、出典不明の解説記事など、必ずしも信頼性が高いとは言えない情報も多数存在します。DeepResearchでは、アルゴリズムによって情報の偏りや質のばらつきを抑制する設計がなされていますが、低品質な情報源がレポート内に混在してしまう可能性を完全に排除できません。
そのため、生成されたレポートを活用する際は、引用された情報が信頼できるかどうかを自ら確認する姿勢が求められます。特に、社外への提出資料や意思決定に用いる情報である場合は、出典の正確性や運営主体、更新日などを確認した上で判断しましょう。
以下のような点を意識するのがおすすめです。
- 公的機関・専門団体・業界メディアなど、発信元が明確な情報かどうかを確認する
- 同様の内容が複数の信頼できる情報源でも示されているかを照合する
- 意図的な誘導や広告目的の情報でないかを見極める
DeepResearchは情報収集の効率を高めてくれるツールであり、最終的な情報の取捨選択や判断の責任はユーザーにあるという意識を常に持つのが、適切なリサーチ活用につながります。
場合により回答までに時間がかかる
DeepResearchは、単純な会話型AIとは異なり、正確かつ網羅的なレポート作成を目指すプロセスであるため、即時的な回答は得られないケースも少なくありません。
質問の内容が複雑であったり、情報収集に必要なデータ量が多い場合には、回答までに5分〜最大30分程度の時間がかかるケースもあります。そのため、すぐに答えが欲しい簡易な調べものやリアルタイム性が重視される場面では、別の検索手段やツールを選ぶ方が適している場合もあるでしょう。
とはいえ、DeepResearchのリサーチ処理はバックグラウンドで実行されるため、その間に他の作業を並行して進められるという利点もあります。
DeepResearchを活用する際には、事前に時間的余裕を確保し、レポートの完成を待つ前提で質問をするのがおすすめです。時間をかける価値のある調査には十分に応えてくれる機能を備えているからこそ、調査の目的や状況に応じて、適切なタイミングや用途を見極めて活用するのが望ましいでしょう。
ChatGPT以外のDeepResearch機能が使えるAI

最後に、ChatGPT以外のDeepResearch機能が使えるAIを5つ紹介します。
- Gemini
- Genspark
- Perplexity
- FeloAI
- Grok
それぞれ詳しく見ていきましょう。
Gemini
GeminiのDeepResearchは、Googleが提供するAIを活用したリサーチツールで、2025年3月時点では「Gemini2.5Pro Experimental」というAIモデルを搭載しています。GeminiのDeepResearchは日本語にも対応しており、Webサイト、学術論文、書籍、統計データなど、さまざまな情報源から必要なデータを集めて整理できます。
GeminiDeepResearchの特長は、ただ情報を集めるだけでなく、ユーザーが入力した質問の意図をAIが読み取り、調査の流れを自動的に考えて実行する点です。集めた情報はAIが分析して、わかりやすくまとめたレポートとして出力されます。
また、GoogleドキュメントやGmailなどのサービスとも連携しているので、レポートの編集や共有がとても簡単です。
料金体系は次の通りです。
- 無料プラン:2025年3月より一部機能が解放されましたが、利用回数が月最大5回と制限があります。
- アドバンスプラン(月額2,900円):ほぼ無制限に利用可能で、Googleドキュメントとの連携機能も含まれます。
Geminiは日常業務から専門領域まで幅広く対応できる、Googleエコシステムとの親和性にも優れたリサーチツールとして注目されています。
Genspark
GensparkのDeepResearch機能は、複数のAIエージェントが連携して作業を進める「マルチエージェント構造」を活用した、調査支援のための検索機能です。ユーザーが知りたいテーマを入力すると、それに関連する専門分野を担当するエージェントたちが協力して、インターネットや各種データベースから情報を集めて分析します。
調査結果は「Sparkpage(スパークページ)」と呼ばれる特設ページにまとめられ、重要なポイントが整理されたレポートとして表示されます。それぞれの内容には、出典元のリンクが付いており、どこからの情報か確認する手間を取らせません。SparkpageはWeb上に保存でき、URLを共有すれば他の人と調査結果を共有できるのも嬉しい機能です。
DeepResearchでは、AIが一方的に結果を返すのではなく、調査中にユーザーが質問や確認ができる「AIコパイロット」とのやりとりも可能。そのため、ただレポートを読むのではなく、ユーザーが対話しながら調査を深めていけるのがGensparkの特徴と言えるでしょう。
さらに、Gensparkは文章の分析に限らず、画像や動画、翻訳など複数の形式の情報処理にも対応しており、分野ごとの特化エージェントによって専門性の高い調査にも対応できます。法律や学術のように正確な情報が重要な分野では、複数の情報源を比較しながら信頼性を高める工夫もされています。
料金プランは以下の通りです。
【無料プラン】
- 通常の検索回数無制限
- Deep Research V2の無料利用は、1日1回まで
【Plusプラン(月額24.99ドル)】
- すべてのAIエージェントにアクセス可能
- 高性能モデル(FLUX、Ideogram、Klingなど)の利用
- 無料版の5倍のリクエスト処理量
無料トライアルは設けられていませんが、無料プランでもDeepResearch機能を試用可能であり、導入のハードルは低い設計となっています。
Perplexity
Perplexityは、AI技術を活用した検索エンジンで、2025年2月に新たに追加された「DeepResearch」機能によって、より本格的な情報収集や調査ができるようになりました。この機能では、ユーザーの質問に対してAIが複数の検索クエリを自動で発行し、関連する情報をさまざまな信頼できるWebサイトから集め、まとめてくれます。
特にこの機能は、レポート作成や論文調査、技術・ビジネスに関する深いリサーチが求められるときに役立ちます。Perplexityは、2024年以降は独自の検索インデックスと複数検索エンジンの検索機能を活かしながら論文やニュース記事なども含めて幅広く情報を集められ、必要に応じて簡単なプログラミング処理や数値分析も行えます。
作成されたレポートは要点が見やすく整理されており、各内容には出典元のリンクがついているため、どの情報に基づいているかをすぐに確認できます。また、レポートは「PerplexityPages」として保存・公開できるので、他の人と共有しやすいのも特徴です。
料金は以下のようになっています。
【無料プラン】
- 1日あたり5件までDeepResearchを利用可能
- 出典付きレポートの表示・共有が可能
【Proプラン(月額20ドル)】
- DeepResearchをほぼ無制限に利用可能(1日最大500件程度)
- レスポンスの高速化
- より高性能なAIモデルの使用が可能
さらに、スマートフォンアプリやChromeの拡張機能にも対応しており、場所や時間を選ばずにリサーチできます。ChatGPTのDeepResearchと比べると、Perplexityは無料でもかなりの範囲を使える点や、レポートの共有のしやすさ、アプリの使いやすさが大きな違いです。
FeloAI
FeloAIは、日本で開発されたAI検索ツールで、日本語での検索や情報の要約に強みを持つサービスです。複数のAIモデルを組み合わせることで、ユーザーの質問に対して検索結果をそのまま並べるのではなく、意図を読み取った文章形式の回答を出してくれるのが特徴です。
DeepResearchという名称はFeloAI公式ではあまり強調されていませんが、実質的に同等の機能を備えています。
FeloAIのDeepResearch機能では、普通のWebサイトだけでなく、SNSの投稿や学術論文など、専門的な情報源にも対応しているのはご存じでしょうか。X(旧Twitter)に投稿された最新の意見や、学術論文データベースからの情報を組み合わせて、テーマに関する全体像を整理してくれます。
出力の面でもユニークな機能があり、検索結果をもとに、PowerPoint形式のスライドやマインドマップを自動で作成できる機能が搭載されています。検索から資料作成までを一つの流れで進められ、手持ちのPDFやテキストファイルをアップロードすれば、その中身を分析・要約してくれるファイル分析機能も備わっています。
料金プランは以下の通りです。
【スタンダードプラン(無料)】
- AI検索は無制限に使用可能
- 登録なしで利用できる
- プロフェッショナル検索は1日5回まで
- ファイル分析は1日3回まで
【プロフェッショナルプラン】
- 月額2,099円(年契約の場合は月あたり1,750円)
- プロフェッショナル検索は1日300回まで利用可能
- ファイル分析は無制限で利用可能
- AIチャットや資料作成機能も使える
- 無料トライアル期間あり
FeloのDeepResearch機能は、日本語を中心とした情報収集に適しており、調査結果をそのままプレゼンやレポートに活かせる点が魅力です。特に、資料作成の時間を短縮したい人や、調査とアウトプットを一度に済ませたい人にとっては、とても実用的なツールです。
Grok
Grokは、xAIが2024年に公開したAIチャットサービスで、調査に特化した「DeepSearch(ディープサーチ)」モードと、AIの思考過程を可視化する「Think(シンク)」モードを搭載しています。
DeepSearchでは、WebサイトやSNS(X)から情報を収集し、矛盾を検証したうえで出典付きで要約を作成します。ニュース速報のように情報が分かれる場合でも、複数の出所を比較し、整合性のある回答を提示してくれるのが特徴です。
Thinkモードは、AIがどのように結論を出したのかを段階的に示す機能で、ユーザーはその思考過程を追って理解を深められます。
情報源にはインターネットとSNSが含まれ、リアルタイムな話題や意見も反映。高性能AIモデルと強化学習によって、複雑な課題にも柔軟に対応できます。
出力の形式はチャットのようなテキスト中心ですが、DeepSearchでは短くまとまった文章に、たくさんの引用リンクがついた形で情報が提示されます。また、ThinkモードではAIの推論ステップが順番に表示され、ユーザーが一緒に理解を深められる構成になっています。
料金プランは次のとおりです。
【ベータ版は無料】
【XPremium+(プレミアムプラス)加入者向け】
- 月額約6,080円(Web経由の場合)
- Grok3の全機能が追加料金なしで利用可能
- DeepSearchとThinkモードが使用可能
- 将来追加される新機能への先行アクセスあり
- 音声モード(予定)、画像生成無制限も含まれる
Grokは、SNS(特にX)と連動して提供されているAIツールで、投稿データを含む幅広い情報をもとに調査が行える点が魅力です。ChatGPTなどのリサーチ機能が単体で提供されるのに対し、Grokはソーシャルメディアと一体化している点で、異なる活用スタイルが期待できるでしょう。
DeepResearchでビジネスを効率化させよう!

本記事では、OpenAIのDeepResearchがどのようなツールであるかについて、主な機能や使い方、料金プラン、活用事例、そして利用時の注意点に至るまでを解説しました。
DeepResearchは、多段階にわたるリサーチタスクの実行、推論に基づいた情報の統合・分析、多様な情報ソースへの対応、さらに根拠と引用元の明示といった主要機能を備えています。人間が数時間かけて行うような調査を、数十分で完了できるでしょう。
【DeepResearchでビジネスを効率化させるためのポイント】
- 目的に応じたプロンプトを設計する
- 利用頻度や予算に応じたプランを選択する
- 出力結果の信頼性を常に確認する
DeepResearchは、ビジネスにおける情報収集や分析業務を効率化し、新たな視点や洞察を得るための強力なツールとなります。ぜひ本記事を参考に、DeepResearchを業務に取り入れ、ビジネスの生産性向上に役立ててください。












