業務の効率化や人手不足の解消を目的に、銀行業界ではAIの活用が本格化しつつあります。
生成AIを取り入れることで競争力の底上げを図る動きが広がっていますが、以下のような悩みによって導入に踏み切れない方も少なくありません。
「銀行にAIを導入しても、どこまで成果が出るのかわからない」
「AIの利便性は感じるけれど、銀行員のスキルや文化とのギャップが心配」
そこで今回は、銀行業界における生成AIの導入事例を紹介します。
【記事を読んで得られること】
- 銀行業界で生成AI導入が進む背景
- 業務効率化やサービス向上につながる活用メリット
- 国内15行の具体的な導入事例
AI導入時の課題も解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
銀行業界で生成AIの導入が進む背景
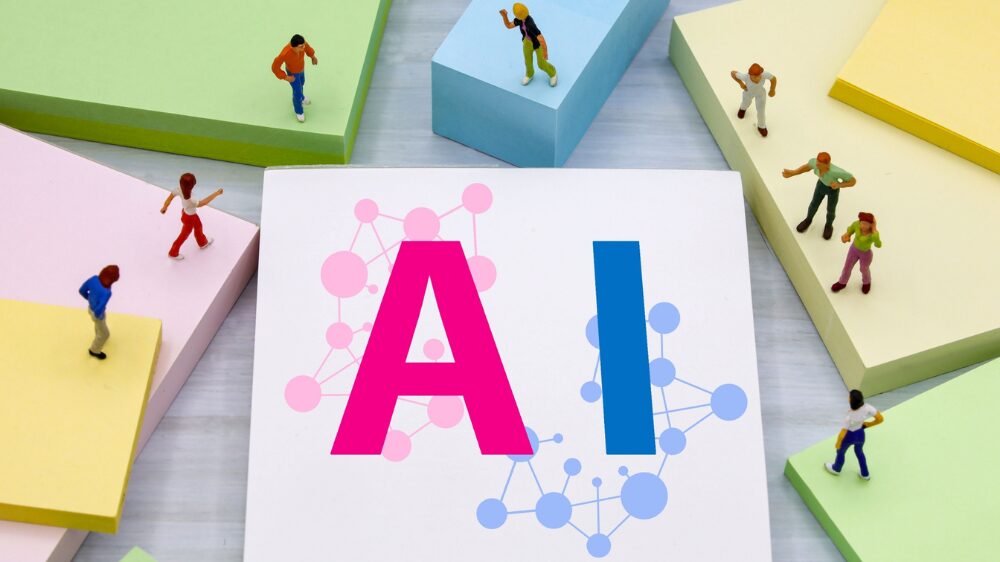
まず、銀行業界で生成AIの導入が進む背景を3つのポイントで解説します。
- 多額のコストが嵩む
- 従来のビジネスモデルを維持できない
- 銀行業界全体でデジタル化が急務になっている
それぞれ詳しく見ていきましょう。
多額のコストが嵩む
銀行は支店の維持費や人件費といった固定コストが重くのしかかっています。
特に、保管スペースや金庫設置が必要な支店では賃料が高騰しやすい傾向にあるでしょう。
加えて、サイバー攻撃の増加に伴い、セキュリティ対策費も欠かせません。
負担を軽減する手段として、業務自動化による効率化を図れる生成AIの導入が現実的な選択肢となっています。
従来のビジネスモデルを維持できない
マイナス金利と人口減少により、貸付収益への依存が難しくなり、金融機関の収益構造は転換期を迎えています。
倒産リスクに備えた引当金の積み増しも、経営を圧迫する一因。こうした中で、生成AIは市場データを分析し、顧客ニーズに即した新サービス開発を後押しするツールとして注目されています。
既存のビジネスモデルからの脱却が求められているのです。
銀行業界全体でデジタル化が急務になっている
スマホやネットバンキングの普及で、若年層を中心に窓口利用は減少傾向にあります。
利用者の期待に応えるには、スピード感のある非対面対応が欠かせません。銀行が保有する大量の顧客データを活かすには、AIによる分析・自動処理が有効です。
なかでも生成AIは、顧客応答の自動化や文書作成など業務効率化を進めるうえで、有力な手段として導入が加速しています。
銀行業界で生成AIを活用する5つのメリット

ここでは、銀行業界で生成AIを活用するメリットを5つ紹介します。
- 業務の自動化によって効率が上がる
- 顧客対応が効率的かつ高品質になる
- サイバー攻撃や不正の検知が強化される
- データ活用によって新たな商品やサービスが生まれる
- 人手不足への対応につながる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
業務の自動化によって効率が上がる
生成AIを活用すれば、定型的な文書作成や社内FAQ対応といった繰り返し業務を自動化でき、人的負担を大きく軽減できます。
具体的には、報告書の下書きや質問応対の自動化により、対応時間を削減しながら生産性を高められます。
リソースを創造的な業務へ振り向けられ、人件費や運用コストの見直しにもつながるでしょう。
顧客対応が効率的かつ高品質になる
生成AIにより、問い合わせ対応の一部を24時間自動化できるため、顧客対応の効率が大きく向上します。
従来よりも幅広い質問に対応でき、サービス品質のばらつきも抑えられるでしょう。顧客データをもとに最適な提案を自動生成する仕組みを整えれば、個別ニーズに応じたサポートも実現できます。
サイバー攻撃や不正の検知が強化される
生成AIは、異常パターンの検出や取引監視を自動で行えるため、不正行為への対応が迅速になります。
人の目では見逃しやすい動きも検知でき、ヒューマンエラーの防止にもつながります。AIが継続的に学習し進化すれば、巧妙化するサイバー攻撃にも柔軟に対応可能となるでしょう。
データ活用によって新たな商品やサービスが生まれる
生成AIは、顧客情報や市場データの分析を通じて、商品開発やサービス改善のヒントを導き出します。収益源が限られる中、的確なニーズ把握と迅速な意思決定は競争力の強化に直結します。
属性や行動履歴に基づいたパーソナライズ提案で、提案精度と顧客満足度の向上が期待できるでしょう。
人手不足への対応につながる
生成AIは、人手に頼っていた反復作業を自動化し、少人数でも業務を回せる体制づくりを支援します。
浮いたリソースは営業や顧客対応など、付加価値の高い業務に集中できるでしょう。
「AIで仕事が奪われる」という懸念もありますが、実際には業務補助ツールとして活用することで、働き方の柔軟性や定着率の改善にもつながります。
日本の銀行における生成AI導入事例15選

ここでは、日本の銀行における生成AI導入事例を15行紹介します。
- 三井住友銀行:社内向け生成AIアシスタントで業務効率化を推進
- 三菱UFJ銀行:全社で生成AIを活用し業務革新を加速
- みずほ銀行:生成AIとAI-OCRで業務効率化と新サービス創出
- りそな銀行:AIで商談成約確度をスコアリングし営業効率化
- SBI新生銀行:AIスコアリングでマネーロンダリング対策を強化
- 楽天銀行:AIによる個人ローン審査モデルで受賞・データ活用を推進
- PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行):AIチャットボットで24時間顧客サポート
- 住信SBIネット銀行:GPT-4o導入のバーチャルアシスタントで電話応対を自動化
- 静岡銀行:生成AIチャットボットで営業提案を高度化
- 北海道銀行(ほくほくフィナンシャルグループ):AI信用スコアリングで融資審査を高度化
- 福岡銀行:AI与信モデルで融資先の健全度をモニタリング
- 筑邦銀行:AIで財務分析し不良債権の予兆管理を実現
- 横浜銀行:MOBI VOICEを導入し従業員の生産性向上
- セブン銀行:社内生成AI「7Bank-Brain」で日常業務を自動化
- ゆうちょ銀行:現場主導の生成AI内製化で業務革新
それぞれ詳しく見ていきましょう。
三井住友銀行:社内向け生成AIアシスタントで業務効率化を推進
三井住友銀行は、社内業務支援として生成AIツール「SMBC-GAI」を開発し、2023年7月から活用を開始しました。
Microsoft Teams上で動作し、調べ物・翻訳・文字起こしなどを支援します。開発は数日で完了し、その後約3カ月半かけて安全な運用ルールを整備。事実誤認のリスクに対しては、正確性を自ら確認するガイドラインを徹底しています。
導入後の利用件数は増加を続け、2024年4月時点で1日約12,000件に到達。短期間での浸透と定着が進み、業務効率化に貢献している点が特徴といえるでしょう。
三菱UFJ銀行:全社で生成AIを活用し業務革新を加速
三菱UFJ銀行は、2023年11月からAzure OpenAIサービスを使い、社内で生成AI「ChatGPT」の運用を開始しました。
手続き照会・稟議書作成・ウェルスマネジメント分野での活用を優先し、特に融資関連の書類作成は、手間と時間の削減効果が期待されています。今後は、業務フローの見直しと学習データの整備を進め、2024年度内に社内システムとAPI連携を完了する予定です。
また、現場への浸透を目的に「伝道師」育成の研修も2024年9月に開催し、社内全体でAI活用を定着させる体制構築を図っています。
みずほ銀行:生成AIとAI-OCRで業務効率化と新サービス創出
みずほ銀行は、生成AIの活用を2023年2月から検討し、6月に社内用AI「Wiz Chat」を導入しました。
現在は「Wiz Search」「Wiz Create」などシリーズ開発を進行中です。3万ページ以上の事務手続き書・マニュアルの検索を支援するAIチャットボットを活用し、業務照会の負担軽減と稟議資料の作成時間短縮を実現しました。
法人営業の現場では、稟議資料のドラフトを約10分で自動生成できるようになり、営業担当者が顧客提案に集中できる環境が整いつつあります。
りそな銀行:AIで商談成約確度をスコアリングし営業効率化
りそな銀行は、ブレインパッドと共同で業務支援ツール「Data Ignition」を開発し、顧客の金融商品ニーズをAIでスコアリングする仕組みを構築しました。
住宅ローンや投資信託の成約確度を予測し、優先すべき顧客を抽出。自社で検証済みのAIモデルを地域金融機関にも展開し、営業活動の効率化を支援しています。
初導入先は静岡銀行で、今後はFinBASE社を通じて全国の地域銀行へサービス提供を拡大する計画です。
SBI新生銀行:AIスコアリングでマネーロンダリング対策を強化
SBI新生銀行は、取引モニタリング強化のため自社開発のAIスコアリングモデルを導入しました。
2023年の導入後、2024年にはデータ連携も本格化。疑わしい取引のスコアと判断根拠を提示する仕組みにより、調査件数は約半分に削減されました。
重要案件に集中できる体制が整い、業務効率が向上。金融犯罪の傾向に応じて、スコアモデルのチューニングも継続的に行われています。
楽天銀行:AIによる個人ローン審査モデルで受賞・データ活用を推進
楽天銀行は、カードローン審査にAIモデルを導入し、「World’s AI In Finance Award」で国内・地域部門の2冠を達成しました。
1600万超の口座情報を活用した審査体制が評価され、アジア太平洋地域でも注目を集めています。受賞は、データ分析力と技術力の裏付けであり、今後も顧客に価値ある商品・サービスを提供し続ける姿勢を明確にしています。
PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行):AIチャットボットで24時間顧客サポート
PayPay銀行は、2019年にAIチャットボット「AIChat」をWebサイトへ導入し、24時間365日対応の顧客サポート体制を整えました。
LINEの自動応答や電話・チャット応対に加え、Webからもスムーズに問い合わせが可能です。会話履歴や満足度をもとに教師あり学習を継続し、回答の精度と品質を向上。
「聞き返しシナリオ」によって表現の揺れにも対応でき、自己解決を促す仕組みとして顧客体験の改善に貢献しています。
住信SBIネット銀行:GPT-4o導入のバーチャルアシスタントで電話応対を自動化
住信SBIネット銀行は、業務支援アプリ「Shadow」を社内開発し、AIとのチャットでデータ分析やレポート作成が可能な環境を整えました。
金融特有の複雑な集計・予測・可視化にも対応し、業績見込みや要因分析を自動化できます。さらに、AIが自律的に判断しプログラムを実行する機能も実装。Azureの閉域ネットワークで運用され、セキュリティにも配慮されています。
全社員への展開により、業務効率と分析精度の向上を同時に実現しているのです。
静岡銀行:生成AIチャットボットで営業提案を高度化
静岡銀行は、Snowflakeやブレインパッドと連携し、営業支援チャットボットを新たに開発しました。
S-CRMに蓄積された顧客情報を活用し、顧客ごとの最適な提案を自動化。過去の営業活動から経営環境の変化に応じた対応も可能です。若手行員の準備負担を減らし、業務レベルの向上にもつながっています。
Snowflakeの生成AIサービス「Cortex」を使う国内初の事例としても注目されています。
北海道銀行(ほくほくフィナンシャルグループ):AI信用スコアリングで融資審査を高度化
ほくほくフィナンシャルグループは富士通と連携し、北陸銀行と北海道銀行で生成AIの実証実験を実施しています。
行内の問い合わせ対応や文書作成・校正、融資関連の説明文などにAIを活用。富士通が提供する環境を使うことで、構築の手間を省きスムーズに検証を開始できました。
実験を通じて、具体的なユースケースを洗い出し、業務効率化や文書品質の改善に向けた有効性を検証中です。
福岡銀行:AI与信モデルで融資先の健全度をモニタリング
福岡銀行は、営業店の稟議書作成を支援する生成AIシステムを内製開発し、全店舗での導入を開始しました。
案件情報や交渉記録をもとにAIが意見欄のドラフトを生成し、文書作成の負担を大幅に軽減。業務効率を高めるとともに、顧客理解や課題発見に時間を割ける体制を整えました。
今後は融資業務全体でのAI活用を視野に、コンサルティング営業の質を高める取り組みを進めています。
筑邦銀行:AIで財務分析し不良債権の予兆管理を実現
筑邦銀行は、IVRy社と提携し、音声AI「IVRy」の導入を進めています。
このプロダクトは、電話対応を自動化するSaaS型の対話AIで、人手不足に悩む中小企業の支援にもつながります。導入コストが低く、AIによる業務効率化を実現しやすい点も評価されているのです。
筑邦銀行はこの連携を通じて、地域企業の業務支援や予兆管理の高度化を図り、支援体制の多様化を目指しています。
横浜銀行:MOBI VOICEを導入し従業員の生産性向上
横浜銀行は、AI電話応答システム「MOBI VOICE」を2023年に導入し、事務サービス部での融資・カード業務の問い合わせ対応を自動化しました。
クレジットカード不正対策では、一次受付の自動化により「放棄呼ゼロ」を実現。行員の作業時間も月67時間削減され、他業務に集中できるようになりました。
今後は6部署での横断的な活用と、生成AIとの連携によるさらなる自動化を予定しています。
セブン銀行:社内生成AI「7Bank-Brain」で日常業務を自動化
セブン銀行は、社内向け生成AI「7Bank-Brain」を開発し、メール作成・アイデア出し・規程検索などの業務支援をしています。
新入社員が社内規程をすばやく理解できるようサポートし、業務の質と効率を両立させる仕組みとして活用されています。さらに、経営方針の一貫性を保つため「社長AI」も導入されているのです。
セキュリティ確保のため情報入力の制限やクローズド運用を徹底し、社員が意識せず使えるAI浸透を目指しています。
ゆうちょ銀行:現場主導の生成AI内製化で業務革新
ゆうちょ銀行は、neoAIと連携し、AIプラットフォーム「neoAI Chat」を導入しました。
照会業務や文章作成の実証実験で有効性を確認し、専門的なAIが既存ドキュメントから簡単に構築できる点も高評価。Microsoft Azure上での運用によりセキュリティ基準も満たしています。
今後は各部署の業務に特化した機能や管理体制を整え、金融業界全体の業務改革にもつながる展開を進めています。
銀行業界で生成AIを導入する際の7つの課題

最後に、銀行業界で生成AIを導入する際の課題を7つ紹介します。
- 機密情報が漏洩するリスクがある
- サイバー攻撃の対象になりやすい
- 出力結果の根拠が不透明になりやすい
- 誤った出力により業務ミスが生じるおそれがある
- AIの専門知識が必要になる
- 導入や運用にコストがかかる
- 運用ルールが整備されていないと混乱が生じる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
機密情報が漏洩するリスクがある
生成AIの導入には、顧客情報や社内機密を扱うリスクが伴います。
適切な匿名化や用途制限がなければ、入力データがAIに学習されて外部に漏れる可能性があるでしょう。特に生成AIは、無意識のうちに機密情報を蓄積しやすいため、運用には細心の注意が必要です。
暗号化や利用権限の制限、厳格なポリシー策定などの対策が欠かせません。セキュリティ対策とデータ管理ルールの両立が、企業が安全に生成AIを活用するための前提条件となります。
サイバー攻撃の対象になりやすい
金融機関は常にサイバー攻撃の標的となっており、生成AI導入で新たな脆弱性が生まれる可能性があります。
悪意ある第三者が、AIに不正な質問を投げて機密情報を引き出したり、偽の学習データを与えて誤作動させるリスクもあります。また、AIが顧客になりすまし、口座情報の窃取に使われる恐れもあるでしょう。
高度化する攻撃に対応するには、AIの特性を踏まえた新たな防御策が必要です。検知システムの強化やAI監視体制の整備が、セキュリティ維持には欠かせません。
出力結果の根拠が不透明になりやすい
生成AIは膨大なデータから回答を導き出しますが、出力の根拠が示されない場合、信頼性の判断が難しくなるでしょう。
いわゆる「ブラックボックス化」により、誤情報や不適切な説明が生成されるリスクがあります。特に金融分野では、説明責任や正確性が求められるため、誤出力は顧客の信頼喪失につながりかねません。
信頼性を確保するには、法令や自社データと連携したシステム設計と、出力根拠を明示できる仕組みが必要です。
誤った出力により業務ミスが生じるおそれがある
生成AIは高精度な分析が可能ですが、すべての状況で正しい判断を下せるわけではありません。
誤情報や不適切な出力によって、業務ミスや不正確な情報発信につながるリスクがあります。そのため、重要な判断は人が最終確認をするなど、AI任せにしすぎない体制が求められます。
AIはあくまで補助ツールと捉え、人と分担しながら活用することで、正確性と信頼性を両立できるでしょう。
AIの専門知識が必要になる
生成AIを活用するには、仕組みやリスクへの理解が欠かせません。
外部人材の確保は難しく、社内でのリテラシー向上や教育体制の整備が重要です。操作方法だけでなく、利用判断やデータ管理の知識も求められるでしょう。
知識が不十分なまま運用すれば、システムの定着が進まず、導入効果を発揮できません。実践的な研修と、現場をリードできる人材育成が、安定的な活用につながります。
導入や運用にコストがかかる
生成AIは業務効率化が期待される一方、初期費用やランニングコストがかかります。
古いシステムとの連携が難しい場合は、想定以上の費用や手間が発生する可能性もあります。また、セキュリティ対策などの維持費が、人件費削減効果を上回るケースも考えられるでしょう。
そのため、いきなり全社導入するのではなく、小規模な試験運用(PoC)で効果を見極めましょう。コストと効果のバランスを事前に見極める視点が欠かせません。
運用ルールが整備されていないと混乱が生じる
生成AIは便利なツールですが、明確なルールがないまま運用するとトラブルの原因になります。
従業員が機密情報を入力してしまい、情報漏洩に発展するケースや、AIの出力を鵜呑みにして確認を怠れば、業務ミスが発生するおそれもあります。安全に活用するには、AIの使用目的や範囲、禁止事項を明示したガイドラインの整備が欠かせません。
技術的な対策だけでなく、ルールを周知し、現場での運用を徹底する仕組みづくりが必要です。
銀行業界における生成AI導入事例を参考にしてビジネスを効率化させよう
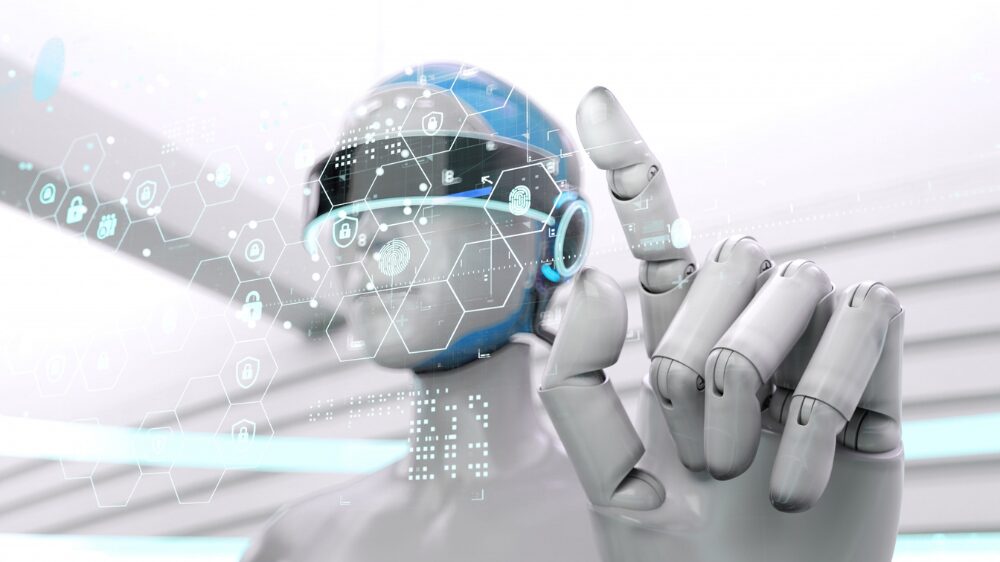
本記事では、銀行業界で生成AI導入が進む背景やメリット、具体的な事例と課題について解説しました。
生成AIは、業務の効率化や人手不足の対応に貢献し、新たなサービス創出の可能性も広げます。しかし、情報漏えいや誤出力のリスクには注意が必要です。
【生成AI導入に取り組む際のポイント】
- ROIを意識し、スモールスタートで検証する
- 専門人材や教育体制を段階的に整える
- 導入目的と運用ルールを明確にする
他社の取り組みも参考にしながら、自社に合った導入方針を検討してみてください。












