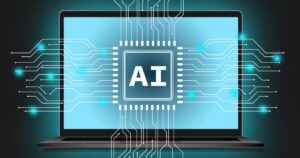介護業界にAIを導入すべきか悩んでいるが、決断には踏み切れない経営者の方も少なくありません。
「介護現場で本当にAIを使いこなせるのか不安」
「AI導入コストに見合う介護での効果があるのかわからない」
そこで今回は、介護業界におけるAIの活用状況やメリット・課題をわかりやすく解説します。
【記事を読んで得られること】
- AI導入による業務効率化や負担軽減のポイント
- 導入に踏み切れない理由とその対処法
- 現場で活用されている具体的な事例
現場の課題をどう乗り越えるかも紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
介護業界におけるAI活用の現状

まず、介護業界におけるAI活用の現状を以下の3つで解説します。
- 入居者の状態変化を検知する見守り用途が広がっている
- 業務記録や情報共有の効率化にAIが活かされている
- 人手不足を補う手段として注目が集まり導入が進んでいる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
入居者の状態変化を検知する見守り用途が広がっている
AIによる見守りシステムは、転倒や体調変化の早期察知に有効です。センサーやカメラが高齢者の動きを常時モニタリングし、異常を自動通知します。
たとえば「LASHIC」は、カメラを使わずに脈拍や熱中症リスクも検知でき、プライバシーを守りながら負担を軽減します。また「Rehab Cloud モーションAI」では姿勢推定機能を活用し、転倒リスクのある動作を事前に検知可能。
24時間体制でAIが稼働すればスタッフが常に張り付く必要がなくなり、迅速な対応が可能になるでしょう。
参考:介護施設用デジタル見守りシステムLASHIC-care(ラシク)|インフィック株式会社
参考:AI動作分析ソフトRehab Cloud モーションAI|株式会社Rehab for JAPAN
業務記録や情報共有の効率化にAIが活かされている
介護現場では、ケアプラン作成や記録業務が大きな負担になっています。AIは利用者データをもとに必要情報を抽出し、作業の効率化とミス削減に貢献します。
たとえば「SOIN」は、蓄積されたデータからケアプランを提案し、職員の意思決定を支援。さらに、清掃・配膳などの定型業務もロボットで自動化が進み、対人ケアに専念できる時間が増加するでしょう。
結果として、業務負担の軽減だけでなく、人件費削減や運営効率の向上も実現しやすくなります。
参考:ケアマネージャーの業務を支援する次世代AIツールSOIN(そわん)|株式会社シーディーアイ
人手不足を補う手段として注目が集まり導入が進んでいる
介護業界は慢性的な人材不足に直面しており、2040年には57万人の人員不足が予測されています。このギャップを埋めるために、AIが有効な選択肢として導入が進行中です。
AIは単なる業務代替ではなく、職員の業務を補完し、人間にしかできないケアへ集中できる環境を整えます。送迎や見守りの自動化、会話ロボットによる認知機能支援などが導入され、現場の余力創出につながっています。
政府も補助金制度で導入を後押ししており、経営効率を高めたい企業にとってAIは注目すべき投資対象といえるでしょう。
参考:第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について|厚生労働省
介護業界のAI導入によって得られる5つのメリット

ここでは、介護業界のAI導入によって得られるメリットを5つ紹介します。
- 異変の早期察知によって迅速な対応が可能になる
- 送迎業務を最適化して効率的に運営できる
- ケアプランの作成支援によって質の高い介護を実現できる
- 職員の作業負担を軽減して心理的なゆとりが生まれる
- 高齢者の孤独感を和らげて安心感のある環境を提供できる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
異変の早期察知によって迅速な対応が可能になる
事故やクレームの発生は、介護施設にとって経営リスクに直結します。AI見守りシステムは、転倒・異常の兆候をリアルタイムで検知し、迅速な対応を可能にするでしょう。
たとえば「LASHIC」では、プライバシーに配慮しつつ体調変化も自動検知。「Rehab Cloud モーションAI」では、転倒リスクのある動作を事前に把握でき、未然の事故防止につながります。
事故を減らせることで、訴訟リスクや保険コストを抑えられる点も大きな経営メリットです。
送迎業務を最適化して効率的に運営できる
送迎計画は人手と時間を要し、現場の隠れたコスト要因になっています。AIは、交通状況や車椅子対応などを踏まえた効率的なルートを自動生成します。
「DRIVEBOSS」は、送迎ルートの可視化と計画時間の短縮を実現し、属人的な調整業務を削減。結果として、送迎業務に割かれる人員・稼働時間を抑え、月あたりの人件費削減にもつながるでしょう。
参考:送迎計画自動作成システムDRIVEBOSS|パナソニックカーエレクトロニクス株式会社
ケアプランの作成支援によって質の高い介護を実現できる
ケアプラン作成は、職員の経験と判断に依存しがちな業務のひとつです。AIを活用すれば、客観的なデータに基づいたプラン提案が可能になるでしょう。
「SOIN」は、過去のデータから個々の状態に応じた課題分析と支援提案を自動化。これにより1件あたりの作成時間が短縮され、業務の属人化リスクも回避しやすくなります。
職員の作業負担を軽減して心理的なゆとりが生まれる
離職率の高い介護業界では、職員の負担軽減が人材定着に直結する要素となります。AIによって、移乗・排泄介助や記録業務などの負荷の大きい作業が軽減されます。
職員が利用者との対話や個別ケアに集中できる環境が整うことで、やりがいを感じやすくなり、離職防止や採用コストの抑制にもつながるでしょう。
高齢者の孤独感を和らげて安心感のある環境を提供できる
コミュニケーションの質は、施設のサービス価値に直結します。
会話ロボット「PALRO」は、利用者と自然に会話し、笑顔や発語の機会を増やせられるでしょう。「パロ」のようなセラピーロボットは、精神的な安定を促し、心理的ストレスを軽減します。
結果として、施設の評判や満足度向上につながり、利用者獲得にも良い影響を与えるはずです。
参考:コミュニケーションロボットPALRO|富士ソフト株式会社
参考:メンタルコミットロボ_パロ|大和リース株式会社
介護業界のAI導入における3つの課題

ここでは、介護業界のAI導入における課題を3つ紹介します。
- 担い手不足のなかで介護ニーズが急増している
- 導入コストや運用面への不安が現場で障壁になっている
- 職員の不安や技術への抵抗感が活用を妨げている
それぞれ詳しく見ていきましょう。
担い手不足のなかで介護ニーズが急増している
人材の採用だけでなく、育成や定着にも課題を抱える事業所が増えています。
新しいスタッフを採用しても、OJTに割ける時間がなく、戦力化する前に離職してしまうケースも多いです。とくにAIやロボット導入を前提としたスキル育成は、通常業務と並行では手が回らないのが現実。
人材不足が続く中で、研修体制の未整備が技術導入の遅れを招くという悪循環に陥る施設もあります。
導入コストや運用面への不安が現場で障壁になっている
導入にかかる金額ではなく、効果の見通しが立てづらいことが意思決定のネックになっています。
「実際どれくらい削減できるのか」「どんな成果が出るのか」定量的に把握できるデータや比較材料が不足しているのです。結果として、AI導入は効果が不透明なコストとして扱われ、予算化されにくくなるでしょう。
選定・比較・試算といった導入前のプロセスに対し、客観的な判断材料がもっと求められている状況です。
職員の不安や技術への抵抗感が活用を妨げている
技術そのものへの不安というより、推進をリードできる人材や体制の不在が課題になっています。
中小の介護施設では、ICT推進担当者が不在で、導入を主導できる人がいないケースも多く見られます。「誰が管理するのか」「どう研修を回すのか」といった体制作りの準備が整わず、現場任せで頓挫してしまう場合もあります。
AIを現場に根づかせるには、導入だけでなく、その後の運用・教育を担う人材配置が欠かせません。
介護現場でのAI導入事例5選
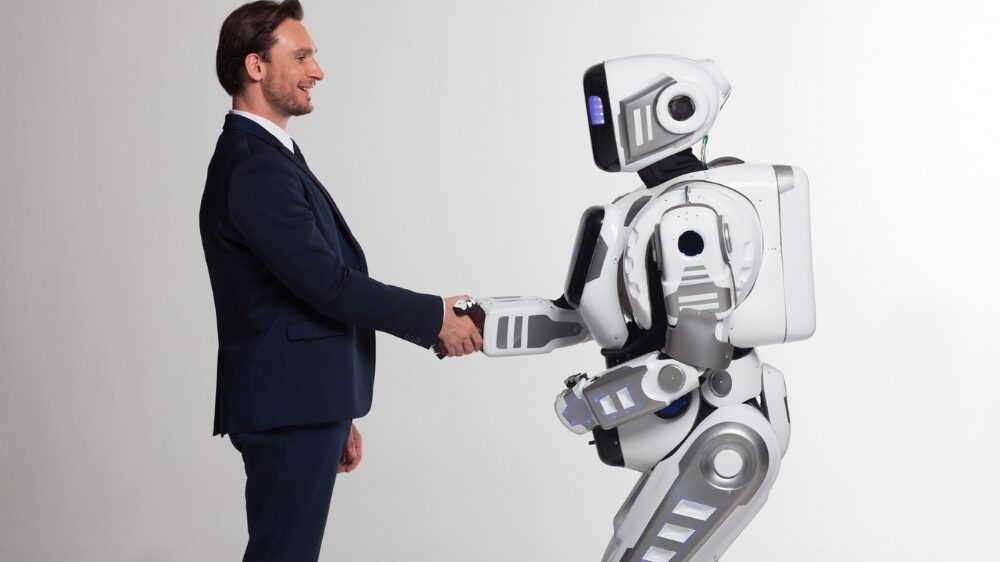
ここでは、介護現場でのAI導入事例を5つ紹介します。
- 福島県昭和村 × 凸版印刷「LASHIC+」(見守り支援)
- 神戸中央福祉会 塩屋さくら苑 × パナソニック「DRIVEBOSS」(送迎計画支援)
- 新潟県上越市 丸互 & NTT東日本「tsuzumi」(記録業務自動化)
- 芙蓉グループ(筑紫南ヶ丘病院)「安診ネット カイゴDX」(健康管理・重度化予防)
- 社会医療法人仁寿会 グループホームかわもと × 富士ソフト「PALRO」(コミュニケーションロボット)
それぞれ詳しく見ていきましょう。
福島県昭和村 × 凸版印刷「LASHIC+」(見守り支援)
福島県昭和村と凸版印刷は、独居高齢者向けの見守りシステム「LASHIC+」の実証実験を実施しました。
このシステムは、カメラを使わずに人感・温湿度・ドア開閉などの情報をセンサーで取得し、AIが行動パターンの変化から異常を検知します。職員へ通知されるタイミングも最適化されており、定期訪問の内容を見直すことで業務効率の改善とケアの質向上が可能。
特に、孤独死のリスクが高い高齢者に対する早期対応や異常の可視化が進む点が評価されています。
神戸中央福祉会 塩屋さくら苑 × パナソニック「DRIVEBOSS」(送迎計画支援)
塩屋さくら苑では、送迎業務がベテラン職員に依存しており、急な休職などで計画が破綻するリスクがありました。
そこで導入された「DRIVEBOSS」は、利用者の制約条件を登録するだけで、送迎ルートや順番を自動生成できる仕組みです。職員交代にも柔軟に対応できるようになり、属人化の解消と効率化の両立が実現しました。
サービス提供の安定性が高まり、家族からの信頼向上にもつながった点は特筆すべき成果です。
新潟県上越市 丸互 & NTT東日本「tsuzumi」(記録業務自動化)
NTT東日本と丸互は、介護現場の記録作業に着目し、大規模言語モデル「tsuzumi」による音声記録の自動化に取り組みました。
これまでキーボード入力に時間を取られていた業務が、音声入力から文章変換される仕組みによって短縮可能。実証実験では、1人あたりの1日の介護記録の登録にかかっていた時間を、39分から17分へ削減という明確な成果が出ています。
削減された時間は、利用者とのコミュニケーションやケアの質向上に活かされています。
芙蓉グループ(筑紫南ヶ丘病院)「安診ネット カイゴDX」(健康管理・重度化予防)
芙蓉グループ傘下の芙蓉開発が展開する「安診ネット カイゴDX」は、AIを活用した遠隔健康モニタリングシステムです。
毎日のバイタルデータに加えて、職員による主観記録や既往歴なども分析対象に組み込み、AIが異常値を早期に検出。異変を見逃さず通知できる仕組みにより、症状が出る前に医療対応へとつなげられる体制が強化されています。
高齢者特有の“自覚症状の少なさ”に対応したこの仕組みは、重症化予防の観点からも注目を集めています。
社会医療法人仁寿会 グループホームかわもと × 富士ソフト「PALRO」(コミュニケーションロボット)
社会医療法人仁寿会グループホームかわもと「あいあいの家」では、富士ソフトの「PALRO」を導入し、職員と利用者双方の心理的負担軽減を目指しました。
当初は職員からの戸惑いもありましたが、4段階の定着支援策と研修により運用がスムーズに進行。PALROは話しかけたりリアクションを返したりすることで、利用者の笑顔や会話の頻度を増やし、認知症予防の一助にもなっています。
ロボットが職員の業務を支援し、人にしかできないケアに集中できる時間を生み出した点が大きな評価ポイントです。
介護ロボットの主なタイプ
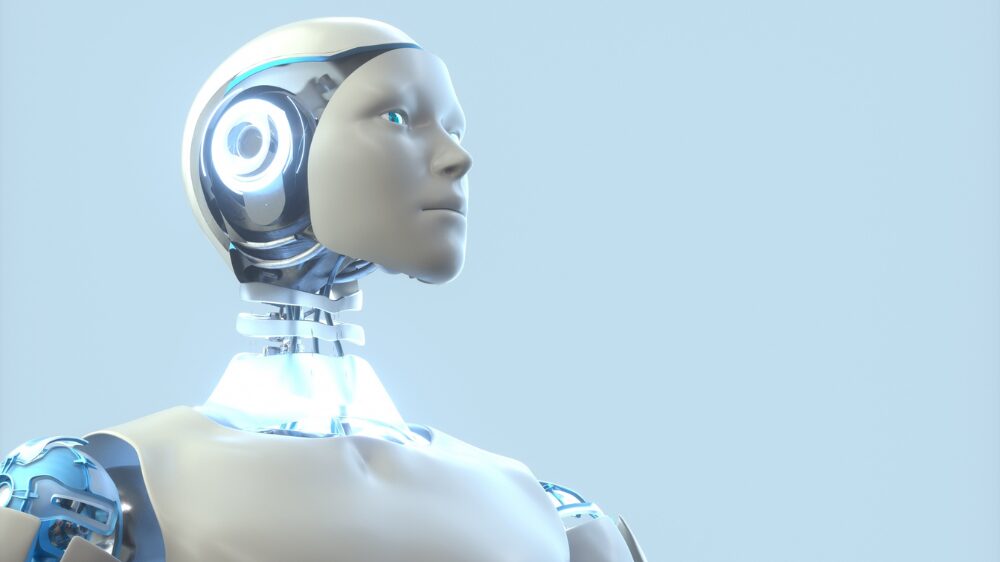
ここでは、介護ロボットの主なタイプを7つ紹介します。
- 移動支援ロボット
- 移乗支援ロボット
- 見守り・コミュニケーションロボット
- 排泄支援ロボット
- 入浴支援ロボット
- 業務支援ロボット
- 健康管理ロボット
それぞれ詳しく見ていきましょう。
移動支援ロボット
歩行が不安定な高齢者の移動を安全に支援するロボットです。
センサーとAIにより、周囲の環境や利用者の動きを検知し、自動で速度や方向を調整します。また、夜間の見回りや物品運搬、転倒検知にも対応できる多機能モデルも存在し、職員の見守り負担を軽減できるでしょう。
移動の自立を後押しすることで、生活の質向上にもつながります。
移乗支援ロボット
ベッドから車椅子などへの移動を補助し、介護者の身体的負担を軽減するロボットです。
装着型はパワーアシストで介助をサポートし、非装着型は自動で移乗できます。腰痛や疲労リスクの低減だけでなく、利用者にとっても安心感のあるケアが叶います。
見守り・コミュニケーションロボット
利用者の安全管理と精神的ケアの両面を担うロボットです。
センサーで動きを検知し、転倒などの異常時には即座に職員へ通知します。また、対話機能で会話や脳の刺激を促し、孤独感の緩和や認知機能の維持にも効果が見込めるでしょう。
排泄支援ロボット
排泄のタイミングを予測し、介助を最適化するロボットです。
センサーとAIによって、排泄の兆候を検知し、事前に職員へ知らせる仕組みが活用されています。ベッド脇に設置できる水洗式のロボットも登場し、臭いや処理の手間を減らすことで環境改善にもつながっています。
入浴支援ロボット
入浴時の移動や洗体を補助し、転倒リスクや身体負担を軽減するロボットです。
体を持ち上げる機能や洗体の補助機能を備え、安全性と清潔感の両立が図れます。浴室での重労働を軽減し、職員の腰痛予防やケア効率の向上にも役立つでしょう。
業務支援ロボット
清掃・除菌・配膳といった定型業務を自動化するロボットです。
施設全体の掃除や食事の配膳をロボットが担えば、職員は直接的なケアに集中できるでしょう。日常業務の効率化を通じて、人手不足の緩和とサービス品質向上が期待できます。
健康管理ロボット
体調や生活データを常時モニタリングし、異常を早期に察知するロボットです。
心拍数や動作パターン・睡眠状態などをAIが解析し、異変があれば職員に通知します。早期対応とケアプランの最適化に活かせば、介護の質全体の底上げにつながるでしょう。
AIやロボットは介護の現場で役立つのか

介護現場では、人手不足とニーズの増加という大きな課題に直面しています。この状況で、AIやロボットの導入は業務を支え、ケアの質を高める手段として注目されています。
AIは、記録やケアプラン作成、見守りといった事務的な作業を効率化し、職員の負担を減らす役割を担います。時間と体力の余裕が生まれれば、より丁寧なケアに向き合える環境が整うでしょう。
ロボットは移動・移乗・入浴といった身体的な介助を補い、現場の安全性と作業効率を高めます。利用者にとっても、安心して過ごせる空間づくりに役立つでしょう。
ただし、初期費用や運用体制の整備、現場での不安や戸惑いといった課題も無視できません。こうした壁に向き合いながら、少しずつ現場に浸透させていくのが成果につながるはずです。
介護業界でのAI導入事例を参考にしてビジネスを効率化させよう

本記事では、介護業界におけるAIの活用事例や導入メリット、直面する課題について解説してきました。
AIは業務負担を軽減し、現場の人材不足を補う有効な手段です。しかし、導入効果が見えづらいことや現場の不安感がハードルになるケースも多くあります。
【介護現場にAIを導入するためのヒント】
- 現場目線で導入事例を確認し、ROIの具体化を図る
- 段階的な導入で技術への抵抗感を軽減する
- 人材の代替ではなく支援ツールとして位置づける
介護業界のAI導入事例を参考に、自社へのAI導入検討を進めてみてください。